ある日、仕事中にスマホが鳴りました。
母が倒れて救急搬送されたという知らせでした。
慌てて病院に駆けつけると、母はベッドの上で意識はあるものの、右半身が動かない状態。
医師からは「脳梗塞です。しばらく入院が必要になります」と告げられました。
その瞬間、私の中で「介護」が現実のものになったのです。

1.あの日、突然やってきた“介護のはじまり”
母はこれまで大きな病気もせず、どちらかといえば元気なタイプでした。
「うちの親はまだ大丈夫」そんな根拠のない自信がありました。
でも、介護はある日突然、やってきます。
入院初日、医師との面談で「後遺症が残る可能性があります」
「日常生活にも支援が必要になります」と説明され、頭が真っ白になったのを覚えています。
突然の事態に追いつかない気持ち
何をどうしたらいいのか分からず、ひとまず会社に連絡し、休みをもらいました。
その夜は病院近くのビジネスホテルに泊まり、眠れぬまま翌朝を迎えました。
現実感がなく、「明日には元に戻ってるんじゃないか」と思いたい気持ちと、
「これからどうすれば…」という不安が交錯していました。

「介護が始まる」ってどういうこと?
家族が倒れて初めて、「介護」という言葉が現実味を持ち始めます。
でも、いざその場になると、制度も仕組みも分からないまま、
目の前のことに追われ続ける毎日でした。
2.病院とのやりとり、家族とのすれ違い
母の容態が安定した数日後、病院から「今後の生活について考える必要があります」と言われ、
退院後のことを検討するよう促されました。
ソーシャルワーカーとの面談
病院のソーシャルワーカーさんから、
介護保険の申請や在宅介護、施設入所の選択肢などの説明を受けました。
その時点で初めて「要介護認定」という言葉を知りました。
兄弟間での意見の違い
実家で母を看る案、施設に預ける案…。
兄は「施設のほうが安心だ」と言い、私は「せめて最初は家で看たい」と言い張りました。
どちらも悪くない考えなのに、話し合いはすれ違いばかり。
「なんでそんな冷たいの?」「お前が全部やる気か?」と、口論になることもありました。

誰も悪くないけど、うまくいかない
今振り返ると、みんな不安で、正解が見えなくて、言葉が荒くなっていたんだと思います。
介護が始まる時、家族の関係性は大きく揺さぶられます。
一人では抱えきれないと、初めて感じました。
3.初めて知る介護の制度と現実
「介護保険って、どうやって使うの?」
病院で紹介された地域包括支援センターに連絡すると、
ケアマネジャーの方が親身に相談に乗ってくれました。
「要介護認定を申請して、結果が出るまでに1か月ほどかかります」
「その間も必要に応じて、暫定的にサービスは使えますよ」
知らない言葉ばかりで最初は戸惑いましたが、少しずつ仕組みが見えてきました。
在宅介護か、施設入所か
母は要介護2と認定されました。
リハビリが必要で、日常生活では入浴やトイレ介助が必要とのこと。
ケアマネジャーは「在宅で支えるなら訪問介護やデイサービスの利用を」と提案してくれました。
でも私は、「家で本当にできるの?」「仕事との両立は?」と不安が募るばかり。

退院日が迫る焦り
入院から3週間が経ち、病院から「そろそろ退院先を決めてください」と連絡が。
施設の空きはなく、結局、いったん自宅に連れて帰ることに。
その時の私は、“介護をする覚悟”がまだ十分にできていなかったと思います。
4.私が直面した心と生活の変化
1日があっという間に終わる
退院してからの母は、思った以上に介助が必要でした。
トイレ介助、着替え、食事の世話、リハビリの付き添い…。
気づけば自分の時間はゼロ。
それまでは仕事終わりに友人と食事をしたり、映画を観たりしていたけれど、そんな日々は一変。
「こんなはずじゃなかった」と思う自分
ある夜、母がトイレで転びそうになり、思わず強い口調で言ってしまいました。
「危ないって言ってるでしょ!」
母は黙ってうつむき、私はその背中を見て自己嫌悪に襲われました。
「もっと優しくしたい」
「でも疲れて余裕がない」
そんな矛盾した気持ちでいっぱいでした。

まわりに頼るのが怖かった
「きっと、他の人はもっと上手にやってる」
「こんなことで弱音を吐いたらいけない」
そう思い込んで、誰にも本音を言えずにいました。
でも、ケアマネジャーさんが何気なく言ってくれた
「みんな最初は同じですよ。うまくいかなくて当然です」
という言葉に、ふっと肩の力が抜けました。
「頼っていい」と思えた瞬間
ある日、母のデイサービス初日。
スタッフの方がにこやかに母を迎え入れ、
レクリエーションや入浴介助まで丁寧に行ってくれました。
迎えに行ったとき、母が「楽しかったよ」と笑ったのを見て、涙が出ました。
「全部自分がやらなくてもいい」
「プロにお願いしても、母はちゃんと笑える」
その時初めて、“介護は一人で抱え込むものではない”と実感できました。

5.「一人じゃない」と思えるまでの道のり
小さなつながりに救われる
母がデイサービスを利用するようになってから、少しずつ私の生活にも余裕が出てきました。
デイの送迎中、スタッフの方と話す時間ができたり、
同じように親を介護している利用者家族と雑談するようになったり。
「実はうちも、最初はお風呂が大変で…」
「私なんて、毎日泣いてたよ〜」
そんな言葉に、「私だけじゃないんだ」と心が軽くなりました。
介護の情報は“人”から入ってくる
インターネットや本では得られない、リアルな情報。
それは、やっぱり現場にいる人たちとの会話からでした。
「あの施設、空き出たみたいよ」
「この福祉用具、便利だったよ」
何気ない会話が、大きなヒントになることもあります。
母との関係が少しずつ変わった
最初は、「介護する側・される側」という意識が強く、私自身も構えていました。
でもある日、母が私の手を握って
「ありがとうね。あんたがいてくれてよかった」と言ってくれたのです。
その一言で、張り詰めていた何かがほどけていきました。
「親だからって、ずっと強いわけじゃないんだ」
「弱い姿を見せてくれるのも、信頼のひとつなんだ」
そう思えるようになってからは、少しずつ心が楽になりました。

※この記事は筆者の実体験ではなく、複数の体験談や調査をもとに構成したフィクションです。
誰にでも起こりうる突然の介護の始まりを少しでも想像してもらえたらと願って書きました。
6.まとめ:介護が始まったあなたへ伝えたいこと
1. 「突然」は誰にでも起こる
介護は、ある日突然やってくることがあります。
心の準備がなくても、それは誰のせいでもありません。
だからこそ、焦らずに、ひとつずつ目の前のことをこなしていくことが大切です。
2. 「全部ひとりでやろうとしない」
最初は「家族だから自分が頑張らなきゃ」と思いがちですが、
介護は一人で背負うにはあまりにも大きなテーマです。
支援制度、ケアマネ、デイサービス、友人、きょうだい…。
頼れるところは、遠慮せずに頼っていいんです。
3. 「気持ちを話せる場所を持つ」
誰にも言えない本音がたまっていくと、心が疲れてしまいます。
愚痴をこぼせる人、話を聞いてくれる人がひとりでもいるだけで、
介護はずいぶん違って感じられます。
「私、今日すごくしんどかった」
「なんか泣きたくなっちゃった」
そんな一言が、あなたの心を守ってくれます。
4. 「いつか終わる日が来る」
介護は、永遠には続きません。
いつか、終わりの日が来ます。
そのときに後悔しないようにできる範囲で、あなたらしく、
親との時間を過ごせたら、それで十分だと思います。
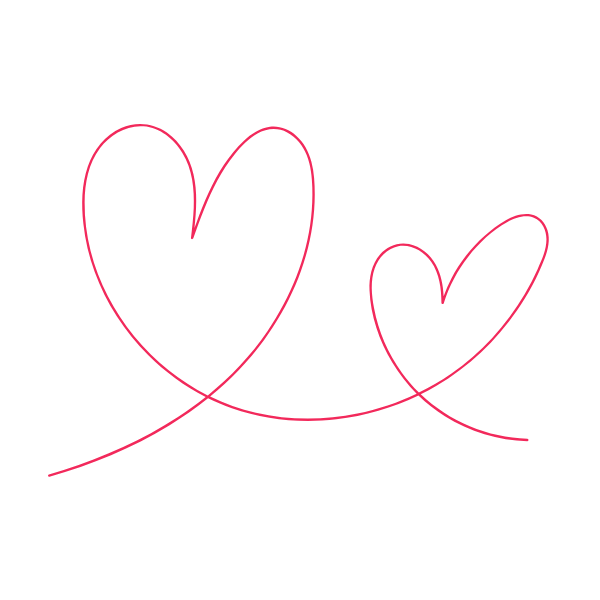
7.さいごに
親が突然倒れてから、ほとんどの人はいろんなことを知ります。
制度のこと、心の揺れ、人のありがたさ。
そして、「介護は、つらいだけじゃない」ということも。
不安でいっぱいのあなたに、少しでも寄り添えたらという思いでこの文章を書きました。
無理せず、でも諦めずに。
ときには立ち止まっても、また歩き出せばいい。
あなたが、あなた自身のことも大切にしながら、介護と向き合えますように。
いつも応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
参考
- 厚生労働省「急な介護が必要になったときの対応ガイド」
- 東京都福祉保健局「高齢者支援サービスのご案内」
- NHK福祉ポータル ハートネット
- 全国社会福祉協議会「生活支援体制整備事業 関連資料」
- NHK福祉特集「突然始まる介護〜その時、家族は〜」




コメント