こんにちは。
「もう限界かも…」「私だけが頑張ってる気がする…」「何でこんなに苦しいんだろう…」
あなたは今そんな気持ちでこのページを開いてくれていますか。
そんなあなたに、どうか知ってほしいことがあります。
そんな気持ちを持ってしまうのは、あなただけではないんです。
介護をしている方ならきっとみなさん同じ気持ちです。
疲れ果て、涙があふれ、ときには逃げ出したくなることだってあるんです。
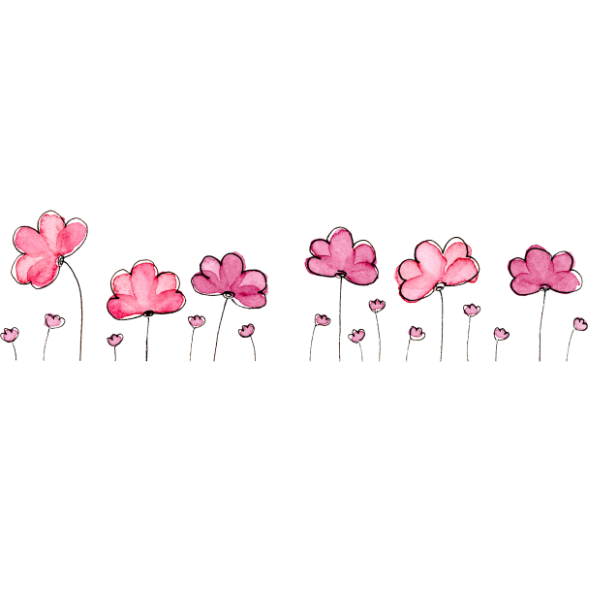
介護が「しんどい」と感じる
まず大前提として、介護は心も体も想像以上にエネルギーを使う行為です。
身体的な疲労はもちろんのこと、時間の拘束、生活の制限、仕事や人間関係との両立、
そして「感情の揺れ」——それらが積み重なることで、介護者の中には大きなストレスや
孤独感を抱える方が少なくありません。
「家族なんだから当たり前」「私がやらなきゃ」という責任感が強い人ほど、
自分の気持ちを押し殺してしまいがちです。
「しんどい」「つらい」「もう嫌だ」と思う気持ちがあるのは、
あなたが一生懸命に向き合っている証拠なんです。
感情は押し込めないで、「今、私はしんどい」と自分で認めてあげることから、
少しずつ心の整理が始まります。
「なんで私ばかり…」と思ってしまうとき
「兄弟は協力してくれない」
「パートナーが他人事のような顔をしている」
介護の日々、こうした不満が蓄積されていきます。
そしてある日突然、心の中で「爆発」が起きる。
「誰もわかってくれない」「もうやりたくない」
そう思う自分を責めないでください。
それは、あなたが“限界までがんばってきた証”です。
人は限界を超えてまで誰かに尽くすことはできません。
だから、ひとりで抱えすぎないで下さい。
「協力してほしい」「手伝って」と伝える勇気が、
あなたを守る第一歩です。
[PR]介護うつという現実
実は、介護者の4人に1人が「介護うつ」に悩んでいるというデータもあります。
症状は人によってさまざまですが、「朝起きるのがつらい」「物忘れが増えた」「急に涙が出る」
といったサインがある場合、それは心が「もう無理だよ」と訴えているのかもしれません。
特に真面目で優しい人ほど、
「こんなことで疲れる自分はダメなんだ」と自分を責めてしまいがち。
でも、責める必要なんてありません。
まずは、自分の感情に気づき、認めること。
そして信頼できる人に少しでも話してみること。
言葉にするだけで、心はずいぶん軽くなることもあります。
「うつ」という言葉に抵抗がある方もいますが、疲れが心にまで及ぶことは自然なことです。
心が風邪をひいているようなもの、と考えてください。
しっかり休み、必要なら専門家に頼ることも、立派な回復の一歩です。
「手を抜く」ではなく「手を借りる」こと
介護サービスやデイサービス、ショートステイ、訪問介護、家事代行…。
最近はたくさんのサポートがあります。
でも、なぜか「そんなの甘えじゃないか」
「家族を他人に任せるなんて」と感じてしまう人もいます。
でも、あなたが風邪をひいたとき、ご飯を作ってもらったり、
代わりに掃除してもらったりすると、ほっとしませんか?
介護も同じです。
体も心も疲れたときに「少し休む」というのは、自分を守るための大切な選択。
これは「手を抜く」のではなく、「手を借りる」という当たり前の行為です。
実際にデイサービスや訪問介護を活用し始めた人たちは、
「もっと早く使えばよかった」と口を揃えて言います。
それくらい、心にゆとりが戻ることに意味があるのです。
介護と仕事、家事、育児…どうしてこんなに大変なの?
いわゆる“ダブルケア”“トリプルケア”と呼ばれる状況の方も増えています。
子育てをしながら親の介護。
仕事を抱えながら家事と通院付き添い…。
それらをすべて1人でこなそうとすれば、時間も気力もあっという間に底を尽きます。
「がんばること」が当たり前になりすぎて、自分のキャパシティに気づかないこともあるんです。
まずは「全部を完璧にやるのは無理」と認めてください。
そして、優先順位をつけてみてください。
「今日はこれだけで十分」そう思える日が増えてくると、気持ちが少しずつ変わってきます。
洗濯が1日遅れても、夕飯がレトルトになっても大丈夫。
あなたが倒れてしまったら、介護そのものが立ちゆかなくなってしまいます。
[PR]共感できる人とつながる
介護について話せる人、愚痴を言える人、ただ話を聞いてくれる人がいること。
それだけで、心の重さは半分になります。
たとえ5分でも、「わかってくれる誰か」との会話は、想像以上の癒しになるんです。
また、福祉施設の職員さんや地域包括支援センターの方など、専門家に話すことで、
想像もしなかったサポート制度を知ることができることもあります。
「しんどい気持ち」を受け止めることから始めよう
介護をしていると、どうしても「自分の感情は後回し」になりがちです。
でも、あなた自身の心が元気じゃなければ、どんなに手を尽くしても空回りしてしまいます。
「しんどい」「疲れた」「逃げたい」そんな気持ちが出てくるのは自然なこと。
むしろ、それだけ真剣に向き合っているからこそ生まれる感情です。
今の自分を否定せず、ありのままを受け止めること。
そこからしか、次の一歩は生まれません。
日記に書く、スマホのメモに残す、それだけでもいいので、
今の気持ちにフタをせず、そっと自分に声をかけてあげてください。
[PR]最後に
「介護がしんどい」と感じるのは、決して弱さではありません。
それはあなたが、今日まで一生懸命に、大切な誰かと向き合ってきた証拠です。
全国のたくさんの介護者たちが、同じように悩み、迷いながら、
それでも一歩一歩を歩いています。
どうか無理をしすぎないで下さいね。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 厚生労働省「介護者支援マニュアル」
- 内閣府「高齢社会白書(介護と仕事の両立に関する調査)」
- 認知症介護研究・研修仙台センター「介護者のこころのケア」
- 公益社団法人認知症の人と家族の会「一人で抱え込まないために」
- 介護者支援ガイドブック(厚生労働省監修)

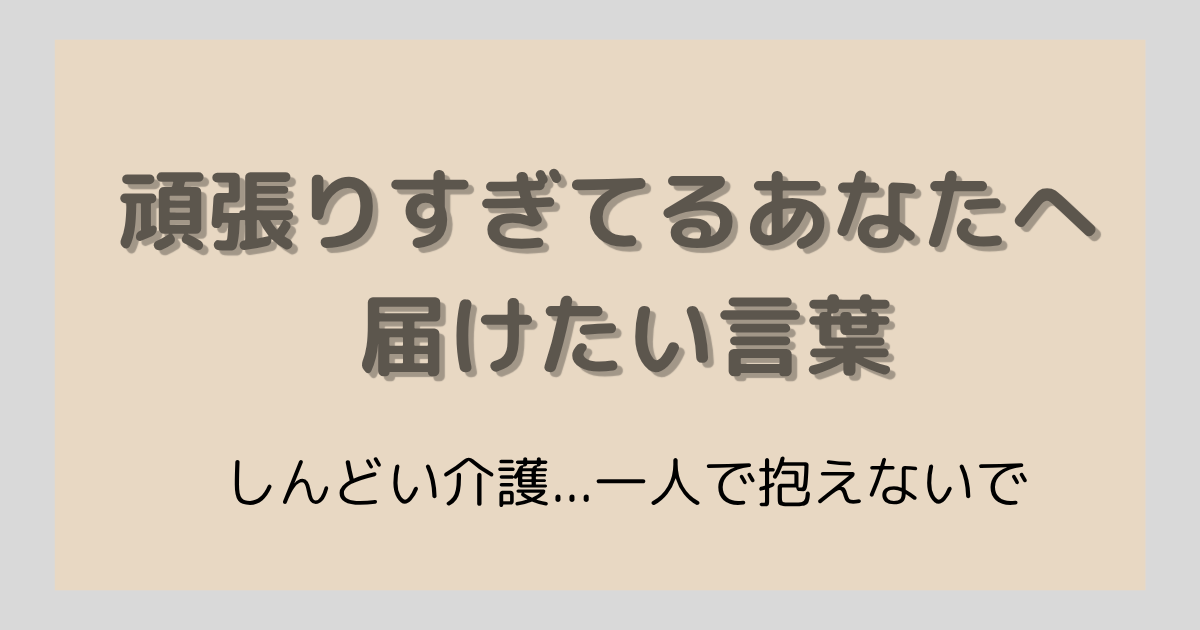


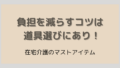
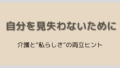

コメント