こんにちは。
「親の介護、そろそろ考えないと…」と思ったときに、真っ先に浮かぶのが
「お金」のことではないでしょうか。
実際、介護が始まると想像以上に出費が増えます。
たとえば、介護用品の購入、通院の交通費、施設の利用料など…。
積み重なると家計への負担が大きくなるのも無理はありません。
ただ、心配しすぎる必要はありません。
国の公的制度に加え、民間の介護保険などをうまく組み合わせることで、
経済的な不安をやわらげることができます。
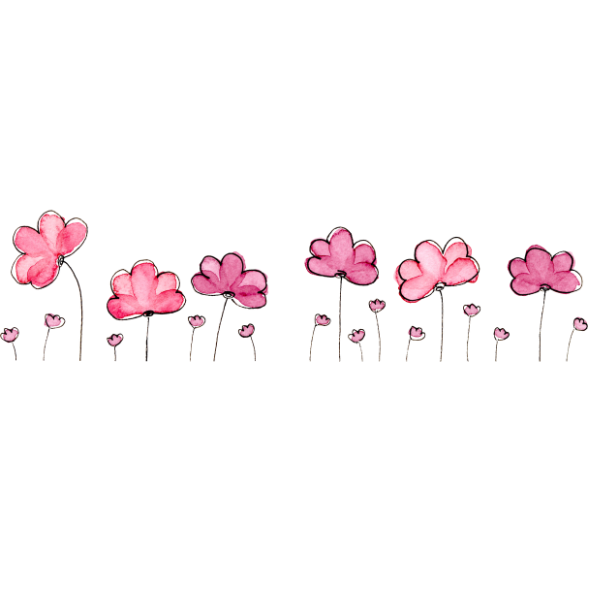
まずは知っておこう!介護にかかる主な費用
介護の費用は人によって大きく異なりますが、大きく分けると次のような支出があります。
① 介護サービス費(デイサービス、訪問介護など)
② 介護用品費(オムツ、介護ベッド、福祉用具など)
③ 医療費・通院費
④ 住環境の改修費(手すり設置や段差解消など)
⑤ 食費・光熱費などの生活費
厚生労働省の調査によると、在宅介護では月に平均約8万円前後、
施設介護では月に約20〜25万円ほどかかるケースが多いと言われています。
もちろん、介護度や地域によっても違いますが、「思ったよりかかるな…」
と感じる方が多いのも事実です。
介護保険でカバーできる部分をチェック
介護保険制度を使えば、介護サービスにかかる費用の一部(原則1〜3割)を
自己負担するだけで済みます。
つまり、実際のサービス費用の7〜9割は国が負担してくれる仕組みです。
たとえば、要介護認定を受けてデイサービスを利用する場合、
1回5000円のサービスなら自己負担は500〜1500円程度。
とても助かる制度ですよね。
ただし、介護保険でカバーできるのは「認定を受けた範囲のサービス」に限られます。
食費やおむつ代、居住費などは自己負担となるため、
そこが経済的な負担として残ってしまうのです。
「民間の介護保険」で備えるという選択
そんなときに役立つのが「民間の介護保険」です。
生命保険会社などが販売しており、介護が必要になったときに
まとまった一時金や年金が受け取れるタイプがあります。
代表的なのは次の2種類です。
① 介護一時金タイプ:
要介護状態になったときに、100万円〜500万円などのまとまった金額を受け取れるタイプ。
② 介護年金タイプ:
介護状態が続くあいだ、毎年または毎月一定額を受け取れるタイプ。
どちらが良いかは、生活の状況によります。
まとまった資金が必要な人は一時金タイプ、
毎月の生活費を安定させたい人は年金タイプが向いています。
保険料は年齢や加入時期で大きく異なりますが、
早めに検討しておくと負担が軽く済む場合が多いですよ。
とはいえ、「民間保険って難しそう…」「本当に必要?」と思う方もいるかもしれません。
次で、民間介護保険のメリット・デメリットと、知っておくと安心な補助制度について、
さらに詳しくお話ししていきます。
[PR]民間介護保険のメリットとデメリット
民間の介護保険は、「介護保険制度ではカバーできない部分を補う」ための強い味方です。
でも、どんなものにもメリットとデメリットがあります。
ここではその両面を見ていきましょう。
メリット① 介護状態になったときにすぐ使える安心感
たとえば、親が突然倒れて要介護状態になったとき。
介護用ベッドや車いすをそろえたり、リフォームをしたりと、初期費用が一気にかかります。
そんなとき、民間介護保険の一時金を受け取れると、
経済的な心配をせずに必要な準備ができます。
また、介護が長引く場合でも、年金タイプの保険で毎月一定額を受け取れると、
生活費の支えになります。
「介護うつにならないよう、少しでも気持ちに余裕を持てる」
という安心感も大きいポイントです。
メリット② 使い道が自由
公的介護保険では、利用できるサービスがあらかじめ決まっています。
でも民間の介護保険は、受け取ったお金を自由に使えるのが特徴です。
介護サービスの自己負担に充ててもいいし、ヘルパーさんを増やしたり、
介護者の休息費用に使ってもOK。
使い勝手の自由度が高いんです。
デメリット① 保険料の負担がある
当然ながら、加入するには毎月(または年払い)の保険料を支払う必要があります。
年齢が上がるほど保険料も高くなるため、「どのタイミングで入るか」が大切になります。
目安としては50代前半くらいからの検討がおすすめです。
デメリット② 条件によっては支払い対象にならないことも
保険によっては「要介護2以上」など、支払いの条件が設定されています。
つまり、「軽い介護状態」では給付の対象外になる場合もあります。
契約前に必ず「支払い条件」と「認定基準」を確認しておくことが大事です。
[PR]民間保険だけじゃない!公的な補助制度も活用しよう
介護の負担を減らすために、国や自治体にはさまざまな補助制度があります。
「そんな制度あったの?」と思うような支援もありますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
① 高額介護サービス費制度
介護保険を使っても、1か月の自己負担額が一定の上限を超えた場合、
その超えた分が払い戻される制度です。
所得に応じて上限額が決まっており、たとえば一般的な世帯なら月額4万4000円が上限です。
つまり、どれだけ介護サービスを利用しても、自己負担はその上限までで済むという仕組み。
知らないと損をしてしまう制度のひとつです。
② 高額医療・高額介護合算制度
これは医療費と介護費の両方がかさんだ場合に、合計して上限を設けてくれる制度です。
介護と通院・入院が同時に発生することも多いので、該当する方はぜひ利用を検討しましょう。
③ 福祉用具購入費の支給
要介護認定を受けていれば、特定の福祉用具(歩行器やシャワーチェアなど)の購入費を、
年間10万円まで支給してもらえる制度があります。
実際には自己負担は1〜3割ほど。
こまめに申請しておくと、思ったより出費が抑えられます。
④ 住宅改修費の支給
「段差をなくしたい」「手すりをつけたい」といった住宅改修にも、
最大20万円までの補助が受けられます。
工事の前に申請が必要なので、ケアマネジャーさんに相談して進めるのが安心です。
情報を得るにはどこに相談すればいい?
補助制度は自治体によって内容や申請方法が少しずつ違います。
まずは「地域包括支援センター」に相談してみましょう。
制度の紹介だけでなく、あなたやご家族の状況に合わせて最適な方法を提案してくれます。
最近では、市区町村のホームページでも分かりやすい資料を掲載しているところが多いので、
チェックしてみるのもおすすめです。
次は、実際にどう組み合わせて使うと家計が助かるのか、
そして家族でお金の話をするコツをお伝えしますね。
[PR]保険と補助制度をどう組み合わせる?
介護費用の不安を軽くするには、「どれか1つに頼る」のではなく、
公的制度+民間保険+家族の支えをうまく組み合わせることがポイントです。
たとえば、介護保険で基本的なサービスをまかないつつ、
どうしても自己負担が発生する部分を民間の介護保険でカバーする。
さらに、高額介護サービス費制度などの補助を申請して、実際の支出を減らす。
この流れを意識しておくだけでも、心の負担はぐっと軽くなります。
また、「どの制度を使えるか」を定期的に確認しておくことも大切です。
要介護度が変わると、使えるサービスや上限額も変化するため、
半年〜1年に一度はケアマネジャーさんと一緒に見直すのがおすすめです。
介護費用を家族で話し合うときのコツ
お金の話は、どうしても避けがちなテーマですよね。
でも、介護が始まってから慌てるより、元気なうちに話し合っておくことが、
家族みんなの安心につながります。
① 「誰が負担するか」ではなく「どう支えるか」で話す
「お金の負担をどう分けるか」という話し方よりも、
「どうすれば親の生活を支えられるか」という視点で話すと、空気がやわらぎます。
金額よりも、気持ちの共有から始めるのがコツです。
② ケアマネジャーや第三者を交えて話す
家族だけで話すと感情的になりがちですが、ケアマネジャーさんや社会福祉士を交えることで、
冷静に現実的な話がしやすくなります。
特に補助制度や助成金については、専門家の意見を取り入れると無駄なく利用できます。
③ 介護費用は「見える化」しておく
毎月の介護費用や補助金の申請状況などを、ノートやアプリで記録しておくと、
誰が見ても分かりやすくなります。
「今月はこんな支出があったね」「次はここを工夫しよう」と
家族の話し合いもスムーズになります。
[PR]民間保険に入る前に確認しておきたい3つのポイント
もし民間の介護保険を検討しているなら、次の3つをチェックしておくと安心です。
① 介護状態の定義(どの段階で給付対象になるか)
② 給付金の受け取り方法(一時金 or 年金タイプ)
③ 支払い免除の条件(要介護になった後の保険料がどうなるか)
パンフレットを見ただけでは分かりづらい部分もあるので、
保険会社の担当者やFP(ファイナンシャルプランナー)に相談するのが確実です。
最後に
介護費用の心配は、多くの人が抱える悩みです。
でも、制度や保険の仕組みを知ることで、
「どうにかなるかもしれない」という希望が見えてきます。
国の介護保険制度に加え、民間の介護保険や自治体の補助を上手に活用すれば、
「お金の不安」に押しつぶされず、介護そのものに集中できます。
何より大切なのは、ひとりで抱え込まず、
行政・専門職・家族と手を取り合って進めることです。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 「介護保険制度の概要」厚生労働省
- 「高額介護サービス費」大阪市
- 「介護保険福祉用具購入費の支給について」京都市
- 「介護で活用できる補助金制度を8つ紹介」朝日生命
- 「民間の介護保険の必要性やメリット・デメリット、選び方」ほけんの窓口

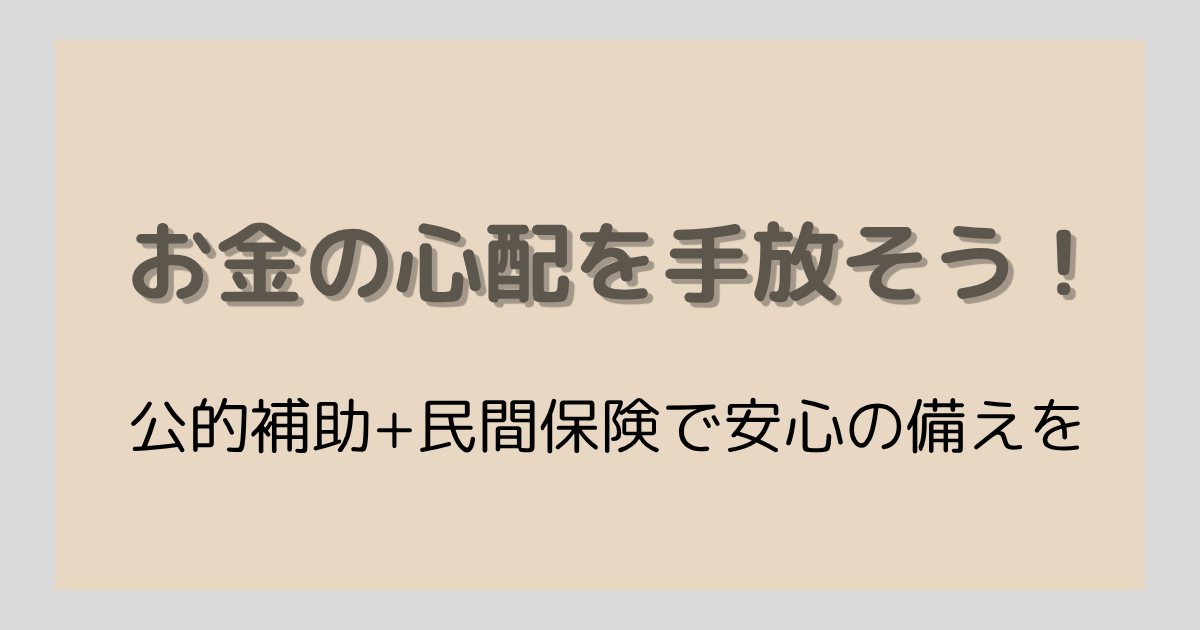

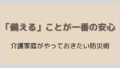
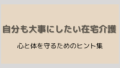

コメント