こんにちは。
今日は、私自身が実際に体験して衝撃を受けた「要介護認定の申請」と、
その裏側にある“書類の山”についてお話ししていきます。
親や家族が年齢を重ねると、どうしても「介護」というキーワードが
生活の中に顔を出すようになります。
私も以前祖母のために、母と介護認定を申請したのですが、手続きに入ってすぐに
「これは…まるで書類との戦いだ!」と実感させられました。
今回の記事は、申請の流れの中で出てくる手続きや準備書類を実体験に基づいて紹介しつつ、
「これから申請するよ」という方の心の準備になるようにまとめています。
少しでも参考になれば幸いです。
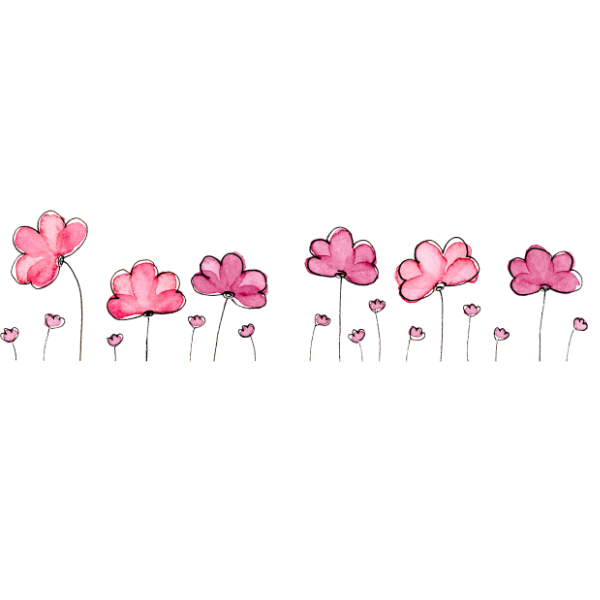
最初の試練:役所に電話してみた
まず最初に「要介護認定を受けたい」と思ったとき、
多くの人は市区町村の介護保険担当窓口に連絡します。
私たちも例にもれず、祖母の住民票のある役所へ電話をしました。
電話口の担当者さんはとても丁寧で、「必要な書類一覧を送りますね」と案内をしてくれました。
この時は正直、“なんだ、思ったより簡単そうだな” と油断していたんです。
でも、数日後にポストに届いた分厚い封筒を開けた瞬間…
まるで大学入試の願書のような大量の紙が飛び出してきました。
中には「申請書類一式」「医師意見書の依頼用紙」
「介護保険被保険者証を添えて提出してください」といった案内がぎっしり。
説明文を読むだけでもうんざり…。
まさに「書類との長い戦い」の始まりでした。
書類A:介護認定申請書
最初に立ちはだかるのが、申請そのものの基本となる「介護認定申請書」。
これは申請者本人や家族が記入するものです。
名前や住所、保険証の番号などの基本情報に加え、連絡先や同居している家族構成など、
かなり細かく書き込む欄があります。
さらに「介護が必要になった理由」や「どのような日常の困難があるか」を記入する欄もあって、
ここで早くもペンが止まることに。
祖母の日常生活を思い出して一つひとつ「これはできる」「これは難しい」と書いていくのです
が、正直こういうことは普段あまり冷静に振り返らないので、文字に落とし込むのが大変でした。
「えーと、入浴は…完全に一人では無理。でも着替えはまだ自分でできるかな?」
と迷いながら書き込んでいくと、用紙はあっという間に時間泥棒に変わりました。
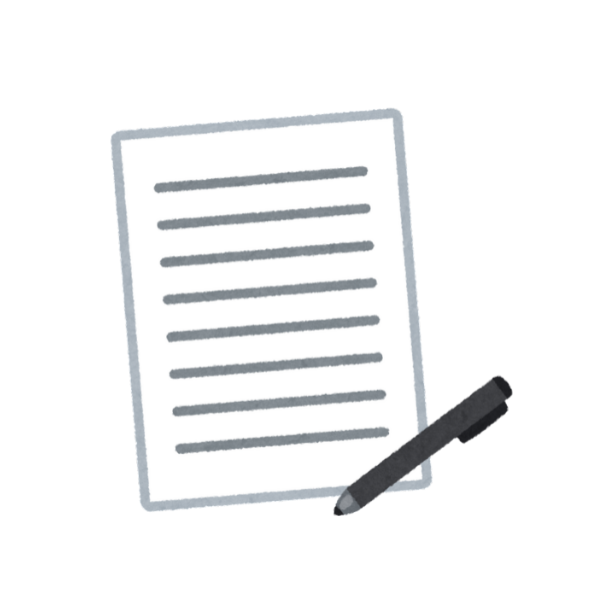
書類B:医師意見書
次に必須となるのが「医師意見書」。
これは本人がかかっている主治医に依頼して書いてもらう書類で、
要介護認定の大きな判断材料になります。
家族としては、病院へ行って「この用紙に記入をお願いします」と頼むだけ。
ですが、ここでも小さな壁が。
「次回の診察日まで待ってね」「医師が記入するまで1〜2週間かかる場合もあるよ」と言われ、
申請スケジュールが一気に先延ばしになってしまったのです。
役所の案内では「医師意見書が揃わないと判定が進まない」としっかり書いてある…。
つまり、病院のペース次第で全体の申請もストップ。
まさに「待ちの姿勢」を強要される書類でした。
書類C:介護保険被保険者証
さらに忘れてはいけないのが「介護保険被保険者証」。
これは65歳以上の方に配布される保険証で、申請時にコピーか原本の提出を求められます。
ところが…「あれ、どこにしまったっけ?」となるのがこの証書。
祖母の場合、本人がどこにしまったのかを忘れていたので、
探し出すのに家族揃って大騒ぎしました。
気づいたこと:「書類集め」は家族のチームプレイになる
こうやって書類を準備していると、ひとつ実感したのが「家族みんなで動いた方が早い」
ということです。
申請用紙を記入する人、必要書類を探す人、病院へ依頼に行く人…。
ひとりで全部担おうとすると心が折れてしまうので、自然と役割分担が必要になってきます。
私たちの場合も「私が申請書を書くから、弟は祖母のかかりつけ病院に依頼してきて!」
とお願いして、なんとか効率を上げました。
家族で協力できないとこの時点で相当な負担になるんだろうな…とゾッとしました。

提出後すぐに待ち受ける「訪問調査」
書類を提出すると、今度は「要介護認定調査員がご自宅に伺います」というお知らせが届きます。
これがいわゆる「訪問調査」。
本人が日常生活をどう送っているか、実際に確認するための大事なステップです。
祖母の場合も調査員さんが家に来られて、食事やトイレ、入浴、歩行、服の着替えなど、
細かい質問攻めにあいました。
もちろん祖母への質問がメインなのですが、実際は家族にも「普段どうサポートしていますか?」
「どの程度目を離せますか?」と聞かれます。
このとき、調査員さんが手にしていた調査票を見てびっくり。
A4用紙が十数ページもあり、しかも質問数にまたびっくり。
「あ、これも“書類地獄”の一部だったんだ…」と思いました。
調査での苦労ポイント
訪問調査の難しさは、「本人が“できる”と答えがち」というところです。
祖母も見栄やプライドがあるのか、「これくらいできるわよ!」と答えてしまう。
でも実際には、入浴はほとんど介助が必要ですし、
料理も包丁は危なくてできなくなっている状態でした。
その場で「いやいや、実際は無理なんです」と家族が補足しないと、
実際よりも軽い介護度になってしまう可能性があります。
書類にも「できる/できない」を細かく◯×する欄があり、
ここにリアルな生活状況を伝えるのが本当に大事なんだなと感じました。
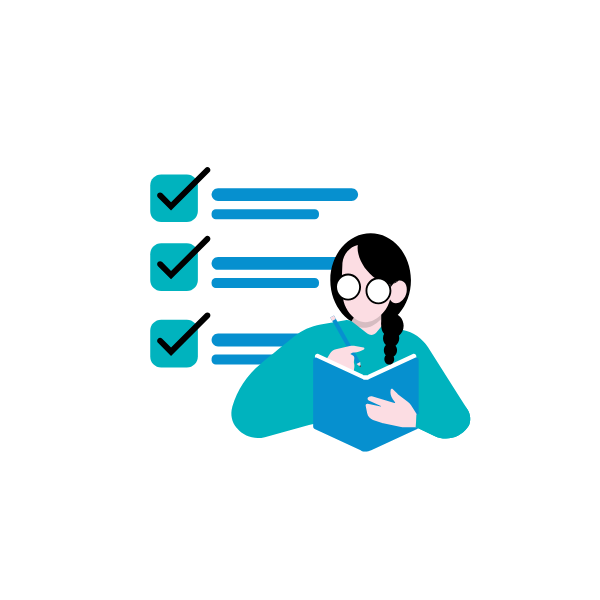
追加で降ってくる「確認書類」
訪問調査が終わって、ホッとひと息…。
と思ったら、また役所から封筒が届きました。
開けてみると「収入状況確認のための書類」「保険証明関係の追加提出」などの用紙です。
そう、また新しい紙たちが机に並ぶことに。
介護認定に直接関係するのは「要介護度の判定」ですが、
それと並行して「介護サービスを利用するときの負担割合」を計算するために、
本人や世帯の収入・年金情報などもチェックされます。
そのため、年金振込通知書の写しや、住民税の非課税証明書などを求められることもあるのです。
気づけば「ファイル1冊分」に…
最初に届いた申請関連書類、病院から返ってきた医師意見書、訪問調査で使われた控えの用紙、
さらに収入関係の追加書類…。
気づけば、クリアファイル1冊がパンパンになっていました。
私は「せっかくだから時系列でまとめよう」と思い、
100円ショップでA4対応のポケットファイルを買って整理し始めました。
結果的にこれは大正解。
後から役所の人に「このコピーをもう一度」と言われたときも、
ファイルを見返せばすぐに取り出せて便利でした。
待ち時間は「書類とのにらめっこ」
訪問調査が終わると、次は審査会での判定を待つことになります。
だいたい1か月くらいかかるのですが、その間に「あの追加資料を提出してください」
と電話がかかってくることもしばしば。
「え、まだ出すものあるの?」とため息をつきつつ、
年金関係の封筒や保険証をまたひっくり返す日々でした。
書類の影にある心理的な負担
ここで正直に書くと、書類の多さは単純に「面倒」というだけでなく、
気持ち的にもずしんと重くのしかかってきました。
祖母が介護を必要とする現実を、紙の上で何度も突きつけられるからです。
申請用紙に「できないこと」を並べる、調査票で「歩行困難」「入浴は介助」
とチェックされる…。
すべて事実なのですが、改めて活字にされるとやっぱりショックを受けました。
この“書類地獄”には、物理的な大変さだけでなく、
こうした心理的負担も含まれているんだと痛感しました。
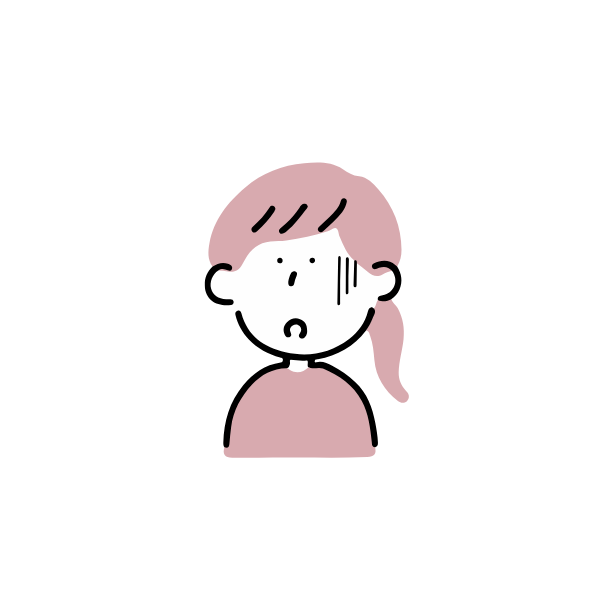
役所職員さんの存在が救いに
そんなとき、電話で丁寧に説明してくれた役所の担当者さんが本当にありがたい存在でした。
「この用紙は提出済みなので大丈夫ですよ」「これとこのコピーだけが必要です」
と整理して伝えてくれるだけで、不安がかなり和らぎます。
「全部そろうまで受け付けられません!」みたいな投げやりな対応をされたら、
きっと心が折れていたと思います。
だから、これから申請する方には「分からないことは遠慮なく聞く」のを
強くおすすめしたいです。
ついに届いた「認定結果通知」
申請からおよそ1か月。
ポストに役所からの封筒が届きました。開けてみると、中には「介護認定結果通知書」と
「介護保険負担割合証」が同封されていました。
正直なところ予想より少し軽めでした。
祖母の日常を考えるともう少し重いかなと思っていたのですが、
やはり訪問調査で「本人が思ったより元気ですよ」と答えてしまった部分が
影響したのかもしれません。
それでも、とにかく認定が出たことでホッと一安心。
これで介護サービスを利用できるスタートラインに立てたわけです。

またまた出てきた新しい用紙たち
しかし封筒の中をよく見ると、またしても新しい紙の束。
「介護サービス計画作成依頼(ケアプラン作成依頼書)」や「居宅介護支援事業所の選択届出書」
などが入っていました。
つまり、認定が出たら次はサービスを使うための手続きが待っていたのです。
書類地獄に、もはやゴールなどないのか…と半分ため息をつきつつ、
「でもここからが本番なんだ」と自分を納得させました。
ケアマネさん登場
ここで心強い味方となるのが「ケアマネジャー(ケアマネ)」さんです。
認定通知が出ると、介護サービスをどのように利用するかを一緒に考えてくれるケアマネさんと
契約を結ぶ流れになります。
ケアマネさんは介護のプロだけあって、書類関係も慣れています。
「この用紙はこちらで準備しますね」「ここに印鑑を押すだけで大丈夫ですよ」と
スムーズに案内してくれました。
家庭に寄り添ってくれる存在なので、ここで初めて「書類に追われる日々」から
少し解放された気持ちになりました。
「印鑑」「署名」のラッシュ
ただし、ケアプラン作成やサービス契約でも必要になるのが「署名」と「押印」。
契約書関係には必ずといっていいほど出てきます。
祖母は手の力が弱くて字が上手く書けないので、家族が代筆し、
横に「代筆者○○(続柄)」と記入しました。
気づけば、数日間で十数枚もの書類に名前と印鑑を押していました。

最後の難関:「負担割合証」と費用の説明
認定結果と一緒に届いた「負担割合証」も重要な書類です。
これは介護サービスを利用したときに自己負担が1割なのか2割なのかを明示するもの。
祖母の場合は1割負担でしたが、もし世帯収入が多いと2割負担になるケースもあります。
つまり書類1枚で、これからの介護費用が大きく変わる可能性があるのです。
ケアマネさんから「この証書はとても大事なので絶対になくさないでくださいね」
と念を押されました。
さらにサービスを使い始める段階で「契約書」「重要事項説明書」といった
冊子のような書類も登場。
文字通り、最後まで紙・紙・紙…。
ここでやっと「書類地獄」という言葉がぴったりだと確信しました。
書類地獄を経験して分かったこと
こうして要介護認定からサービス利用開始までをひと通り終えて、
私が感じたことは大きく3つあります。
1つめは、「準備と整理が命」ということ。
途中からはファイルを分けたりコピーをとったりして管理しましたが、
最初から“介護申請専用ファイル”を作っておけばもっとラクでした。
2つめは、「一人で抱え込まないこと」。
家族で役割分担したり、ケアマネさん、役所、病院と遠慮せず相談するのが大事です。
自分だけで頑張ろうとすると、本当にパンクします。
そして3つめは、「心の準備がいる」ということ。
書類には「できないこと」を淡々と記録する欄が多いので、
家族としては精神的にしんどい部分があります。
でもそれは、適切な支援につなげるためのプロセスなんだ、と割り切ることが必要でした。
「書類地獄」を笑い話に変える
最初はうんざりした書類の山も、今振り返ると
「あれがあったから祖母の介護がきちんとスタートできたんだ」と思えるようになりました。
確かに手間は大きいですが、それは安心できる介護制度が整っている証拠でもあるんですよね。
今だからこそ「まるで入試願書みたいだった」とか「家が紙の山に埋もれた」
なんて笑って言えます。
もしこれから申請する方がいたら、「大変だけど必ず終わりは来るから大丈夫!」
と伝えたいです。

最後に
要介護認定の申請は、まさに“書類地獄”。
申請の時点から、訪問調査、結果通知、サービス契約まで、終始紙とペンに追いかけられます。
でも、その地獄を抜けた先にあるのは、介護サービスを安心して使える暮らしでした。
もし今この記事を読んでくださっている方が「これから申請しよう」と思っているなら、
ぜひ最初からファイルを用意して、そして「分からないことは聞く」「一人で抱え込まない」
を合言葉に進めてもらえたらと思います。
書類との戦いは確かに大変。
でもいつか「あの頃は大変だったね」と家族で笑い話にできる日が来ますよ。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR] 探しているものがきっと見つかります
マイナビあなたの介護
参考
- 「要介護認定とは?認定基準や区分、申請、通知の流れ」LIFULL介護
- 「介護保険の認定調査は何をする?手続きの流れや後悔しない準備」NCJホームケア
- 「要介護認定の認定審査期間について」厚生労働省
- 「認定申請:要介護認定からサービスを利用するまでの手続き」介護支援センター

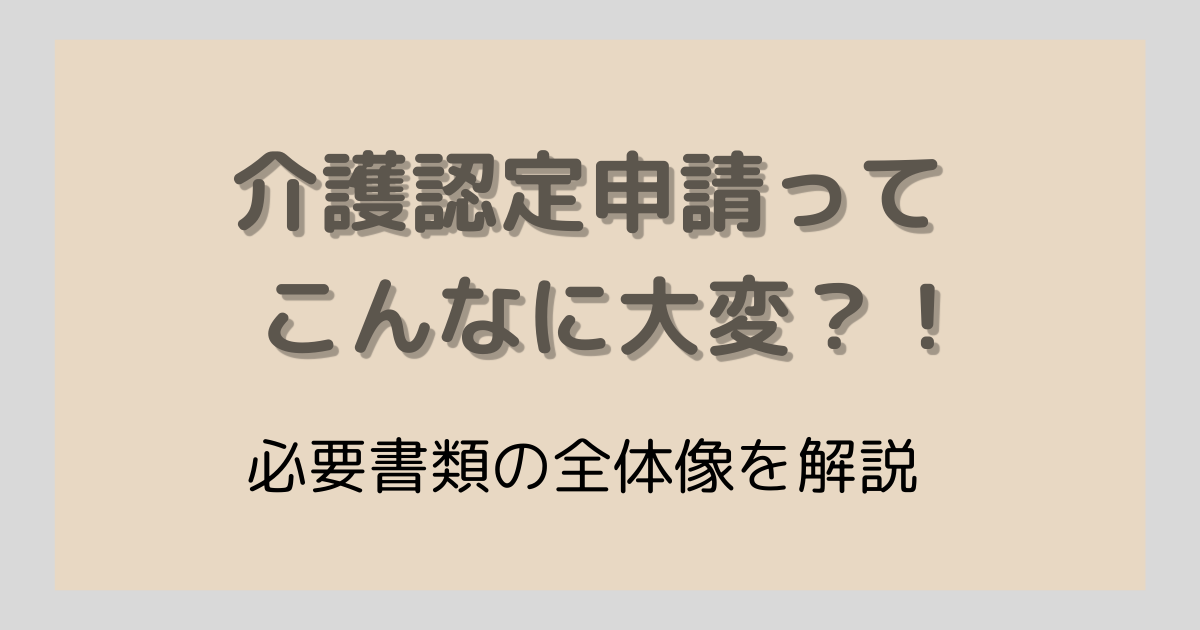


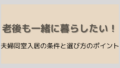
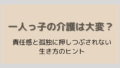

コメント