こんにちは。
日本の介護の現場は、深刻な人手不足に直面しています。
そんな中で増えているのが「外国人介護士」です。
現状どうなっているの?未来はどう変わるの?――
「介護」って、誰にとっても無縁じゃないテーマですよね。
自分の親や祖父母のこと、あるいは将来自分がどうなるか。
少子高齢化が進む日本では、本当に切実な問題になってきています。
日本の高齢化は、世界的にもトップレベル。
2025年には、いわゆる「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者になります。
これにともなって、介護の需要もどんどん増えていますが…
それに追いつくように介護士さんが増えているわけではありません。
ニュースで耳にする「人手不足」という言葉、その中で特に深刻なのが介護の現場。
高齢者は毎年増え続けているのに、働き手は足りなくなる一方……。
これはもう、数字を見ても一目でわかるくらい。
つまり「人をどう確保するか」が大きな課題なんですよね。
厚生労働省の試算によれば、2025年には約32万人の介護人材が不足すると言われています。
その穴を埋める存在として、外国人の介護士が注目されているんです。
この記事では、 外国人介護士のメリットや課題、
そして私たちにできることを考えてみたいと思います。
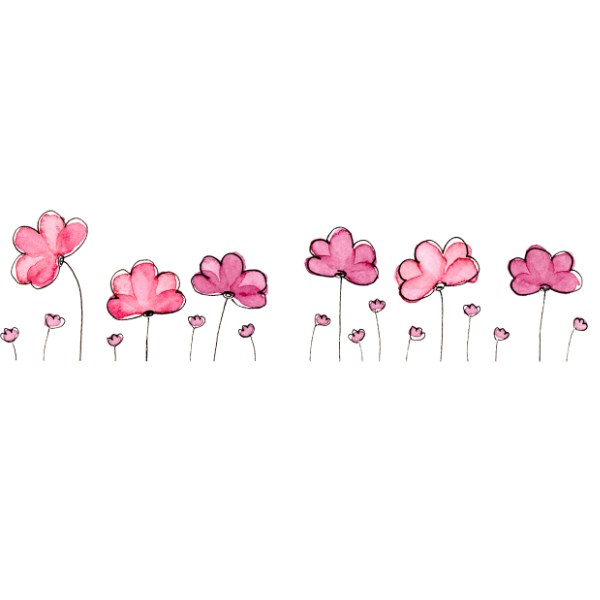
どうして外国人介護士に注目が集まっているの?
介護の仕事をする人が足りない。
そこで注目されているのが外国人です。
フィリピン、ベトナム、インドネシア、ミャンマーなど、
アジアを中心とした国々から多くの方が日本にやってきて、
実際に介護施設や在宅介護の現場で働き始めています。
「技能実習生」として来日するケースや、
「EPA(経済連携協定)」によって受け入れられるルート、
「特定技能」という在留資格を使って働くケースなど、
いろんな仕組みがあるんです。
ちょっと制度の名前を聞くと難しそうですが、
「外国から来てもらう仕組みをいろいろ作っている」ということです。
厚生労働省が発表しているデータでも、外国人介護士は年々増加。
2020年代に入って、介護分野の外国人労働者は数万人規模になっています。
そしてこれからもっと増えると言われています。
現場のリアルな声
では現場で本当に外国人介護士がどう働いているのか?
実際に施設の方や利用者さんたちの声を聞くと、意外とポジティブな意見が多いんです。
・にこやかで優しい雰囲気を持っていて、利用者さんに安心感を与えている。
・歌や料理など、母国の文化を取り入れて交流のきっかけになっている。
・「ありがとう」という言葉を一生懸命覚えて、真っすぐに伝えてくれる姿勢に心を打たれる。
介護は体力的にも精神的にも大変なお仕事だけど、外国から来て頑張っている姿を見ると、
日本人スタッフも刺激を受けることが多いそうです。
チームとしていい雰囲気が生まれる例も少なくないみたいですよ。
一方で、課題もある
もちろん、良い面ばかりではありません。やっぱり課題もあるのが現実です。
・言葉の壁:専門用語や方言を理解するのが難しいことがある。
・文化の違い:介護の仕方や生活習慣にギャップを感じる場面がある。
・資格のハードル:国家試験に合格しないと「介護福祉士」になれず、長く働くのが難しい。
特に「失敗が許されない医療に近い場面」では、正確なコミュニケーションが求められるため、
どうしてもハードルが高くなるんですよね。
本人にとっても、日本語の試験勉強や文化の違いに悩んで
途中で帰国してしまうケースもあるそうです。

「頼らざるを得ない日本」と「頑張る外国人」
日本の高齢者人口は2040年くらいにピークを迎えると言われています。
つまり、これからさらに介護の需要は高まり、ますます人手不足が深刻化する見通しです。
そうなると、日本人だけでまかなうのはもう現実的ではありません。
政府レベルでも「外国人なしでは介護の現場は回らない」という意識が広がっています。
だけど、その一方で「外国人に頼りきっていいのか?」という疑問もある。
ここにジレンマがあるんです。
外国人の方々も、自分の人生を背負って日本に来ています。
自分の国に仕送りをするため、技能を身につけるため、夢を持って来日する。
でもその夢と現実のギャップに悩む声も多いのが事実なんです。
外国人介護士が増えた未来のシナリオ
ここからは少し未来を想像してみましょう。
「もしもっと外国人介護士が増えたら、日本の介護の姿はどう変わるんだろう?」――
そんな視点で考えてみたいと思います。
シナリオ①:多文化共生の介護現場
例えば介護施設の中で、日本語とベトナム語とフィリピン語が飛び交うような光景。
最初は「ややこしい」と思うかもしれませんが、
利用者さんからすると「なんだか賑やかで楽しい」と感じる場面もありそうですよね。
また、季節のイベントでは「七夕」だけでなく
「テト(ベトナムのお正月)」や「クリスマス」をみんなで祝う。
そんなふうに文化が交じり合って、ただ「介護する/される」という関係を超えて、
人と人との交流や楽しみが広がる可能性もあります。
シナリオ②:人手不足は解消されるが…
一方で「人手不足が解消される=すべてがハッピー」ではありません。
むしろ新しい課題が出てくることも考えられます。
・外国人への依存度が高まりすぎて、日本人スタッフの育成が後回しになる。
・待遇や条件に格差が生まれ、「働きやすいのはどっち?」という不満が出る。
・地域社会の理解が追いつかず、「外国人介護士に抵抗感を持つ」人も出てくる。
つまり「人数が足りればそれで解決!」という単純な話じゃないんです。
きちんと制度や地域のサポートが整っていないと、
外国人も日本人もどちらも息苦しくなってしまいます。
シナリオ③:テクノロジーとの融合
最近では介護ロボットやAIの活用も注目されていますよね。
移乗をサポートするロボットや、見守りセンサーなどはすでに現場に導入されています。
ここで面白いのは、「外国人介護士 × テクノロジー」の組み合わせです。
日本語がまだ完璧じゃなくても、
翻訳アプリや音声サポートロボットが補ってくれるようになったら、
もっと安心して介護ができる。
逆に「人にしかできない温かいケア」は外国人介護士が担い、
力仕事や記録業務は機械が担う――そんな役割分担の未来像も見えてきます。
外国人介護士がいることで変わる“日本人の意識”
ここまで未来の姿を考えてきましたが、もうひとつ大事なのが「日本人の意識の変化」です。
外国人の方々と一緒に働くことで、
「介護ってそんなに暗い仕事じゃない」
「いろんな人と協力してできる仕事なんだ」
というポジティブな雰囲気が生まれるかもしれません。
これは実際の現場の声にもすでにあります。
また、介護を「低賃金で大変な仕事」というイメージから、
「グローバルに活躍できる専門職」というイメージにシフトしていく可能性もあるんです。
例えば外国人ヘルパーと英語を使って仕事をする日本人スタッフが増えれば、
「介護の仕事なのに英語スキルも活かせる」
という新しいキャリアの形が生まれるかもしれません。
[PR]地域社会とのつながり
外国人介護士がもっと増えると、地域社会全体にも変化が出てきます。
・地域のイベントに外国人スタッフが参加して、文化交流の場が広がる。
・スーパーや公園などで自然に外国人と出会う機会が増える。
・「介護」というきっかけを通じて、地域全体が多文化共生を学ぶ。
介護って、ものすごく“地域密着型”の仕事ですから、
外国人介護士が地域とつながっていくことで、
そこに暮らす高齢者だけでなく、
若い世代や子どもたちにとっても貴重な経験になると思います。
課題を乗り越えるための工夫
もちろん、理想の未来を描くためには課題の克服が欠かせません。
そのために、すでに取り組まれている工夫や、これから必要とされるポイントを挙げてみます。
・語学教育の充実:
日本語学校と介護施設が連携して、実践的に学べる場を増やす。
・メンター制度:
日本人スタッフが「日本の常識」を一方的に押し付けるのではなく、
一緒に悩みを共有しながら成長できる関係づくり。
・地域ぐるみのサポート:
町内会やボランティアと連携し、外国人を孤立させない環境を整える。
・資格取得支援:
試験対策講座や母国語での学習サポートなどを強化して、長期的に働ける人材を増やす。
こうした工夫が積み重なれば、「外国人に頼らざるを得ない介護」から、
「外国人と一緒に未来を作る介護」に変えていけるんじゃないかなと思います。
外国人介護士に頼る日本の未来、私たちができること
ここまで「現状」と「未来のシナリオ」についてお話ししてきました。
最後にお伝えしたいのは、私たち一人ひとりにできること。
これは決して特別なことではありません。
小さな意識の変化や行動によって、
日本と外国人介護士の未来は少しずつ良い方向に進んでいけるんです。
「ありがとう」を伝える
シンプルだけれど、とても大きな力を持つのが「ありがとう」という言葉です。
外国から来ている介護士さん達は、日本語を一生懸命勉強しています。
そんな中で「ありがとう」と笑顔で伝えるだけで、安心したり自信が持てたりするんです。
利用者さんだけではなく、同僚や地域の人からも感謝を伝えられることは、
外国人にとって大きなモチベーションになります。
介護の現場はとても疲れる仕事ですが、
その一言が「また明日も頑張って働こう」と思える原動力になるんです。

異文化へのちょっとした興味
「母国の料理ってどんな味?」
「休みの日はどんなふうに過ごしてるの?」…
そんな小さな質問で十分です。
相手に興味を持つというのは、「あなたはここで大事な存在」と伝えるサインでもあるんです。
例えばある施設では、
外国人スタッフがそれぞれの国のおやつを利用者さんと一緒に作るイベントを開いたそうです。
利用者さんにとっては「初めての味」との出会い、
スタッフにとっては「自分らしさを発揮できた経験」。
こんな交流が積み重なると、ただの職場を超えて「居場所」になっていくんですよね。

偏見や先入観を手放す
外国人介護士と聞くと、
中にはまだ「ちゃんと仕事できるの?」とか「日本語大丈夫なの?」といった声もあります。
でも実際に一緒に働いてみると、勤勉さや思いやりの深さに驚かされることも多いようです。
もちろん言葉の壁や文化の違いはあります。
でも、それを補う工夫やサポート体制を整えれば十分に力を発揮できる。
大事なのは「外国人だから」というフィルターを外して、
一人の仲間、一人の人として向き合うことなんです。
制度や環境づくりを応援する
個人としてできることは限られているけれど、
日常の中で「制度や環境づくりを応援する」こともできます。
例えば選挙で候補者が、
「介護人材育成」や「外国人労働者の支援」にどう取り組むのかを知ること。
SNSや口コミで「外国人介護士が活躍してて素敵だよ」というエピソードを広げること。
こうした小さな関心が、社会の流れを変えていく第一歩になると思います。
「一緒に支え合う」未来を目指して
日本の未来を考えるとき、介護は避けて通れない大きなテーマ。
そこに外国人介護士が加わることは、いわば「頼らざるを得ない状況」から始まりました。
でも、それを「仕方ない選択」として受け入れるか、
「新しいチャンス」として前向きに取り入れるかで、未来の景色は大きく変わります。
一緒に働き、一緒に学び、お互いの文化を認め合う。
そんな積み重ねがあれば、外国人介護士は単なる労働力ではなく、
日本社会を一緒に作る仲間になっていけます。
そして、それは日本人にとっても「介護の仕事の価値を再発見する」きっかけになるはずです。

最後に
この記事を読んでくれたみなさんが、明日から外国人介護士に出会ったとき、
ちょっと笑顔をプラスして「ありがとう」と声をかけるようになったら――
それだけでも未来は少し変わると思います。
介護は「人と人が支え合う」仕事です。
その輪が国境を越えて広がっていくのは、本当に素敵なことじゃないでしょうか。
これからの日本は、外国人と一緒に支え合って歩んでいく。
そんな未来をイメージしながら、今回の記事を締めくくりたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 「外国人介護人材の受け入れの現状と今後の方向性について」厚生労働省
- 「介護業界の人材不足はなぜ深刻?原因と今後の展望」Guidable Jobs
- 「特定技能[介護]の現状は?人手不足の深刻さや今後の展望」スキルドワーカー
- 「介護人材の受け入れ・現状や課題について」介護のツクイスタッフ



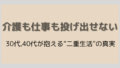


コメント