こんにちは。
日本の高齢社会を生きている私たちにとって、
親の介護はある日突然“自分ごと”としてやってくることがあります。
特に、実家の親を一人で支えている娘の姿は、周りからはなかなか見えにくく、
本人も声を上げづらい現実があります。
今回は、「実家の介護を一人で背負う娘たちの現実」をテーマに、
具体的な風景や気持ちを交えながらお話ししていきたいと思います。
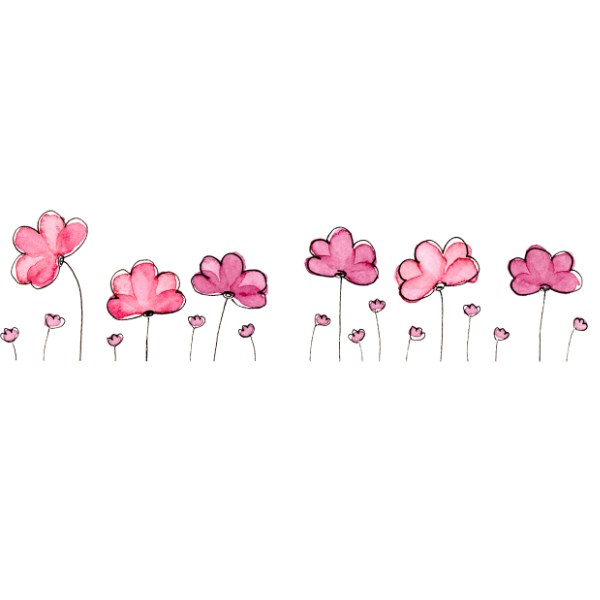
ある日突然始まる「親の介護」
介護は、準備して始まるものばかりではありません。
例えば、母親が転んで骨折をしてしまった。
父親が軽い脳梗塞で入院して、退院後はサポートが必要になった。
そんな風に、“昨日までは元気だった親”が、
一気に「介護の必要な親」に変わる現実があるのです。
「これからどうしたらいいの?」と途方に暮れながらも、
病院のベッドの横に座っているのは、多くの場合、娘です。
兄弟がいても、「とりあえず娘に任せよう」となるケースは少なくありません。
「娘だから」というプレッシャー
日本の家庭には、まだ「娘が面倒をみるもの」という空気感が残っています。
誰も口には出さなくても、親戚や近所の人の視線にそういう期待がにじんでいたりしますよね。
本人も「やっぱり私がやらなきゃ」という気持ちが強くなり、
自然と生活すべてを介護中心に切り替えていかざるを得なくなります。
そのとき心の奥に芽生えるのは、愛情だけではありません。
親に恩返しをしたい気持ちもあるけれど、
「どうして私だけが?」という小さな不満も確かに存在します。
介護と仕事、自分の生活
例えば、週5日フルタイムで働いていた人が、親の介助のために時短勤務に変えたり、
場合によっては退職せざるを得なくなったりします。
経済的な不安はもちろん大きいですが、それ以上に
「自分の人生が親の介護だけになってしまうかも」という不安が重たくのしかかります。
仕事を辞めれば収入は減りますし、再就職の道も年齢が上がるほど難しくなります。
それを理解しながらも、「でも親を一人にはしておけない」と踏み出してしまう娘たち。
頭の中では「将来どうなるんだろう」と警鐘が鳴り続けているのに、
実際には目の前の介護に追われる毎日で精一杯です。
一人で向き合う孤独な介護
介護を一人で担っていると、とにかく孤独です。
他の兄弟や家族から「ありがとう」と言われても、どこか“丸投げされた感覚”は消えません。
また、介護の仕方を相談できる人が身近にいないと、不安や悩みを心にため込んでしまいます。
介護は「体力」と「知識」と「気持ちの余裕」がすべて必要になる仕事です。
ところが一人で抱え込むと、この3つがどんどんすり減っていきます。
体力は疲れで削られ、調べてもわからない制度にイライラし、
気持ちの余裕は日に日に薄れていく…。
そんな日常を、全国の多くの娘たちが過ごしているのです。
揺れる気持ち
親の介護を続ける娘たちが一番苦しいのは、
実は身体の疲れよりも「心の矛盾」かもしれません。
「親のことは好きだし、できる限り支えたい」
しかし、「こんなに自分ばかり負担しているのは不公平だ」。
この気持ちが交互にあらわれ、まるで波にさらわれるように心を揺さぶっていきます。
しかも、この気持ちは簡単に人に打ち明けられません。
少し愚痴をこぼせば、「自分の親でしょ?」「親不孝だ」と言われるんじゃないかと怖い。
だからこそ、娘たちは笑顔で「大丈夫だよ」と取り繕ってしまう。
傍からは明るく見えても、実際には心の奥で涙をこらえる毎日なのです。
兄弟との関係性
本来であれば、兄弟で力を分担して支えるのが理想です。
でも実際には、娘にすべてがのしかかるケースが多いですよね。
たとえば「自分は仕事が忙しいから」と兄は遠回しに責任を避けたり、
「同居してるのはお姉ちゃんだから」と弟が距離を置いたりする。
結果的に、誰も悪気はなくても「一人に集約」されてしまうのです。
さらにやっかいなのが、「介護の仕方」について外から意見だけしてくるパターン。
「もっとデイサービスを入れたら?」「施設を探せばいいじゃない」―
簡単に言うけど、その手続きや説明をすべて担うのは結局世話をしている人。
精一杯やっている側からすれば、助言ではなく“口だけ出されている”と感じてしまい、
ありがたさより苛立ちが募ることもあるのです。
消える「自分の時間」
介護をしている人の多くが口にするのが、「一日が全部世話で埋まっていく」という感覚です。
朝起きて食事をつくり、服薬確認、病院の付き添い、トイレや入浴のお手伝い、夜の見守り…。
気づけば自分がゆっくり座っている時間は数分程度。
静かにお茶を飲む余裕もないまま、一日が終わってしまいます。
友達からランチに誘われても断ることが続くし、趣味や楽しみの時間はどんどん後回しに。
大げさでなく「自分の人生を休止しているような感覚」になってしまいます。
そんな状態が長く続くと、笑顔が減り、気持ちが塞ぎ込み、
最悪の場合“うつ”の入り口に立ってしまうことも少なくありません。
周囲からの評価
また、介護を一人で担う娘たちは、周囲から正しく評価されにくいという現実もあります。
「親孝行してて偉いね」と褒められる一方で、
「娘なんだから当然」と無意識に軽くみられてしまうこともあるのです。
しかし実際には、介護は仕事以上の責任と労力を伴います。
24時間気を抜けず、相手は自分で選べる上司や部下ではなく、自分の親。
感情のぶつかりやすさも全然違います。
「外の人からは理解してもらえない」「誰も私の疲れに気づいてくれない」―
そんな思いが娘たちをさらに孤独にしていきます。
“介護うつ”という落とし穴
厚生労働省の調査や様々な研究でも、
介護を担っている人はうつ状態に陥りやすいことが報告されています。
睡眠不足、ストレス、そして先の見えない不安。
これらが積み重なることで「自分なんか消えてしまいたい」
という思いにまで至ってしまう場合もあるのです。
もちろん、誰も最初からそんな思いを抱くわけではありません。
ただ、支援を受けられずに孤立してしまうと、愛する親の世話で疲れ果て、
自分自身を失っていく危険がある。
それが一番の問題なのです。
つい頑張りすぎてしまう
実家の介護を担う娘たちは、知らず知らずのうちに自分を追い込んでしまう傾向があります。
その背景には、「家族だから自分がやらなければ」「他の人を頼るのは甘え」
という思い込みがあります。
でも実際には、介護は一人でできるものではありません。
介護保険や地域包括支援センター、ケアマネジャーという存在を知るだけで、大きく変わります。
介護サービスは「必要な支え」です。
上手に利用することで「介護=24時間張り付き」ではなくなります。
ー種類豊富なメニューがあるので、食事作りぐらいは手を抜いて下さいねー
[PR]最後に
もし今、あなたが同じような立場にあるなら、心に留めておいてほしいことがあります。
あなたの人生も、あなたの幸せも大切です。
人に頼ることは弱さではなく、介護を続けるための知恵です。
人は、頼られた時、意外と力を貸してくれるものですよ。
どうか、遠慮せずに周りにどんどん頼って下さいね。
この記事が、頑張り屋のあなたの肩の力を抜くきっかけになれたら幸いです。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
ーぐっすり眠って、また明日、元気に一日をスタートできますようにー
[PR]参考
- 「親の介護を長女や一人っ子がするときの基本!直面する3つの不安と解消法 」 Caresul
- 「家族介護者の負担・ストレスに留意を 」都健康長寿医療センター
- 「家族をケアする:毎日の生活という文脈での家族介護を考える」 – 東京都健康長寿医療センター

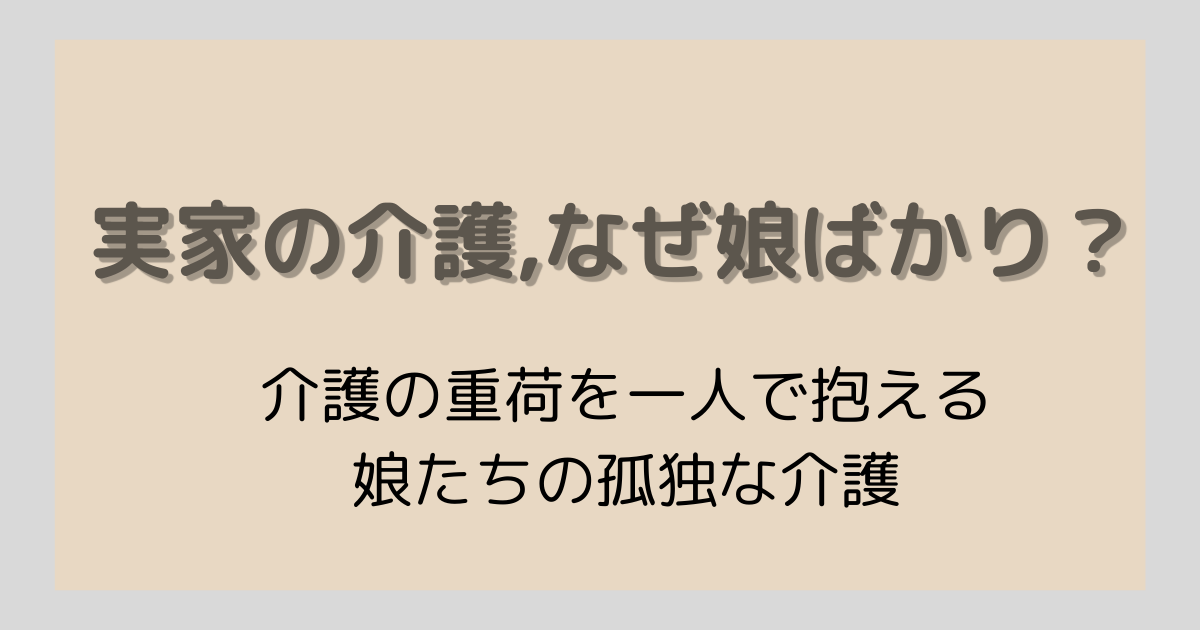



コメント