こんにちは。
親や配偶者など、大切な家族の介護が必要になったとき、
仕事と両立するのがとても大変ですよね。
つい無理をしてしまったり、会社を休みがちになったり…。
その結果「やっぱり仕事を辞めて介護に専念した方がいいのでは…」と悩む方も多いと思います。
実際に、日本では毎年何万人もの方が「介護離職」をしています。
けれど、離職した後に「こんなに生活が大変になるなんて…」
「もっと制度を知っておけばよかった」と後悔する声も少なくありません。
そこで今回は「介護離職した場合に使える制度や支援」について、
できるだけ分かりやすくまとめてみたいと思います。
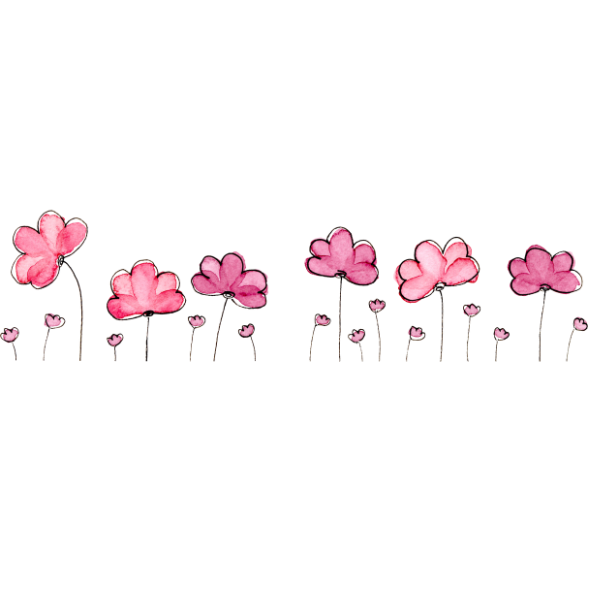
介護離職をする前に知っておきたいこと
まず最初にお伝えしたいのは、
「できれば辞める前に使える制度を確認してほしい」という点です。
介護のために仕事を辞めることが悪いわけでは全くありません。
でも、仕事を続けながら支えていける制度があるのに、
それを知らずに辞めてしまうのはすごくもったいないんです。
例えば「介護休業制度」や「短時間勤務」、介護のための「フレックスタイム制度」など、
会社によって活用できる仕組みはさまざま。
職場の理解を得られれば、「離職」という選択肢を少し先延ばしにできるかもしれません。
それでも、どうしても介護離職が避けられなかった場合。
そんなときに利用できる制度や支援がたくさんあります。
知らないまま経済的にも精神的にも追い込まれてしまうのは、避けたいところですよね。
ここからは「介護離職した後」に受けられる制度や支援を整理してご紹介していきます。
[PR]介護離職後に活用できる公的な制度
介護離職をすると、一番大きな心配は収入面だと思います。
安定した給与がなくなってしまうと、どうしても不安が大きいですよね。
でも、日本には失業した方の生活を支える仕組みが整っています。
まずは、代表的な制度から見ていきましょう。
雇用保険(失業給付/失業手当)
介護のために退職すると、「自己都合退職」として扱われることが多いですが、
実は介護離職は「特定理由離職者」として認めてもらえるケースがあります。
通常の自己都合退職だと、失業手当の受給までに3か月の待機期間があります。
でも「特定理由離職者」として認められれば、この待機期間が短縮される可能性があるんです。
そのため、ハローワークに申請するときには
「介護が理由での離職」であることをきちんと伝えましょう。
診断書や要介護認定の書類などが証拠になります。
また、失業手当の受給期間は基本的に1年間ですが、
介護に時間を取られてハローワークに通えない場合は、期間を延長することが可能です。
最長で4年間まで延長できるので、焦らずに利用できますよ。
健康保険の継続と国民健康保険
退職後は、会社の健康保険をそのまま一定期間継続する「任意継続被保険者制度」
を利用できる場合があります。
国民健康保険に入るか、会社の健康保険を2年間継続するかを選べるので、
保険料や保障内容を比較して考えるのがおすすめです。
介護中は自分自身も体調を崩しやすいので、医療保険を切らさないことは何より大切です。
国民年金免除制度
退職して収入が減ってしまうと、国民年金の保険料が重く感じることがありますよね。
そんなときは「国民年金保険料免除制度」を検討してみてください。
全額免除や一部免除、納付猶予など段階的に対応ができます。
将来の年金額には多少影響しますが、支払いが難しいからと未納にしてしまうより、
制度を利用する方がずっと安心です。
介護している人を支える福祉サービス
公的な社会保険の制度に加えて、「介護をしている人自身」を支える福祉サービスも存在します。
介護は終わりが見えづらく、心身ともに大きな負担がかかります。
だからこそ、国や自治体は介護者を支える制度を用意しているのです。
生活支援・生活福祉資金貸付制度
介護のために離職すると、日々の生活費に困ることもあります。
そんなときは「生活福祉資金貸付制度」という、
低金利(場合によっては無利子)の貸付制度を利用できることがあります。
社会福祉協議会が窓口となっている場合が多いので、相談してみるとよいでしょう。
返済についても柔軟に対応してくれることがありますよ。
自治体の介護者支援サービス
自治体によっては、
介護者向けの相談窓口や講座、リフレッシュのための交流会を開催しているところがあります。
同じ立場の人とつながることで気持ちが軽くなることも多いので、
「一人で抱え込まない」ということが何より大切です。
[PR]介護離職後の生活設計をどう考える?
離職した直後は、気持ちが追い込まれて「とりあえず介護に専念する!」となりやすいのですが、
その後の生活設計をどう整えるかで不安の大きさが変わります。
もちろん完璧な計画を立てる必要はありません。
ただし、ある程度の見通しを持っておくことはとても大切です。
生活費のシミュレーション
毎月どれくらいの出費があるのかを一度書き出してみましょう。
食費や光熱費、介護サービスの自己負担、医療費などは意外と見落としがちです。
公的な支援がどれくらい受けられるかも含め、
「今の貯蓄でどのくらい持ちこたえられるか」を把握しておくことで、早めに行動がとれます。
自治体の相談窓口を活用する
自治体の介護保険課や地域包括支援センターには、
介護者の相談も受け付けてくれる窓口があります。
「介護サービスをどこまで使えるのか」「費用の助成制度はあるのか」など、
知らないうちに損をしているケースも少なくありません。
特に生活が厳しい場合は「生活困窮者自立支援制度」を相談できることもあります。
ケアマネジャーに相談する
介護保険サービスを利用している場合は、担当のケアマネジャーに聞いてみるのもおすすめです。
ケアマネさんは介護サービスの調整役ですが、
家族の状況も含めてアドバイスしてくれることがあります。
「介護で疲れ切ってしまっている」「仕事に戻れるか不安」といった気持ちも、
率直に話してみるといいですよ。
介護を続けながら再就職を目指すには?
「一度会社を辞めたら、もう働けないかもしれない…」と不安に思う方は多いです。
でも実は、介護中の方を対象にした就職支援が少しずつ広がっているのをご存じでしょうか?
特にハローワークや自治体が提供している支援は心強い味方になります。
ハローワークの「介護離職者支援コーナー」
一部のハローワークには「介護離職者支援コーナー」が設置されており、
専門の相談員が再就職をサポートしてくれます。
例えば「介護と両立できる働き方」「週に数日だけ勤務したい」「在宅ワークを探したい」
といった要望を伝えると、その条件に合った求人を紹介してくれることがあります。
「再就職しないと…」と焦る気持ちはとても自然ですが、
無理にフルタイムで復帰しなくても大丈夫です。
自分に合ったステップを一緒に考えてもらえますよ。
職業訓練(求職者支援制度)
介護でいったん仕事を辞めても、「また別の職種に挑戦したい」と考える方も多いと思います。
そんなときに活用できるのが、就職に役立つスキルを学べる「職業訓練」です。
パソコンスキルや介護以外の資格取得を目指す講座など、幅広いプログラムがあり、
受講料が無料だったり、受講中に生活支援金を受けられることもあります。
無理のない範囲で「次の自分に必要な勉強をする時間」として利用するのも、
とても前向きな選択になります。
介護経験を活かせる仕事
長く介護をしてきた経験そのものが、実は仕事につながることもあります。
ホームヘルパーや介護職、相談員といった仕事はもちろんですが、
「同じ経験をした人だからこそできる仕事」が社会には増えつつあります。
資格が必要なケースもありますが、
ハローワークや福祉人材センターで研修を紹介してくれる場合もあるので、
情報を集めてみると意外な道が見えるかもしれません。
[PR]心のケアも含めた支援の大切さ
介護離職した方に多い悩みのひとつが「孤独感」です。
家族の介護は尊いことですが、自分の世界が介護だけになってしまうと、
心が疲れてしまうことがあります。
そんなときに助けてくれるのが、カウンセリングや介護者の交流会です。
介護者カフェ・交流の場
多くの自治体やNPOでは「介護者カフェ」や「介護家族の交流会」を開いています。
お茶を飲みながら、同じ立場の人と話せる場です。
「自分だけじゃなかったんだ」と思えることが、心の負担を大きく減らしてくれます。
介護生活はどうしても「頑張りすぎ」になりやすいので、
こういう場に出かけることはおすすめです。
メンタルヘルスの相談窓口
各自治体には「心の健康相談」や「ストレス相談ダイヤル」があります。
深刻に落ち込んでからではなく、ちょっと苦しいな…と思ったときに気軽に相談してみましょう。
介護をしながら自分の心を守るのはとても大切なこと。
弱音を吐ける相手や場所を持ってくださいね。
[PR]そもそも介護離職を防ぐ工夫とは?
介護離職は、「介護」と「仕事」の両立が難しいときに避けられず選ばれるケースが多いです。
ですが、ちょっとした工夫や制度の活用によって「全部自分で背負い込まなくてもよかった」
と感じられる場面もたくさんあります。
介護サービスを思い切って使う
介護保険サービスにはさまざまな種類があります。
デイサービス、ショートステイ、訪問介護など、
うまく組み合わせることで介護者の負担を軽くすることができます。
特に「ショートステイ」を利用すると、数日間は介護を専門の施設に任せられるので、
自分自身の休養や仕事への集中の時間を安心して持つことが可能です。
「家族だから自分で全部やらなきゃ」と思わず、
プロの手を借りることを前向きに考えてくださいね。
職場としっかり対話する
つい介護の事情を隠してしまう人もいますが、
実際には職場に事情を伝えることでサポートしてもらえるケースもあります。
「介護休暇」や「短時間勤務」のほか、
フレックスタイムやテレワーク制度が整っている会社もあります。
勇気を出して相談することで「辞めるしかない」と追い込まれなくても良くなるかもしれません。
家族や親族と情報を共有する
介護を一人で抱えてしまうと、いずれ心身ともに限界が来てしまいます。
兄弟姉妹や親族と「今日は誰が病院に付き添うのか」「費用はどう分担するのか」
といった情報を共有し、お互いの負担を調整しましょう。
最近では「介護アプリ」を使ってスケジュールを共有する方法も広がっていますよ。
自分の健康を最優先に
介護中は「親の世話が第一」「自分のことは後回し」という意識になりがちです。
ですが、自分が倒れてしまったら、結果的に介護が続けられなくなることもあります。
栄養や睡眠を意識して取ること、時にはリフレッシュの時間をあえて作ること、
それが結果的に長く介護を続けられる力になります。
[PR]仕事と介護を両立するための制度
介護離職を防ぐうえで知っておきたいのが「仕事と介護を両立するための制度」です。
会社規模に関わらず法律で定められているものもありますので、ぜひ確認してください。
介護休業制度
家族が要介護状態になったとき、最長93日(通算)の休業を取得できる制度です。
この期間は「介護休業給付金」という形で給与の一部が雇用保険から支給されます。
介護が本格化するときに一時的に仕事を調整できる、とても心強い仕組みです。
介護休暇
年5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、1日または半日の単位で取得可能です。
突発的な通院や急な介助が必要なときにとても役立ちます。
給与が出るかどうかは会社の規定次第ですが、まずは権利として知っておくことが大事です。
短時間勤務・フレックスタイム制度
介護が長期化するなかで効果的なのが、勤務時間を柔軟に調整できる制度です。
特にフレックス勤務やテレワーク制度は、
通勤の負担を減らしながら仕事を続けることを可能にします。
会社によって対応の幅は違うので、一度人事や上司と相談してみるとよいでしょう。
介護離職しないための「心の持ち方」
制度やサービスを知ることも大事ですが、もうひとつ大きなポイントは「心の持ち方」です。
介護は一人で抱え込むものではなく、社会全体で支えるべきもの。
「頼ってもいい」「休んでもいい」という気持ちを持ち続けることが、
長期的に見て非常に大切です。
「ちゃんと介護できていないのでは」「もっとやらなきゃ」
と自分を追い詰めてしまう方はとても多いです。
大切なのは「安全」と「安心」を保ちつつ、自分自身もできるだけ笑顔で過ごせることです。
少し手を抜いてもいい、サービスに頼ってもいい。
そのゆとりが、介護を続けていける力になります。
最後に
「介護離職した場合に受けられる制度と支援」についてお伝えしてきました。
離職後にも活用できる公的制度、生活設計のポイント、再就職や心のケアの支援、
そして離職を防ぐための工夫や両立の制度…。
どれも「一人で頑張らなくてもいい」ということに共通しています。
介護離職は決して特別なことではなく、多くの人に起こりうる身近な出来事です。
介護も仕事も、そして自分自身も全部大切なもの。
だからこそ、自分自身を犠牲にしすぎず、支援や制度に手を伸ばしてみてくださいね。
あなたとご家族の生活が、少しでも穏やかに、そして安心して続けられますように。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 介護離職を防止するための4つの方法!改正育児・介護休業法の義務化について(マネーフォーワード)
- 2025年4月1日施行 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等(社会保険労務士 萩堂事務所)
- 自治体が行なっているさまざまな介護支援(介援隊プラス)




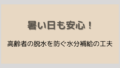


コメント