こんにちは。
今日は介護現場で働く方や、そのご家族、あるいは「将来介護の仕事をしてみたい」
と考えている方が、一度は気になるテーマについてお話しします。
それはズバリ――「なぜ介護士の給料はなかなか上がらないのか?」という問題です。
介護という仕事は、高齢社会の日本にとってなくてはならない存在ですよね。
実際、介護の現場は人手不足が常態化しています。
それでも「給料が低い」という声はずっと続いています。
これだけ社会に求められているのに、どうして待遇が改善されにくいのでしょうか?
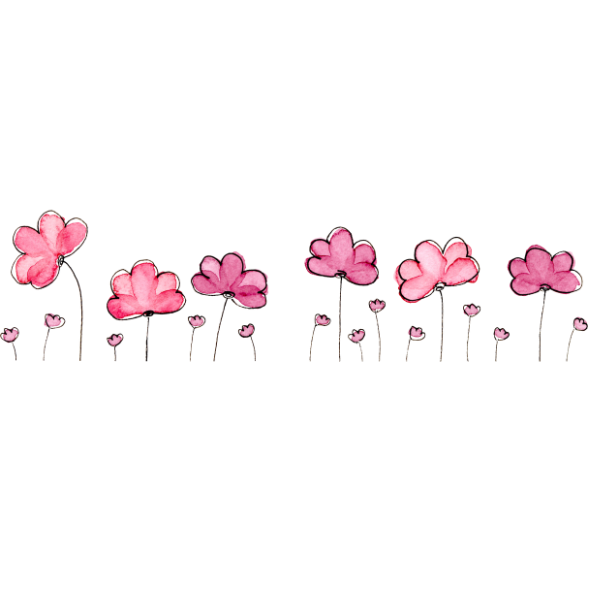
介護士のお給料が低いと言われる理由
まず、多くの人が思う「介護士=給料が安い」というイメージ。
これは実際のデータにも表れています。
たとえば厚生労働省の調査によると、介護職員の平均給与は全産業の平均よりやや低めです。
もちろん施設や地域、経験によって差はあるのですが、
全体的な傾向として“高いとは言えない”のが現状です。
でもここで疑問が出ますよね。
「介護は社会的に必要な仕事なのに、なぜ安いの?」と。
教師や看護師のように“命や生活を守る”役割があるはずなのに、給与水準が追いついていない。
この背景には、介護業界ならではの制度的な仕組みがあります。
介護は「市場原理」だけでは決まらない仕事
普通の仕事であれば、需要と供給で値段(=給料)が決まります。
人気があって人手が不足していれば、企業が人を集めるために給与を上げるのは自然な流れです。
でも介護の世界では、そう単純にはいかないんです。
なぜかと言えば、介護サービスは
「介護保険制度」という公的な仕組みの中で運営されているから。
つまり、サービス料金は自由に決められず、国が細かく定めているんです。
具体的には、利用者さんが払う自己負担分と、
国や自治体からの給付(税金と保険料)で成り立っています。
そのため「施設の経営者がもっと職員の給料を上げよう!」と思っても、
受け取れる収入が制度上制限されていて、自由度が低いんですね。
これが「需要があるのに賃金が上がらない」最大の理由なんです。
[PR]介護報酬という“天井”
介護サービスの収入は「介護報酬」で決まります。
これは国が2〜3年ごとに見直していて、
「訪問介護は何分でいくら」「特養での生活支援は1日いくら」といった具合に、
細かく料金設定されています。
つまり、介護事業所はその枠の中でしか収入を得られません。
たとえば飲食店なら「もっと美味しいサービスを提供するから価格も上げよう」とできますが、
介護ではそれができません。
料金を勝手に上乗せしたらルール違反になってしまうんです。
これが、介護士さんのお給料に直接響いてくる仕組みです。
人件費はコストの大部分
介護施設や事業所の経営を支えているのは、ほとんどが介護報酬。
そしてその収入の中でいちばん大きな割合を占めるのが人件費です。
介護の仕事は「人の手」で成り立っているので、人件費にかかるウェイトがとても高いんですね。
つまり、経営者が給料を上げたい!と思っても、介護報酬という“収入の天井”があるので、
大幅に改善するのは難しい…。
このジレンマが続いているのです。
[PR]
給料が上がらないことの影響
給料が低いままだと、介護職を目指す人が減ってしまいます。
せっかく資格を取っても、生活が大変で他の業界に移ってしまう方も多くいます。
それによって現場はさらに人手不足になり、残っているスタッフの負担が増える…
という悪循環に陥ってしまいます。
これこそが「介護士の待遇をどう改善するか」が社会全体の課題とされている理由なんですね。
決して“現場に魅力がないから”ではなく、“制度に縛られているから”なんです。
介護保険制度ってどんな仕組み?
介護のお金の流れを分かりやすく整理してみましょう。
介護サービスは「介護保険制度」で成り立っています。
利用者さんは、40歳以上の国民が払っている介護保険料と、税金、
それに実際にサービスを利用するときの自己負担(1〜3割)で制度を支えています。
つまり、介護士さんの給料の源泉は「みんなが払っている保険料と税金」。
この枠内でやりくりしなくてはいけないという制約があるんです。
介護報酬改定はなぜ渋い?
介護報酬は2〜3年ごとに国が改定しています。
「もう少し施設にお金をまわそう」と思えば報酬を上げられるはずなのに、
実際はなかなか大きくは上がりません。
その背景にはいくつか事情があります。
1.高齢化による財源圧迫
日本は世界一の高齢社会。介護サービスを利用する人は年々増えています。
もし報酬をどんどん引き上げたら、国や自治体の財政があっという間に厳しくなります。
2.保険料と税金のバランス
私たちが毎月払う介護保険料は、すでに家計にとって負担感があるものです。
これ以上引き上げると国民生活にしわ寄せがいきます。
だから簡単に「介護費用にもっと税金を回そう」とはいきにくいんですね。
3.社会保障全体との兼ね合い
医療費、年金、子育て支援…日本は社会保障にかかるお金がどこもパンパンです。
その中で「介護だけに多く配分する」のは難しい状況があります。
[PR]利用者負担を増やすか、国の支出を増やすか
介護報酬を上げようとすると、財源をどこから持ってくるのかという課題にぶつかります。
大きく分ければ二通りあります。
・① 利用者の自己負担を増やす
・② 国や自治体の負担(=税金の投入)を増やす
でも①を選べば家計への負担が増えて、サービスを受けにくくなる人が出てしまう。
②を選べば国の財政赤字がさらに悪化する。
その綱引きの中で、介護職員の給与改善が後回しになりやすいのです。
「処遇改善加算」とは?
とはいえ、国も何もしていないわけではありません。
その一つが「処遇改善加算」と呼ばれる仕組みです。
これは、介護サービス事業者が条件を満たすと「介護報酬にプラスして加算」
を受け取れる制度で、その分を職員の給与にまわすことが期待されています。
最近では「特定処遇改善加算」や「ベースアップ加算」など、名前も複雑に増えてきました。
このおかげで、昔に比べれば給与は徐々に改善してきています。
でも現場からすると「手続きが複雑」「結局は数万円レベルで劇的な改善にはならない」
という声も多いのが現実です。
介護職員の給与は“政治的な問題”
ここまでお読みいただけると、「介護職員の給与改善は単に経営者の努力では解決できない」
という構造が分かってきたのではないでしょうか。
実はこれは、経済問題というより政治問題なんです。
つまり、国全体で「介護にどれだけお金を投じるか」という優先順位の問題なんですね。
医療や教育、子育て支援…。
どれも必要だからこそ、みんなで分け合うしかない。
そんな中で「介護をもっと重視して欲しい」という声をどう大きくしていくかが、
一つのカギになります。
[PR]介護の価値は目に見えにくい
介護士の給料が上がりにくい理由には、もうひとつ大切な視点があります。
それは介護の“成果”が目に見えにくいということです。
たとえば営業職やエンジニアなら「売上アップ」「新製品開発」
といった形で成果が数値化されます。
でも介護は違います。
やっていることは「その人がより安心して生活できる」という、
とても大事だけれど数字になりにくいもの。
だから社会的に評価されにくい傾向があるのです。
その目に見えにくい価値を、どう社会に理解してもらうか。
これはとても大きな課題の一つです。
社会全体が「介護の価値」を認める
まず大切なのは、介護が「社会のインフラ」だともっと認識されることです。
道路や学校、病院と同じように、介護があることで社会が回っているのに、
それがまだ十分に評価されていません。
つまり「当たり前に介護がそこにある」という空気が、
逆に価値を埋もれさせてしまっているのです。
ですが、もし介護がなかったら――
家族が無理な介護で心身を壊したり、仕事を辞めざるを得なくなる人がもっと増えるでしょう。
実際、介護離職は毎年10万人以上と言われています。
介護の充実が「働き続けられる社会」を支えている。
この事実をもっと共有していくことが、待遇改善につながる第一歩だと思います。
給与改善のための制度改革
次にカギを握るのは制度改革です。
たとえば現在の「処遇改善加算」だけでなく、
よりシンプルで分かりやすい仕組みで給与底上げをすること。
また、介護報酬そのものを大幅に引き上げる議論も必要です。
欧州のいくつかの国では、介護や福祉職を「専門職」として認め、
医療職と同等の報酬体系を用意しているところもあります。
もちろん日本の財政事情を考えると一足飛びには難しいですが、
「介護士=専門性の高い職業」という位置づけを社会で強めていくことが大切です。
[PR]テクノロジーによる負担軽減
また、直接「給料を上げる」という話ではないのですが、
介護現場の負担を減らす工夫も欠かせません。
最近は介護ロボットや見守りセンサー、ICT記録システムなどがどんどん導入されています。
これによって業務効率が上がれば、職員一人ひとりの余裕が生まれ、
「人が足りないから残業ばかり」という状況を少しずつ改善できます。
結果的に離職が減り、安定した人手で現場が回ると、
給与に還元する余裕も出やすくなるはずです。
つまり「ただ人を増やす」のではなく、「人が働きやすい環境を技術で作る」ことも、
給与改善の土台になるんですね。
キャリアパスの整備
もう一つ重要なのが、介護士さん自身のキャリアアップの道筋をしっかり整えることです。
今でも「介護福祉士」という国家資格がありますが、
それを取っても目に見える昇給が少ないという課題があります。
これを改善し「資格を取れば確実に給与が上がる」仕組みが広がれば、仕事に希望が持てます。
また、介護の専門性を活かしてケアマネジャーや管理職へ進むルート、
教育や地域包括ケアに関わるルートなど、キャリアの多様化も大きな意味を持ちます。
最後に
これは私たち一人ひとりにもかかわる話です。
「介護職は給料が安い」という話を聞いても、
どこか「仕方ないよね」と受け止めてしまうことはありませんか?
介護士の給料が上がらない理由には、制度の仕組み・国の財政・社会の意識など、
いくつもの要素が絡み合っています。
それを少しずつ変えていくためには、介護の重要性を声に出していくことも大切です。
「大切な仕事である」という認識が広がれば、きっと未来は変えていける。
介護士さんの給料や働きやすさを改善することは、単に「一つの職業を守る話」ではありません。
日本社会全体が、高齢化の中で安心して生きていける基盤を整えることでもあります。
介護士の未来は、社会の未来そのもの。
介護の現場で日々奮闘している方々が、もっと安心して働ける社会へ——
その第一歩は、私たち一人一人の気づきかもしれません。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」
- キラケア「介護職の給料はいくら?平均給与額や年収アップ方法」
- 厚生労働省最新調査「介護職員の給与、平均33.8万円 前年比4.3%増」
- 福祉新聞「全産業と介護職の給与差8万円 委員から格差是正求める声相次ぐ」


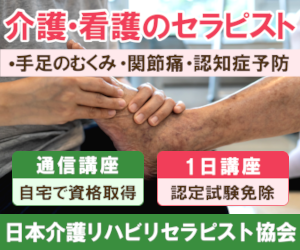




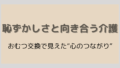
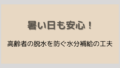

コメント