こんにちは。
今日は少し重くて、
でもとても多くの人が心のどこかで抱えているテーマについてお話ししたいと思います。
「親との関係が昔からうまくいっていなかった…それでも介護ってしなきゃいけないの?」
そう思ったことがある方、もしくは今まさにそういう状況の方もいるかもしれません。
世間では「親孝行は素晴らしいこと」という語られ方が多いですよね。
でも現実には、必ずしも親との関係が良好だったわけではない人もいるし、
幼い頃からのわだかまりや傷が残っていることもあります。
そんなとき、介護をする・しないという選択は、とても難しい問題になります。
今日は、そういう複雑な状況を整理しながら、
少しでも気持ちがラクになるヒントを見つけてもらえたらいいなと思っています。
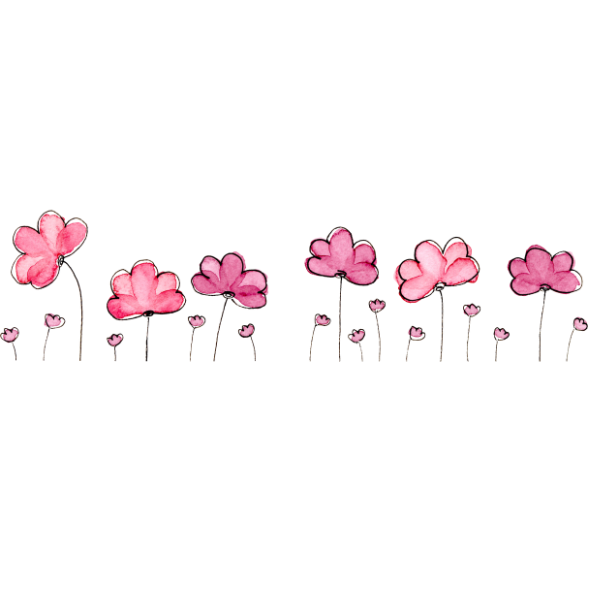
まずは「気持ちの整理」から
「介護」という言葉は、表面的には「お世話すること」と見られがちですが、
実際はそこに感情や過去の出来事、未消化の想いがたくさん絡みます。
親との関係が良くなかった場合、介護の話が出てきた瞬間に、
怒りや拒否感が湧くこともあると思います。
人の気持ちは「過去」に影響されます。
無理やり抑え込もうとすると、自分がすり減ってしまいます。
だから最初にやることは、「介護をするかどうか」ではなくて、
自分の感情を素直に紙に書き出す、ということです。
・正直、関わりたくない
・できるなら距離を置きたい
・でも、放っておくのもモヤモヤする
こうやって書くことで、「自分がどんな気持ちを持っているのか」が見える化されます。
法律や義務の観点と、心の観点は別物
冷静に考えると、日本では民法に「扶養義務」というものがあります。
親子には経済的に助ける義務があるとされていますが、
「必ず自分で介護をしなければいけない」という決まりはありません。
でも、多くの人は法律よりも「世間体」や「罪悪感」に押されて判断してしまいます。
ありがちなのは、「全部やる」か「まったく関わらない」かの極端な二択で考えてしまうこと。
知っていてほしいのは、その間にはグレーゾーンがあるということです。
例えば、
・施設に入所してもらう手続きだけをサポートする
・遠方から月1回だけ様子を見に行く
・費用の一部だけ負担する
こうした形だって立派な関わり方です。
関わり方を細分化すれば、
「感情的にも物理的にも限界を超えずに関われるレベル」がきっと見つかります。
[PR]親との過去がつらいときの、心の声をきく
もし過去に親からの暴言や無視、コントロール、過干渉などで心が傷ついた経験があるのなら、
「介護すべき」と正面から向き合うのは本当にしんどいことです。
そんなときは、介護の話をする前に、まずは自分の安全と心の安定を優先してください。
例えば、
・信頼できる友人やカウンセラーに今の気持ちを話す
・日記やメモに、過去の出来事や感情を書き出す
・「あの時の自分は苦しかった」と、自分の気持ちを肯定する
これは介護の是非を決める前の、心の準備運動みたいなものです。
心がしんどい状態で介護の判断をすると、その後に後悔や怒りが倍増することがあります。
だからまずは、自分の気持ちを抱きしめるステップが大切なんです。
「介護する/しない」を判断するための3つの軸
介護を引き受けるかどうかは、感情だけでなく、冷静に判断する要素があります。
おすすめなのは、次の3つの軸で考えてみる方法です。
1.心の余裕があるか?
過去の関係によって気持ちが大きく揺れる状態なら、
まずは「できる」「できない」を自分に正直に答えることが大切です。
2.時間・体力的に可能か?
仕事や家庭との両立が難しい状況で無理をすると、共倒れになってしまいます。
3.ほかに頼れる人や制度はあるか?
きょうだいや親戚、行政サービス、訪問介護、施設など、代替の選択肢を調べておくことで
「自分だけが背負わなきゃ」という思い込みを減らせます。
この3つを書き出して「OK/NG」でチェックすれば、自分の立ち位置が見えやすくなります。
罪悪感とどう付き合うか
介護をしない選択をする人の多くが悩むのが「罪悪感」です。
親に対して距離を置くことを「ひどいことをしているんじゃないか」と感じてしまうのです。
罪悪感は「こうあるべき」という思い込みから生まれることが多いです。
この場合、考え方の転換が役立ちます。
「私は私の生活を守るための選択をしている」
「介護しないと決めたのは悪いことではない」
こんなふうに、自分を責める思考から少しずつ距離をとっていきます。
[PR]周囲と話すときのポイント
介護の話は、家族や親戚との関係も複雑にします。
とくに兄弟姉妹間では「誰がどれだけ負担するか」で揉めやすいです。
話し合うときのコツは、次の3つ。
1.事実ベースで話す
「私は感情的にしんどいからできない」という個人の感情と合わせて、
「勤務時間が長い」「自分も持病がある」といった客観的事実を伝える。
2.代案をセットで出す
「私は毎日の介護は無理だけど、月1回の通院付き添いはできるよ」
など、完全な拒否でなく部分的な関わりを提示する。
3.制度の情報を共有する
自治体やケアマネジャー、介護保険制度の情報を事前に調べて資料として渡すと、
建設的な会話になりやすいです。
また、感情的なぶつけ合いになりそうなら、
第三者(ケアマネ、民生委員、カウンセラー)に入ってもらうのも有効です。
介護を引き受けると決めたときの心構
親との関係が複雑な場合、介護に踏み切る決断はとても大きなものです。
その際にまず意識してほしいのは、「全部自分で抱え込まない」ことです。
・介護保険サービスや地域包括支援センターを積極的に活用する
・訪問介護やデイサービス、ショートステイなどの外部支援をできるだけ組み合わせる
・週に1日は完全に介護から離れる「休養日」を確保する
また、過去のわだかまりから感情が揺れる瞬間があります。
そのときは「これは昔の感情」「これは今の状況」と、
心の中で線引きして区別する練習が役立ちます。
完璧に割り切るのは難しいですが、
「私には私の人生がある」ということを忘れないことが大切です。
[PR]最後に
親との関係が良くなかった場合の介護問題の答えは人それぞれ。
「やる」も「やらない」も、どちらも勇気のいる選択です。
大事なのは、世間体や過去のしがらみだけで判断せず、
「自分の生活と心を守る」という視点を持つことです。
そして、すべてを一人で背負わない環境を作ることです。
あなたの人生は、あなたのもの。
そのことを忘れないでいてほしいと思います。
少しでも心が軽くなったり、
「こうしてみようかな」と思えるきっかけになれば幸いです。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- Diamond Online「関係が良くない親なら、愛ある介護じゃなくていい」
- Homes介護のホンネ「介護したくないけど絶縁もできない毒親に私がした3つのこと」
- 友愛マール「両親の介護を経て。介護はプロに。二人で暮らす気楽さ」



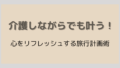


コメント