こんにちは。
「障害者手帳を持っているけど、介護保険も使えるの?」
こんな疑問を持たれている方、多いんではないでしょうか。
ややこしいし、窓口も違うし、
調べれば調べるほど頭が混乱してしまいますよね。
実は、障害者手帳と介護保険はそれぞれ別の制度で、目的も対象も少しずつ違うんです。
でも条件がそろえば、両方の支援をうまく使うことも可能なんですよ。
今回は、「併用って本当にできるの?」 「どっちが優先されるの?」 「注意点は?」
そんな疑問を、できるだけ分かりやすい言葉でお話ししていきますね。
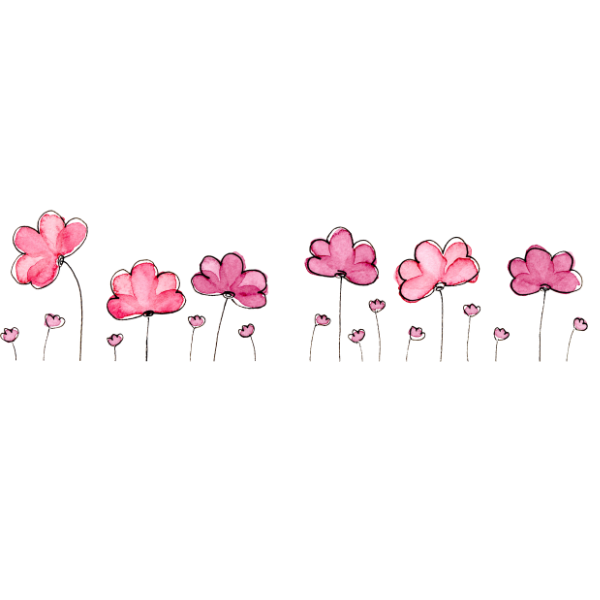
そもそも障害者手帳と介護保険って何が違うの?
まずは、基本の考え方から整理してみましょう。
似た制度のように感じますが、実は目的もサポートの対象も違うんです。
障害者手帳の目的と対象
障害者手帳には、主に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。
これらは、障害によって生活に制限がある方が、少しでも暮らしやすくなるように設けられた制度
です。
医療費の助成や、交通機関の割引、税金の控除など、日常生活を支えるためのサポートが中心に
なっています。
「介護を受けるため」というより、「生活を続けやすくするため」の制度、
というイメージですね。
介護保険の目的と対象
一方、介護保険は、65歳以上の高齢者や、40歳以上で特定疾病がある方を対象にした制度です。
目的はとてもシンプルで、
「介護が必要になったときに、サービスを受けられるようにすること」。
訪問介護(ヘルパーさん)やデイサービス、福祉用具のレンタルなど、
実際の介護サービスが中心です。
つまり、 障害者手帳は「暮らしを支える制度」、 介護保険は「介護を支える制度」と考えると、
少し整理しやすくなると思います。
どっちが優先されるの?
障害者手帳も介護保険も対象になる場合、原則としては「介護保険が優先」されます。
これは、介護保険が高齢者や特定疾病の方のために、より手厚い介護サービスを提供する仕組み
として整えられているからです。
たとえば、65歳以上で身体障害者手帳を持っている場合、 介護サービスについては
介護保険を使うのが基本になります。
ただし、ここで誤解しやすいのが、
「じゃあ、障害者手帳の支援は使えなくなるの?」という点。
実は、医療費助成や割引、税制優遇など、障害者手帳にひもづく支援は、
介護保険を使いながらでも引き続き利用できるんです。
併用はできるの?
結論から言うと、併用はできます。
ただし、すべてを同時に使えるわけではなく、「内容が重なるかどうか」がポイントになります。
たとえば、障害福祉サービスの居宅介護と、介護保険の訪問介護。
似たような内容の場合は、「どちらか一方だけ」と判断されることがあります。
でも、障害福祉サービスでしか対応できない支援や、介護保険の範囲外のサポートについては、
併用できるケースもあります。
正直、自分で判断するのはかなり難しいです。
だからこそ、ケアマネさんや相談支援専門員と一緒に、
「どの制度をどう組み合わせると一番生活がラクになるか」を考えることが大切なんです。
具体例で見る、併用のイメージ
少し具体的に見てみますね。
65歳のAさんは、若い頃の事故で身体障害者手帳を持っています。
65歳になってから要介護認定を受け、介護保険も使えるようになりました。
この場合、デイサービスや訪問介護などの介護サービスは、介護保険が中心になります。
一方で、障害者手帳による医療費助成やタクシー券、税金の控除などは、
これまで通り利用できます。
さらに、介護保険ではカバーしきれない外出支援などについて、
障害福祉サービスを併用できることもあります。
うまく使い分けることで、生活の中で受けられるサポートが、ぐっと広がるんです。
手続きはどうするの?
併用するには、いくつかのステップがあります。
① まずは介護保険の認定を受けて、要支援・要介護の判定を出してもらいます。
② その上で、障害者手帳を持っていることを、ケアマネジャーさんや地域包括支援センターに
伝えます。
③ 介護保険と重ならない部分について、障害福祉サービスの申請を検討し、
市町村が内容を確認します。
窓口で相談すれば、流れや使い分けについて丁寧に教えてもらえるので、
遠慮せずに相談してみて下さいね。
ケアマネと相談支援専門員、それぞれの役割
介護保険を使うときは、ケアマネジャーが中心になります。
障害福祉サービスを使う場合は、相談支援専門員がサポートしてくれます。
この2人が連携してくれると、制度をまたいだ調整がとてもスムーズになります。
もし両方の制度を使うことになったら「情報共有」をお願いすると、
安心感はかなり違います。
ー毎日の食事作りの負担が少し減りますよー
[PR]地域によって支援内容が違うことも
もうひとつ知っておいてほしいのが、地域差です。
外出支援や紙おむつの支給など、自治体独自の支援は、内容や条件が地域ごとに違います。
同じ障害があっても、住んでいる場所で差が出ることもあります。
え?なんで同じ障害なのに住んでる場所で差が出るの?って思いますよね…。
支援制度って意外と「誰も教えてくれなかった..」ということが多いんです。
だからこそ、市役所や福祉課に相談して、 「今使える制度」を一緒に確認することが
とても大切なんです。
気をつけたいポイントとまとめ
障害者手帳と介護保険は心強い制度ですが、
相談先が分かれているため、「どこに聞けばいいの?」と迷いやすいです。
そんなときは、まず地域包括支援センターへ相談してみてください。
担当者によって説明に差が出ることもあるので、 自分でも少し知識を持っておくと、
話がスムーズに進みますよ。
⚫︎障害者手帳と介護保険は、条件がそろえば併用できる
⚫︎ただし、介護サービスについては介護保険が優先され、
内容が重なる支援はどちらか一方になる
⚫︎制度をうまく使い分けることと、ちゃんと専門職に相談することが大切
ー面倒な手続きはプロにお任せしてラクをしませんかー
[PR]最後に
制度って、正直難しいし、ややこしくて面倒ですよね。
読んでいるだけで疲れてしまったり、後回しにしたくなったり..。
でも、ちゃんと知って使うことで、日々の負担や不安を和らげてくれるんです。
すべてを一人で抱え込まなくていいように、制度という仕組みを上手に頼りながら、
無理のない形で日々向き合っていけるといいですね。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
ー介護のことばかり考えていると、気づかないうちに、
自分の体や心の変化を後回しにしてしまうこともありますよねー
[PR]参考
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」(令和6年版)
- 厚生労働省「障害者自立支援法のあらまし」
- 東京都福祉保健局「障害者手帳をお持ちの方への支援制度」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービス等の手引き」
- 日本相談支援専門員協会「相談支援専門員の役割と実践事例集」


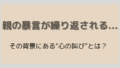
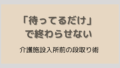

コメント