こんにちは。
「お母さまから、職員に対してきつい言葉があったようで…」
ある日突然、施設やデイサービスのスタッフからそんな連絡が来たら、
どんな気持ちになるでしょうか。
今回は、親が介護士さんに暴言を吐いてしまった時、家族としてどう受け止め、
どう対応していけばいいかを一緒に考えてみたいと思います。
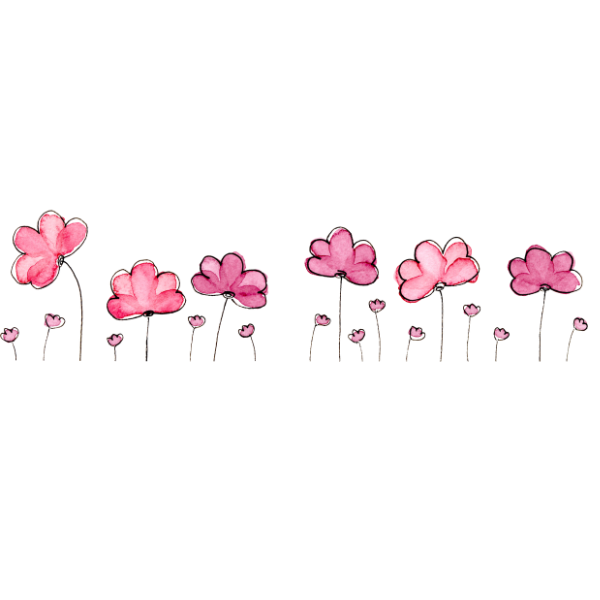
高齢者の“暴言”って、どんなときに起きる?
実は、施設や在宅介護の現場では「暴言・暴力」の問題は珍しくありません。
・「こんなこと頼んでないわよ!」
・「勝手に部屋に入るな!」
・「どこ触ってるんだ!」
これは決して、本人が悪いからではなく、
認知症の症状や混乱、不安、羞恥心、プライドなどが重なって現れることが多いのです。
家族が受ける“クレーム”の重さ
介護スタッフから「お母さまが暴言を…」と伝えられたとき、
家族の心にはさまざまな感情が渦巻きます。
・申し訳なさでいっぱいになる
・「うちの親がそんなことを…」と信じられない
・恥ずかしい
・スタッフに嫌われてしまったのではないか
でもこれはあなたの責任ではありません。
施設や訪問サービスは、こういった場面に対して一定の理解と対応の準備があります。
家族が深く思い詰めすぎないことが大切なんです。
施設やスタッフと連携することが鍵
職員さんからの報告や連絡は、「ご家族を責めたいから」ではなく、
今後の対応を一緒に考えたい場合がほとんどです。
「迷惑をかけたから…」と遠慮して連絡を避けてしまう方もいますが、
こういう時こそ、職員さんを“味方になってもらう”ことが大切です。
施設によっては、介護記録とは別に“家族との連絡ノート”を設けてくれるところもあります。
・「最近、家では落ち着いています」
・「歯が痛いと言っていたので、様子を見てください」
・「新しい薬が増えました」
ちょっとした情報共有で、ケアのヒントが見つかることもあるんです。
こういったやり取りができると、スタッフ側も
「家族と一緒に支えていける」と感じやすくなります。
[PR]同じようなことが何度も…繰り返される暴言
「この前もあったのに、また…」
そんなふうに、暴言が何度も繰り返されると、家族としては本当に悩んでしまいますよね。
・「またクレームが来るんじゃ…」とびくびくする
・職員に申し訳なくて顔を合わせづらくなる
・自分のせいのように感じて、気持ちが沈んでいく
でも、繰り返される暴言の裏には、本人なりの「SOSサイン」が隠れていることが多いんです。
よくある3つのきっかけ
① 身体的な不快感
痛み、かゆみ、トイレの不安など、
うまく言葉にできない不快感が暴言として出ることがあります。
② 認知症による混乱
「見知らぬ人が触ってくる」「家に帰らせてくれない」と感じることで、
防衛反応として怒りが出てくることも。
③ プライドの揺らぎ
「こんなこともできなくなった」と自分を責める気持ちや、周囲への依存への戸惑いが、
苛立ちに変わることがあります。
家族が取れる小さな対応
もしご本人に話が通じる状態であれば、責めるのではなく、やさしく伝えてみましょう。
「昨日ちょっと怒っちゃったみたいだね、どうしたの?」
「言いたいことがあるなら、私にも教えてね。」
感情に寄り添ってあげるだけで、次に気持ちを吐き出す先が変わることもあります。
第三者の力を借りてもいい
何度も続くと、「もう限界かも…」と思うことも当然です。
そんな時は、施設の相談員さんやケアマネジャー、
場合によっては地域包括支援センターに相談してみてください。
家族だけでなんとかしようとしなくていい。
相談していいし、頼っていいんです。
「困ったね」「一緒に考えよう」と言ってくれる存在が、きっといます。
[PR]環境の変化をできるだけ小さく
急な部屋替え、スタッフの交代、行事の参加などのちょっとした変化も
本人に突っては大きなストレスになります。
・あらかじめ本人に説明しておく
・「〇〇さんが今日は担当してくれるよ」と前もって伝える
そんなふうに、予告と安心をセットにすることが、本人の感情の波を和らげ、
混乱を防ぐカギになります。
暴言があっても、親は“悪い人”じゃない
ついつい、「あんなこと言うなんて」と落ち込んでしまうけれど、
暴言があっても、それは一部の“症状”であって、本人が悪いわけではありません。
いつも優しい言葉をくれたこと。
家族のために一生懸命働いてくれたこと。
静かに微笑んでくれたあの表情。
それらは全部、ちゃんとその人の中に今もあります。
だから、暴言にばかり目を奪われず、
できるだけその人の“根っこ”を見てあげられるといいなと思います。
最後に
親が暴言を吐いたことで、クレームを受けた――
その経験は決して軽いものではないし、家族にとっても大きなストレスです。
でも、そこで立ち止まって、「今、できること」をひとつずつ探していけば、
少しずつ、心も現場も落ち着いていくことがあります。
迷いながらでも、悩みながらでも、できることを見つけていけたらいいですね。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 厚生労働省「令和4年度 高齢者虐待の防止・高齢者の養護者に対する支援等事業」
- 公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査」
- NCCU(日本介護クラフトユニオン)「介護現場における利用者・家族からのハラスメントの実態あり」

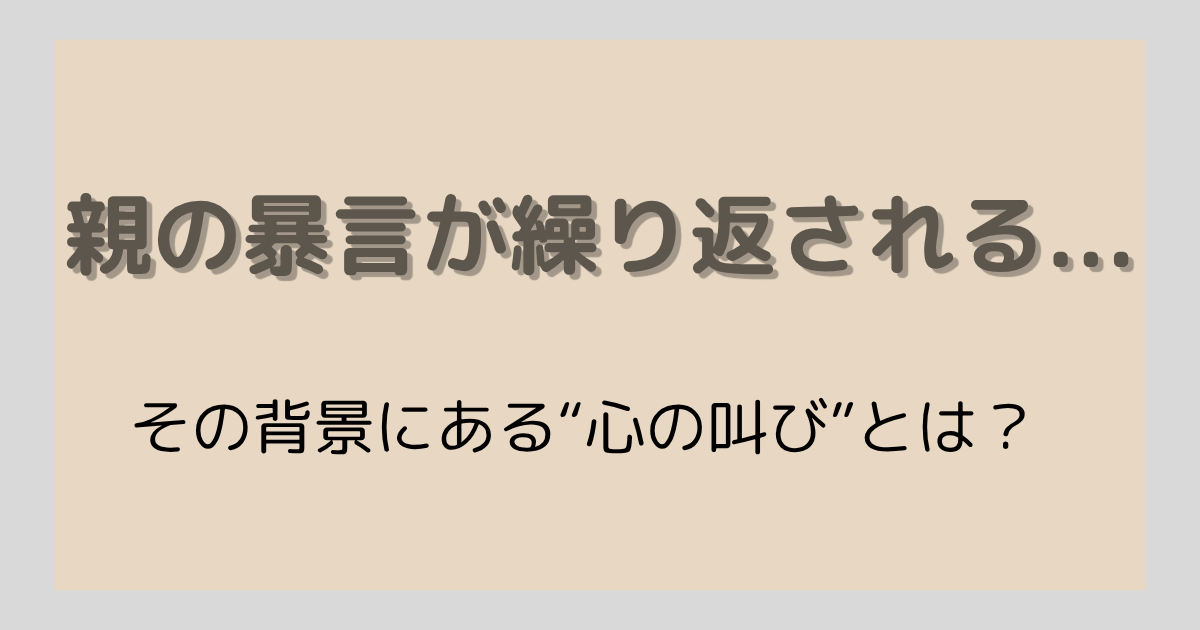

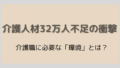


コメント