こんにちは。
「こんなに忙しいのに、いつも人が足りない…」
介護の現場では、そんなため息が日常になりつつあります。
今回は、介護の人手不足という深刻な課題について、現場で何が起きているのか、
なぜこうなってしまったのか、その背景を紐解いていきたいと思います。
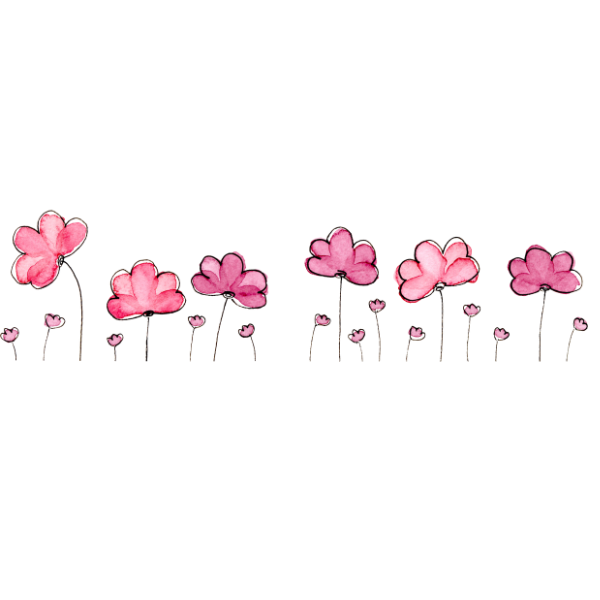
人手不足、現場のリアル
まずは、今の介護の現場がどんな状態なのか、少しのぞいてみましょう。
特別養護老人ホームやグループホーム、デイサービスなど、
どの施設でも共通して聞かれるのが「人が足りない」という声。
・夜勤が2人だけで30人の利用者を見ている施設
・スタッフが急に辞めても、代わりが見つからないままシフトを回す毎日
・ギリギリの人数で、休憩時間もまともに取れない現場
これは決して一部の施設だけではなく、全国的に見られる状況なんです。
せっかく介護の仕事に就いても、早々に辞めてしまう人が多いのも現実。
「介護は好きだけど、続ける自信がない」
そんな思いを抱えたまま、やむを得ず現場を離れる人も少なくありません。

なぜ人手不足が起きているのか?
この深刻な人手不足の背景には、いくつかの要因が絡み合っています。
高齢化のスピードが早すぎる
日本の高齢化は世界でもトップクラス。
65歳以上の人口は年々増え続け、介護を必要とする人も右肩上がりです。
それに対して、介護職として働く人の数はなかなか増えていかない…。
需要と供給のバランスが崩れているのです。
低賃金と厳しい労働環境
「大変な仕事なのに、お給料が見合っていない」と感じている人は多いです。
実際、厚生労働省の調査では、介護職の平均月収は全産業平均よりも低く、
待遇面でのギャップが課題とされています。
夜勤や休日出勤、急な呼び出し…
そんな中でも、気持ちよく働ける環境が整っていないことが離職の要因に。
「介護の仕事、やってみたいけど…」
そんな気持ちがあっても、実際に踏み出せない若者も多いんです。
マイナスイメージが広がってしまうと、新しい人材が入ってこなくなり、
ますます人手が足りなくなっていくという悪循環に..。
「やりがい搾取」という言葉も
介護職には「やりがいが大事」とされる風潮があります。
もちろん、誰かの役に立つ喜びは大きな魅力。
でも、「やりがいがあるから我慢してね」では、人は長く続けられません。
やりがいと同時に、安心して暮らせるだけの報酬や休息がなければ、
人手不足はいつまでも解消されないでしょう。
[PR]人手不足を補う現場の工夫
「人がいないなら、やり方を変えるしかない」
そう考えて、現場ではさまざまな工夫がされています。
ICTや見守り機器の導入
最近では、介護現場にもテクノロジーの力が少しずつ入ってきています。
・センサーで利用者の動きを把握
・ナースコールがスマホに通知されるシステム
・記録の電子化によって手書きの負担を軽減
こうした機器は、働くスタッフの「負担軽減」にとても効果的。
夜間の見回りが楽になったり、情報共有の手間が減ったりと、
限られた人手でも安全にケアができる環境が整いつつあります。
介護ロボットの研究と導入支援
厚生労働省はまた、介護ロボットの導入支援にも力を入れています。
・移乗介助をサポートするロボット
・会話を通じて高齢者を見守るAI機器
・歩行補助やリハビリに活用できる機器
まだまだ発展途上ではあるものの、実際に使ってみると
「腰の負担が減った」「一人でできることが増えた」という声もあり、
現場に希望を与えています。
チームケアの意識
一人で抱え込まないように、職員同士が「チーム」として連携する動きも広がっています。
・声かけのルールを決めて助けを求めやすくする
・新人へのフォロー体制を強化
・困ったときの相談窓口を設ける
こうした取り組みは、精神的な負担を和らげてくれます。
「自分だけがつらいわけじゃない」と感じられる環境づくりが、
離職防止にもつながっているんです。
制度のサポートはどうなっている?
国や自治体も、この人手不足問題に対してさまざまな対策を進めています。
介護職の処遇改善加算
国の施策の一つに、「処遇改善加算」という制度があります。
これは、介護職員の賃金を上げるために、介護事業所に追加で支給される補助金です。
・介護職員の月給を数万円アップできる仕組み
・スキルや経験に応じて段階的に加算される
この制度を活用して、賃金アップや賞与に充てている施設も増えてきました。
ただし、加算の申請や条件がやや複雑で、すべての施設がうまく活用できているとは限りません。
外国人介護人材の受け入れ
日本では、海外からの介護人材の受け入れも進んでいます。
・EPA(経済連携協定)に基づく看護・介護福祉士候補者の受け入れ
・技能実習制度や特定技能ビザでの就労
外国人スタッフは、文化の違いを乗り越えて一生懸命働いてくれている方が多いです。
現場に新しい風を吹き込むとともに、多様なケアの形を模索するうえで大きな力となっています。

職員が続けやすい職場とは
人手不足を根本から解消するには、「辞めたくない職場」を作ることが大切です。
たとえば…
・シフトの希望が通りやすく、家庭と両立しやすい
・新人でも相談しやすい雰囲気がある
・評価や報酬が明確で、努力が報われる仕組みがある
こうした環境づくりが、長く働ける土台となっていきます。
そして何よりも大切なのが、「現場のリアルな声」を吸い上げていくこと。
・実際に働く職員の意見を聞く場を増やす
・制度設計に当事者の声を反映する
机上の理論ではなく、実際の介護の現場に立つ人たちの声が、
今後の制度や働き方改革に活かされることが求められています。
[PR]介護の未来をどう支える?
介護の人手不足は、簡単に解決できる問題ではありません。
でも、だからこそ、できることから一つずつ動いていくことが大切です。
地域で支えるという視点
「介護は家族や施設だけで担うもの」という考え方から、
「地域みんなで支える」という発想へと広がっています。
・地域のサロンや見守り隊
・高齢者が通える居場所づくり
・介護予防の体操教室や健康相談会
介護を「特別なこと」から「日常の一部」にしていく取り組みが、
全国で少しずつ始まっています。
介護職に誇りを持てる社会へ
介護職は、本当に尊い仕事です。
誰かの人生のそばに寄り添い、その人らしく生きる時間を支える。
それって、なかなかできることじゃないですよね。
でも現実には、社会的な評価がまだまだ低いのが現状です。
「ありがとう」の言葉も、もっと届いていい。
「介護職やってるんだ、すごいね」と、自然に言い合える空気があれば、
それだけでもきっと、たくさんの人が救われるんじゃないかと思います。

最後に
もしあなたが、今介護をしていない立場でも、
もし「関係ない話かも」と思ったとしても、
誰もが、いつかは「支える側」「支えられる側」になるかもしれないのが介護です。
だからこそ、今からできることー。
介護の仕事をする人が、もっと笑顔で働けるように。
支える家族が、少しでも心にゆとりを持てるように。
そして、大切な人がその人らしく、安心して年を重ねていけるように。
そんな未来を、私たち一人ひとりの力で少しずつ築いていけたらいいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
参考
- 厚生労働省「介護人材の確保について」
- 公益財団法人 介護労働安定センター「令和5年度 介護労働実態調査」
- 内閣府「高齢社会白書(令和6年版)」
- 独立行政法人 労働政策研究・研修機構「介護人材の現状と課題」
- 厚生労働省「介護ロボットの導入支援事業」

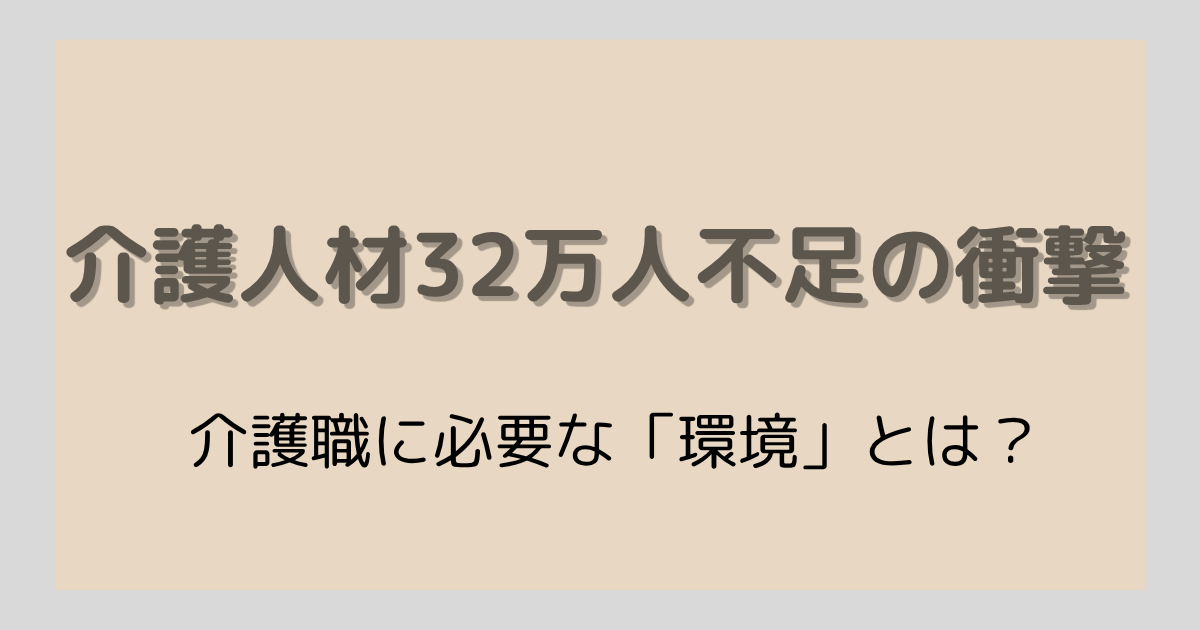


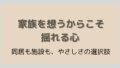
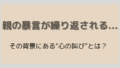

コメント