こんにちは。
介護をしていると、「食事」に関する悩みは尽きませんよね。
「最近、食べこぼしが増えてきたな…」
「むせることが増えて、心配…」
そんなときに検討するのが、やわらか食やきざみ食などの“介護食”です。
でも、「やわらか食」と「きざみ食」って、どう違うの?
どっちがその人に合っているの?
間違った選び方をすると、逆に誤嚥や栄養不足を招くこともあるんです。
今回は、やわらか食ときざみ食の違いや、それぞれのメリット・注意点、
選び方のコツまでをやさしく解説していきます。
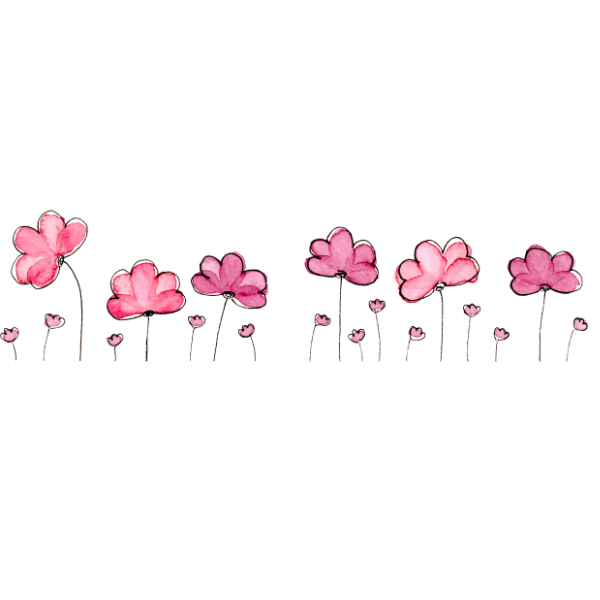
やわらか食ときざみ食の違いとは?
まずはそれぞれの特徴から見てみましょう。
【やわらか食】噛まなくても食べられる、なめらかな介護食
やわらか食とは、噛む力や飲み込む力が弱くなった方のために、
食材をやわらかく調理した食事のことです。
たとえば、
・とろとろの煮物
・ミキサーでなめらかにしたおかず
・ゼリー状に加工された料理
などがあり、飲み込みやすさを重視して作られています。
【きざみ食】食材を細かく刻んだ食事
きざみ食は、通常の料理を細かく刻んで提供するスタイルの食事です。
「噛む力はあるけど、大きいままだと食べづらい」という方に向いています。
たとえば、
・刻んだ肉じゃが
・みじん切りの炒め物
・小さく刻んだ焼き魚
など、料理の見た目はそのままに近く、食べやすさを意識した食事です。
見た目は似てる? でも目的が違う!
やわらか食ときざみ食は、見た目では違いが分かりにくいこともあります。
でも、大きな違いは「噛めるかどうか」「飲み込めるかどうか」。
噛む力がある人にはきざみ食、
噛むことや飲み込むことが難しい人にはやわらか食が合っているのです。
どちらも「食べる楽しみ」を残しながら、安全に食事をとってもらうための工夫なんですね。
[PR]間違った選び方が危険な理由
「やわらかくすればいいでしょ?」
「とりあえず刻めば大丈夫」
…実はこれ、ちょっと危ない考え方なんです。
たとえば、きざみ食にしたはずなのに、かえってむせやすくなったというケースも。
これは、刻んだ食材が口の中でバラバラになりやすく、喉にまとまりにくいから。
反対に、やわらか食が本人にとって「食べた気がしない」と感じられて、
食欲が落ちてしまうこともあります。
やさしい選び方は、「その人の今」を見ること
大切なのは、
「噛めるかどうか」
「飲み込めるかどうか」
「食事の時間を楽しめているか」
本人のいまの状態に目を向けながら、食事の形を選んでいくことがポイントです。
それぞれのメリット・デメリットを知ろう
やわらか食もきざみ食も、それぞれに良さと注意点があります。
ここでは、それぞれの特徴を比較してみましょう。
やわらか食のメリット
・飲み込みやすく、誤嚥のリスクを減らせる
・噛む力が弱くても安心して食べられる
・ゼリーやムース状など、のどごしがよくて食べやすい
やわらか食のデメリット
・見た目が単調になりがちで、食欲が落ちる人も
・「噛まないこと」が逆に筋力の低下につながることも
・本人が「子ども扱いされている」と感じることがある
きざみ食のメリット
・食材そのものの味や香りを感じやすい
・見た目が普通食に近く、食事の満足感が得られやすい
・噛む力が残っている人には、筋力維持にもつながる
きざみ食のデメリット
・細かく刻むことで食材が口の中でバラバラになりやすい
・口腔内の操作が難しい方には、むせの原因になることも
・調理に時間がかかることがある
[PR]こんな声、聞いたことありませんか?
ケース①:「きざみ食にしたら、むせるようになった…」
見た目が普通に近いので「食べやすそう」と思って出したけれど、
実際には口の中でバラけて喉に入りにくかったというケース。
食べる力だけでなく、「飲み込む力(嚥下機能)」が関係していることも多いんです。
ケース②:「やわらか食に変えたら、全然食べなくなった…」
本人はまだ噛めるのに、見た目がぐちゃっとした食事になったことで、
「まずそう」「情けない」と感じてしまったようです。
やわらかくする=安全とは限らない。
本人の気持ちを尊重する視点がとっても大切ですね。
ケース③:「やわらか食に変えてから、体重が安定した!」
むせや誤嚥が減ったことで、安心して食事ができるようになり、
食事量が増えたというケースもあります。
「どちらか」ではなく、いまの本人に合った形が一番なんですね。
「本人の声」がヒントになる
・「固いものが噛みにくいな」
・「食事が楽しくない…」
・「味が薄い」
——そんな何気ないつぶやきが、実は食形態を見直すサインかもしれません。
日々の様子を観察して、少しずつ試しながら調整していくのがベストです。
介護する人が知っておくべきこと
「作る側の都合」ではなく、「食べる人の安全と満足」を軸に考えること。
これは、どんな介護の現場でも共通して言える大切なことです。
「ついきざんじゃった」
「柔らかすぎて味気ないかも」
そんな時は、次に向けてちょっと工夫すればいいんです。
[PR]選び方のステップは「観察」から
「やわらか食ときざみ食、どっちにしよう?」と迷ったとき、
まず大事なのは本人の様子をよく観察することです。
食事のとき、こんな様子はありませんか?
・食事中によくむせる
・食べこぼしが増えた
・口の中に食べ物が残る
・食べるのにすごく時間がかかる
・飲み込む前に長く口にためている
これらは「今の食形態が合っていない」サインかもしれません。
気になることがあれば、無理に判断せず、次のステップに進みましょう。
迷ったら、専門職に相談しよう
管理栄養士や言語聴覚士(ST)など、
食べること・飲み込むことのプロに相談するのはとてもおすすめです。
最近では、デイサービスや介護施設に摂食嚥下チームがあるところも多く、
個別に評価してもらえる場も増えています。
「相談するのは大げさかな…」と遠慮せず、本人の安全と満足のために声をあげていいんです。
食事の形は「変わっていくもの」
一度やわらか食にしたからといって、ずっとそれで固定しなくても大丈夫。
回復して、また普通食に戻せることもあるんです。
逆に、加齢や病気の影響で、やわらかさをさらに調整する必要が出てくることも。
だからこそ、「いまのベスト」を探し続ける柔軟さが大切です。
やわらか食・きざみ食の工夫で「おいしい!」を叶える
最近では、見た目も美しく、味もしっかりした介護食が増えています。
市販の冷凍やレトルトの介護食を取り入れるのもひとつの手。
無理をしすぎないこと、ちょっと便利な道具やサービスを使うことは、
介護を続ける上でとっても大事な視点です。
「食べること」は生きること
食べることで「おいしいね」「まだまだ元気だよ」と感じられる時間は、
介護を受ける人にとって、日常の中の大きな喜びです。
やわらか食でも、きざみ食でも、その人らしくおいしく食べられればそれでいい。
完璧じゃなくていいから、「その人らしい一口」を一緒に探していきましょう。
最後に
やわらか食か、きざみ食か——
その選択は、とても小さなようで、とても大きな意味を持っています。
「安全に」「おいしく」「楽しく」食べられることを願って、
今日のごはんが、明日へのエネルギーになりますように。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 厚生労働省「高齢者の食事と栄養管理について」
- 厚生労働省「高齢者の栄養改善に関する調査結果」
- 農林水産省「食事バランスガイド」
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会「食事形態の分類と基準」

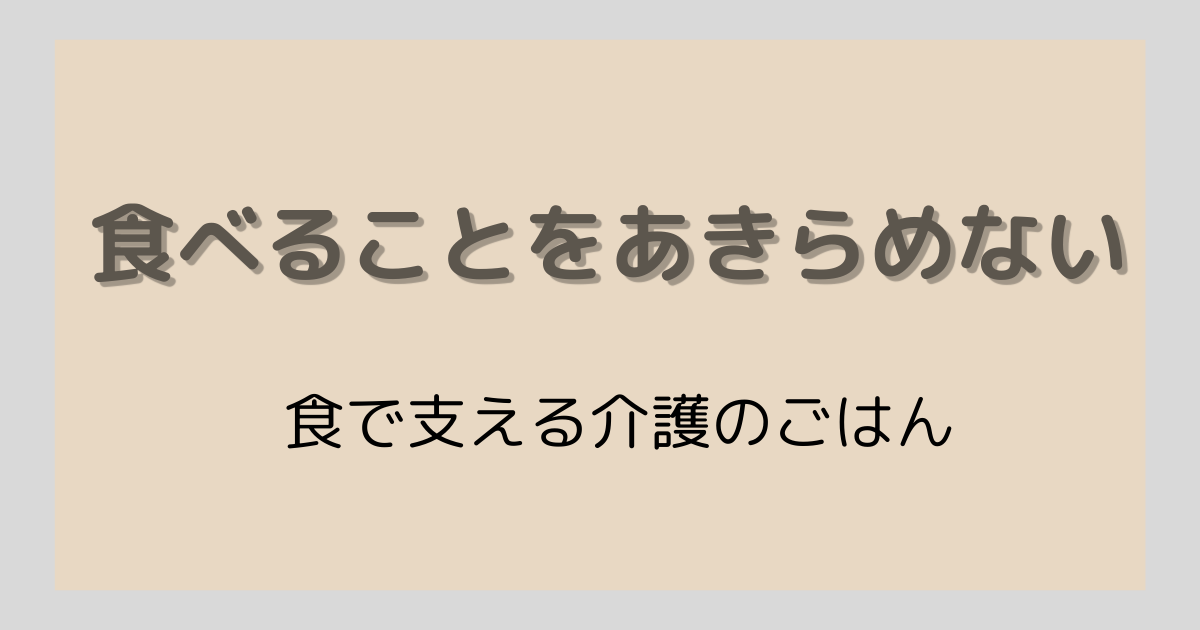

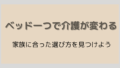

コメント