こんにちは。
介護が始まると、家族の絆が深まる場面もある一方で、
さまざまな“トラブル”に直面することも少なくありません。
「まさか自分が…」と思っていたことが現実になったり、
些細なことから深刻な問題に発展するケースも。
今回は、介護中によくあるトラブルを5つ厳選し、
今日から実践できる具体的な対策を紹介します。
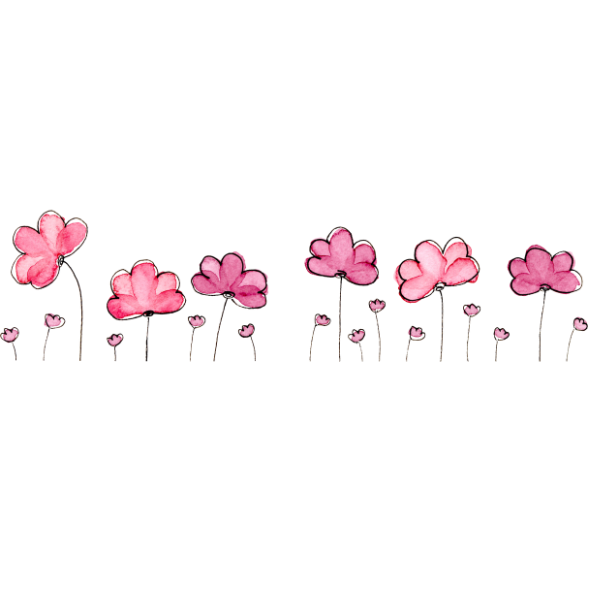
トラブル① 親の“拒否反応”が強い
介護サービスを受けさせようとしたとき、こんな言葉を言われたことはありませんか?
「他人に世話されたくない」
「そんなに私を“できない人”扱いしないで」
高齢者にとって、介護を受けるという行為は“自分の尊厳”に触れるデリケートな問題です。
とくに、今まで自立していた人や、世話をする側だった親にとっては、
「介護される側になる」という現実を受け入れにくいもの。
この“拒否反応”は、無理に押し切るほど頑なになってしまうため、
慎重に対応することが大切です。
対策:感情に寄り添いながら提案する
「お父さんが疲れちゃうから、ちょっとだけ助けてもらおうか」
「これは“お手伝い”だから、病院と同じようなもんだよ」
このように、相手が“介護されている”と感じさせない表現を使うことで、
抵抗を和らげることができます。
また、最初は短時間の利用や、「体験だけ」といった言い方でスタートするのも有効です。
介護保険サービスの中でも、ヘルパーやデイサービスなどは比較的導入しやすいため、
まずは信頼関係を築くところから始めましょう。
トラブル② 家族間の“介護の温度差”
親の介護に対する家族の関わり方には、大きな差があります。
「なんで私ばっかり」
「妹は何もしていないのに、文句ばかり言う」
このような家族間の“温度差”や“分担の偏り”は、
介護の現場ではとてもよくあるトラブルの一つです。
関係が悪化すると、介護そのものに支障が出たり、今後の方針を決める場面で
揉め事の原因にもなりかねません。
対策:情報共有と“見える化”がカギ
まずは、「誰が・どんな役割を・どの程度」担っているのかを共有することが大切です。
LINEグループやノートアプリを活用して、介護の記録や本人の様子を日々発信することで、
他の家族にも“実情”が伝わりやすくなります。
また、定期的に「家族会議」を設けて、感情的にならずに話し合う時間を持つのも有効です。
「自分ばかり負担している」と感じたら、その思いを一度整理して、冷静に伝えることで、
理解が得られる可能性も広がります。
[PR]トラブル③ 金銭的負担と家計の不安
介護が始まると、想像以上にお金がかかることに気づきます。
・介護保険の自己負担
・福祉用具やリフォームの費用
・交通費や医療費の積み重ね
「ちょっとしたことだから」と思っていた出費が、気がつけば大きな負担に。
さらに、自分の収入が減ったり、離職することになれば、
家計全体が苦しくなる可能性もあります。
対策:使える制度を最大限に活用する
介護には、金銭的なサポート制度がいくつか用意されています。
・高額介護サービス費(自己負担が一定額を超えると払い戻し)
・特定入所者介護サービス費(施設の食費・居住費の軽減)
・住宅改修費の支給(要介護認定者が対象)
また、自治体によっては、独自の助成制度やタクシー券の配布などもあります。
介護の支出を「自分たちだけでどうにかしよう」と思わず、
まずは地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、制度やサービスを活用しましょう。
トラブル④ 介護疲れによる心身の限界
介護は“気づかぬうちに疲れがたまる”のが一番怖いところです。
・睡眠不足
・自分の時間がない
・人と話す機会が減る
これらが少しずつ積み重なり、「何もかも嫌になってしまった」「誰とも話したくない」
と感じるようになってしまうことも。
最悪の場合、うつ状態に陥ったり、介護虐待にまでつながってしまうケースもあるのです。
対策:“自分のケア”を最優先に
介護をする上で最も大切なのは、「自分の心と体の健康」です。
・週に1回は外出する
・愚痴を言える相手を持つ
・デイサービスやショートステイで休息をとる
こうした“小さなリフレッシュ”があることで、長期的に介護を続ける力になります。
「自分が倒れたら終わり」と思って、
少し勇気を出して“自分の時間”を作るようにしてみてください。
[PR]トラブル⑤ 介護サービスとのすれ違い
介護保険サービスを利用している中で、
「こんなはずじゃなかった」と感じる場面も少なくありません。
・ヘルパーさんの態度に不満がある
・連絡ミスで予定が合わない
・親がスタッフとの相性を嫌がる
こうしたすれ違いが続くと、「もういいや…自分でやった方がマシ」と、
サービスをやめてしまうことにもなりかねません。
対策:ケアマネジャーに“率直に”伝える
サービスに関する疑問や不満は、遠慮せずにケアマネジャーへ伝えましょう。
「こんなこと言っていいのかな?」と思わず、気になる点は早めに共有することで、
担当者を変えたり、内容を調整してもらえることもあります。
また、「親の希望」と「現実的な介護力」のバランスを、専門職と一緒に考えることで、
よりよい方向へと修正していくことができます。
[PR]“困った”を見逃さないために
介護をしていると、どれだけ準備をしていても、予期せぬトラブルはつきものです。
今回ご紹介した5つのトラブルは、決して特別なケースではありません。
トラブルが大きくなる前に気づくためには、日々の小さな変化に目を向けることが必要です。
・親が何度も同じことを言うようになった
・自分がイライラしやすくなった
・兄弟とのLINEのやり取りがピリピリしてきた
これらは、SOSのサインかもしれません。
「ちょっと疲れてるかも」「誰かに相談したいな」——
そう思った時点で、行動を起こしていいのです。
あなたの気持ちを大切に
介護は“頑張りすぎないこと”が一番のコツ。
サービスを使う、制度を調べる、周囲に相談する…
それはすべて、“よりよい介護を続けるための知恵”です。
もし、「つらいな」「もう限界かも」と思ったら、
まずは身近な人や専門家に話してみてください。
介護の現場では、“介護される側”ばかりが注目されがちですが、
介護を担う人の心と生活も同じくらい尊重されるべきです。
弱音を吐いてもいい、立ち止まってもいいーー
そのすべてが、「あなたが一生懸命向き合っている証」です。
最後に
介護中のトラブルは避けられないものもありますが、ひとりで抱え込まず、
共に支え合いながら歩んでいくことが大切です。
「トラブルに負けない介護」を目指して、今日からできる小さな一歩を、
あなたのペースで踏み出してみてくださいね。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- NHK福祉ポータル ハートネット「介護ストレスが引き起こす家庭内の危機」
- 厚生労働省「介護をめぐる家族間の課題と支援の方向性」
- 内閣府「高齢社会白書(家族介護に関する意識調査)」

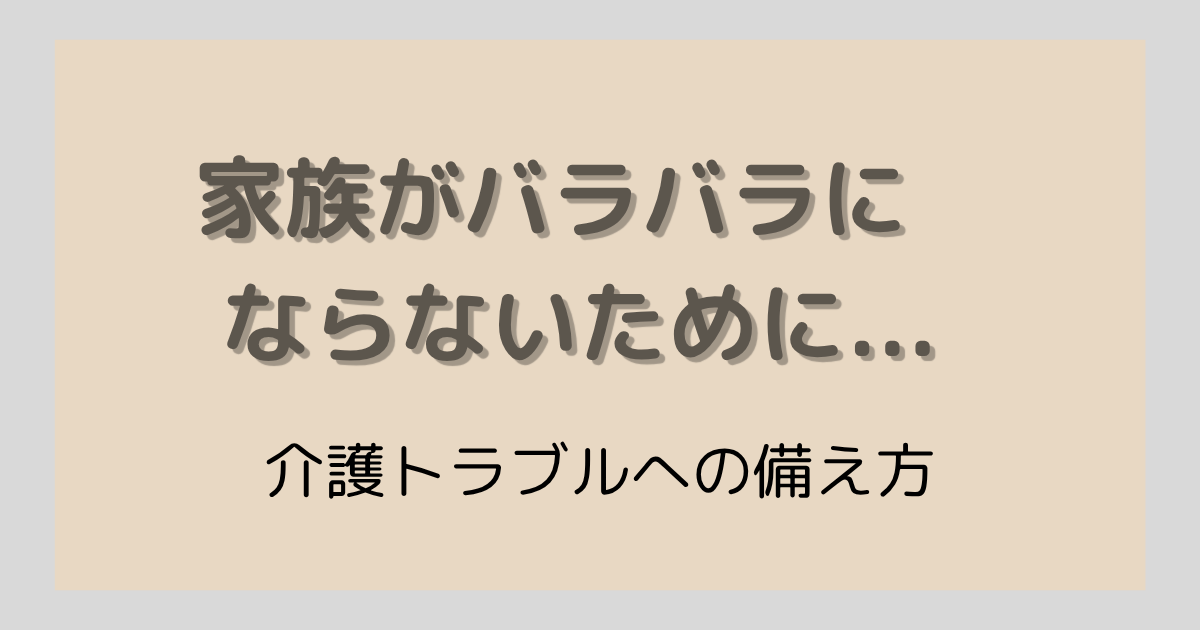




コメント