こんにちは。
「突然、介護が始まった」
「仕事と両立できず、やむを得ず退職した」
「これから先、自分の生活はどうなるのか…」
そんな声を、いま多くの人が口にしています。
親や配偶者など身近な家族の介護を理由に仕事を辞める、いわゆる介護離職。
実はこの問題、働き盛りの世代が直面する深刻な社会課題となっています。
本記事では、「なぜ介護離職がこんなに多いのか?」という疑問に向き合いながら、
その背景にある社会構造、当事者のリアルな声、そして私たちが今できる対策について
一緒に考えていきたいと思います。
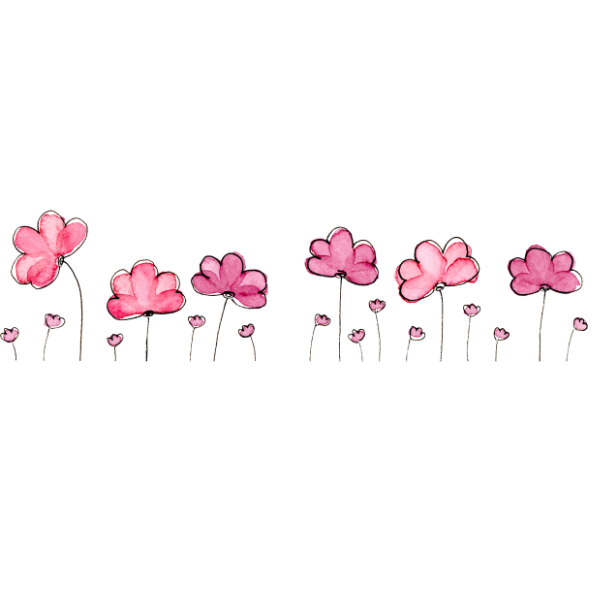
介護離職とは?
「介護離職」とは、家族の介護を理由に仕事を辞めることを指します。
厚生労働省のデータによると、1年間で約10万人が介護を理由に離職しているとされ、
その中でも特に40〜50代の働き盛り世代が多い傾向にあります。
離職者の多くは女性ですが、最近では男性の介護離職も増加傾向にあり、
誰にでも起こり得るリスクとなっているのが現状です。
介護と仕事の両立が難しい理由
「少しの間だけ手伝えばいい」 最初はそう思っていた人も、介護が長期化・
重度化していくことで、日々の生活に限界を感じるようになります。
特に在宅介護の場合、以下のような理由で仕事との両立が難しくなるケースが多いです。
・予測できない介護の突発的対応(急な病院搬送など)
・日中にしか使えない介護サービスとの時間のズレ
・介護のための有給取得が職場で理解されにくい
・精神的・身体的な負担が蓄積し、働く気力が失われていく
「仕事も家のことも完璧にこなそう」と頑張ってしまい、結果的にどちらも疲弊してしまう…。
そうして離職を選ぶ人が後を絶ちません。
[PR]介護離職の“その後”に待つ厳しい現実
離職すれば、時間的な余裕が生まれて介護には集中できます。
しかしその一方で、次のような問題が生まれます。
・収入の減少、またはゼロになる
・再就職が難しい(年齢・ブランクなど)
・社会とのつながりが失われ、孤立感が強まる
介護離職をした人の中には、「あのとき辞めなければよかった…」と後悔する声も多く、
「介護も仕事も、どちらか一方をあきらめるしかない」そんな現状が浮かび上がります。
介護が家族の関係を変える
介護は、家族の形を大きく変えます。
「親が子どもに依存してしまう」
「介護の負担が一人に集中し、きょうだい間での不満が募る」
「介護に疲れた家族同士で、口論が絶えない」
このように家族だからこそ遠慮や甘えが生まれ、関係性がギクシャクしてしまうこともあります。
また、介護をする側が「家族なんだからやって当然」と思われてしまうことで、
感謝や労いの言葉がないまま、疲弊していくことも少なくありません。
職場の“無理解”が拍車をかける
介護離職の背景には、職場での理解のなさが大きく影響しています。
「親の介護で早退したい」と言ったとき、
「また?」「家庭のことは自分で何とかして」と言われた。
「育児休業は整っていても、介護休業は形だけで実際には取りづらい」
このような声は、介護者にとって大きなストレスになります。
とくに管理職や責任ある立場にある人ほど、「自分が休んだら迷惑がかかる」と感じてしまい、
誰にも相談できないまま一人で抱え込み、最終的に退職に至るケースもあります。
誰もが明日は“介護当事者”になるかもしれない
いま介護をしていない人もいつか親や配偶者が介護を必要とする日はやってくるかもしれません。
そのときに、会社に制度がなかったり、家族の理解がなかったりしたら、
選択肢は限られてしまいます。
介護離職を「誰かの問題」ではなく、「自分ごと」として捉えることが今後の対策において
とても重要なのです。
介護離職を防ぐために使える制度
介護と仕事を両立するために、国が用意している制度もいくつかあります。
でも、実際には「知らなかった」「使いにくかった」という声も多いのが現状です。
⚫︎介護休業制度:対象家族1人につき、通算93日まで休業が可能
⚫︎介護休暇:1年に5日(対象家族が2人以上なら10日)まで取得可能
⚫︎短時間勤務制度:労働時間の短縮・フレックス制などでの勤務調整
ただし、これらの制度は「職場の理解」「雰囲気」があってこそ活用できるものであり、
形だけで終わらせない“使いやすさ”が求められています。
[PR]地域や民間のサポートを頼る
公的なサービスに加え、地域包括支援センターやNPO法人などが行っている
家族向けのサポートも活用しましょう。
例えば、
・ケアマネジャーによるプラン作成・相談
・訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービス
・家族会(介護経験者同士の交流の場)
「頼るのは申し訳ない」と思いがちですが、介護は一人で抱えるものではありません。
周りに助けてもらいながら、長く続けられる体制を整えることが、何より大切です。
企業や社会の取り組みもカギ
近年では、介護と仕事の両立支援に取り組む企業も増えてきました。
例えば、
・介護相談窓口の設置
・在宅勤務・テレワークの導入
・管理職向けの介護理解研修
こうした取り組みは、従業員の離職を防ぐだけでなく、
企業の生産性や信頼性の向上にもつながります。
社会全体が「働きながら介護すること」を前提とした制度設計を進めていくことが、
この問題の解決への近道になるのかもしれません。
[PR]最後に
介護は誰にとっても突然やってくる可能性があります。
だからこそ、今から備えることが大切です。
・職場の制度は整っているか?
・家族で介護について話し合っているか?
・いざというとき、どこに相談できるか知っているか?
そうした小さな“準備”が、大きな安心に変わります。
大切なのは、あなた自身の人生も大事にすること。
介護を理由に、自分を犠牲にしすぎないでいいように。
介護離職が“選ばなくて済む選択肢”となるように。
今日からできる一歩を、私たち一人ひとりが踏み出していけるといいですね。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 厚生労働省「介護離職に関する実態調査(令和4年度)」
- 総務省統計局「就業構造基本調査」より、介護離職者の割合
- 内閣府「仕事と介護の両立支援に関する政策パッケージ」
- 日本ケアラー連盟「家族介護者の支援と離職防止に関する提言」
- 厚生労働省「介護休業制度の概要」





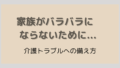

コメント