こんにちは。
「学校よりも、家のことが優先だった」
「友達と遊ぶ時間がなかった」
「“普通の子ども”になりたかった」——。
これは、10代で親の介護を担っていた“ヤングケアラー”と呼ばれる若者たちの、切実な声です。
「介護」という言葉から、私たちは高齢の親を支える50代〜60代を想像しがちですが、
実はその影には、
“子ども”でありながら、日常的に家族の世話や介護を担っている若者たちがいます。
今回は、そんなヤングケアラーの現実に焦点を当て、その苦しみや葛藤、
そして社会に求められる支援について一緒に考えていきたいと思います。
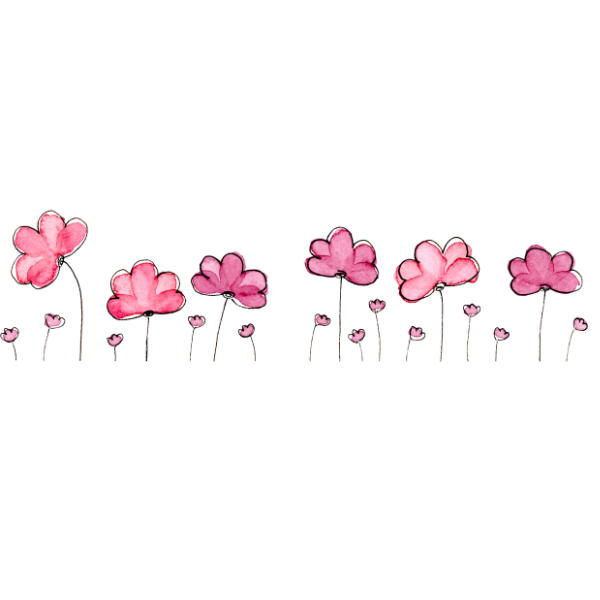
ヤングケアラーとは?
ヤングケアラーとは、
18歳未満で、日常的に家族の介護や世話をしている子どもたちのことを指します。
例えば、認知症の母親に代わって食事の準備をしたり、体の不自由な父親の排泄介助をしたり、
兄弟姉妹の面倒を見たりといったことです。
一見、「お手伝い」の範囲に見えるかもしれませんが、毎日の生活を回すために
“子どもであること”を後回しにせざるを得ない状況は、決して見過ごせるものではありません。
10代で背負う介護の現実
ある高校生の男の子は、母親が難病を患ったことをきっかけに、
家事全般と母親の介助を一人で担うようになりました。
朝5時に起きて母の身支度を整え、学校に行き、
帰宅後は買い物・夕食の支度・入浴介助・就寝介助。
「疲れた」とつぶやく時間もなく、学校の宿題は深夜にこなし、いつも睡眠不足。
でも「自分がやらなきゃ」という思いで頑張っている ——
そんな生活を続けている子どもが、今の日本には少なくありません。

文部科学省の調査結果から見る実態
2020年度に文部科学省が実施した全国調査では、中学生のおよそ17人に1人、
高校生のおよそ24人に1人が「ヤングケアラー」の可能性があるとされています。
中には、家族に障害や病気を抱える親がいるだけでなく、精神疾患を持つ親のサポートや、
アルコール依存症の父親に代わって家計を支えるケースもあります。
「まだ小学生なのに、毎日洗濯と夕飯の支度をしていた」
「友達には恥ずかしくて言えなかった」
——そんな声が、日本中から寄せられているのです。
見えにくい存在、気づかれにくい苦しみ
ヤングケアラーの問題が社会に出てきたのは、ここ数年のことです。
以前は「家庭の事情」「親孝行」とされ、問題視されることがありませんでした。
しかし、子どもが大人の役割を果たすことで、学校生活・友人関係・進路選択・精神的健康など、
多くの場面で影響が出てきます。
とくに10代という時期は、心も体も成長していく大切な時期。
そこで家庭の事情によって子どもらしい時間を過ごせないことは、
その後の人生にも大きな影響を及ぼしかねません。

ヤングケアラーたちのリアルな声
実際にヤングケアラーとして生活している10代の声を見ていくと、彼らが感じている葛藤や孤独、
そして苦悩が浮き彫りになります。
「家では家族の世話、学校では勉強。でも誰にも相談できなかった」
「学校の先生に話しても、『えらいね』で終わってしまった」
「本当は進学したかったけど、お金も時間もなくて就職を選んだ」
それぞれの家庭には事情があり、必ずしも“悪者”がいるわけではありません。
しかし、「助けを求める場所がない」という現実に直面している子どもたちにとって、
日々はとても過酷なものです。
心の中に広がる“罪悪感”と“あきらめ”
ヤングケアラーの多くが口をそろえるのは、「誰にも迷惑をかけたくない」という思いです。
「友達に遊びに誘われても、断るのがつらかった」
「でも母を置いて遊びに行くことが悪いことのよう思えて…」
その裏には、“親を置いて楽しんではいけない”という無意識の罪悪感があります。
このような気持ちは、やがて「自分のやりたいことは我慢しなきゃ」という
“あきらめ”へと変わり、進学や将来の夢を断念してしまう子も少なくありません。
「進路選択」にも大きな影響
ヤングケアラーの進路に関する悩みは深刻です。
「大学に行きたかったけど、家を離れられないからあきらめた」
「夜間の看護学校に通いながら介護を続けている」
「アルバイトと家事・介護を両立させながら通信制高校に通っている」
本来であれば、自分の可能性を広げる時期に、
「親の世話があるから」
「家を空けられないから」と進路を制限してしまう現実があります。
これは、本人の将来にも、そして社会全体にとっても大きな損失です。
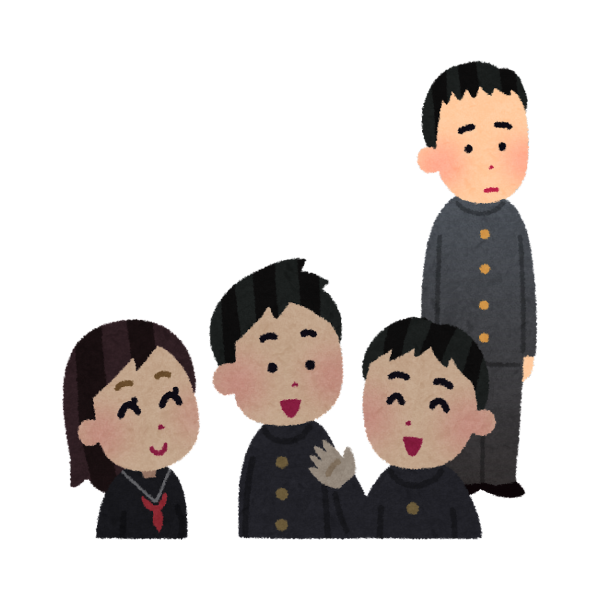
まわりの無理解が追い打ちに
さらに辛いのは、「まわりに理解してもらえないこと」です。
「介護してる」と言っても、
「子どもが?本当に?」
「それって家の問題でしょ?」
といった反応をさてしまうことが多く、孤立感を深めてしまうことがあります。
学校や地域で支援の体制が整っていないと、ヤングケアラーはどこにも頼れず、
自分を責め続けることなります。
彼らが必要としているのは、“正解”ではなく、“理解”と“共感”、
そして“そっと手を差し伸べてくれる大人の存在”です。
心の声に耳を傾けることから始めよう
「どうしても言えなかったけど、誰かにわかってほしかった」
「ひとこと、『大変だったね』って言ってもらえるだけで救われる」
こんな言葉を聞くと、私たち大人ができることは何か、と改めて考えさせられます。
まずは、“ヤングケアラー”という言葉に目を向け、知ること。
そして、「一人で頑張らなくていいんだよ」と伝えてあげられる環境づくりが、
何よりも大切なのではないでしょうか。
ヤングケアラーへの支援制度、始まったばかりの一歩
文部科学省や厚生労働省が、学校や地域での支援体制づくりに着手し始め、
自治体によっては専用の相窓口やスクールソーシャルワーカーの配置も始まったのは、
ほんのここ数年前のことです。
たとえば、東京都ではヤングケアラー支援を明確に打ち出し、
教育委員会と福祉部門が連携して学校で早期発見に取り組んでいます。
また、2023年には「こども家庭庁」も創設され、包括的な子ども支援が強化されつつあります。

学校や地域ができること
学校が果たす役割は非常に大きいです。
先生や保健室の先生、カウンセラーが「何かおかしい」と感じたときに、
適切な対応や支援先へつなぐ体制が整えば、多くの子どもを救うことができます。
地域においても、民生委員や地域包括支援センターが子どもたちの声に耳を傾け、
必要な支援につなげる仕組みが必要です。
一人の大人が気づくことから、支援の輪が広がっていきます。
社会が抱える“見えない負担”を減らすには
ヤングケアラーの問題は単なる個人や家庭の問題ではなく、社会全体が抱える構造的な課題です。
介護を受ける人が、家族に頼らずに暮らせる仕組みや、
サービスの利用ハードルを下げる制度改革も求められています。
「親を施設に入れるのはかわいそう」
「家族のことは家族で」
そんな“無言のプレッシャー”が、子どもたちを沈黙させている側面もあります。
だからこそ、地域の支援、制度の見直し、
そして何より「声をあげていいんだよ」という空気を作ることが何より大切です。
今、大人としてできること
私たちにできることは、たくさんあります。
・子供たちが「相談していい」と思えるような雰囲気を作ること
・学校や地域でヤングケアラーに関する研修や勉強会を開くこと
・「家庭の事情」として片付けず、その子の背景を見ようとすること
たった一人の大人の“気づき”や“言葉”が、子どもの未来を変えることもあるのです。

最後に:「がんばってるね」その言葉を届けたい
ヤングケアラーの子どもたちは、日々誰にも言えない孤独と責任の中で生きています。
でも本当は、「助けて」と言いたいはずです。
我慢して一人で戦う必要なんてないんです。
もしまわりに、何かを抱えている様子の子どもがいたら——
「よくがんばっているね」「一緒に考えようか」
と大人の誰もが声をかけてあげられる社会になってほしいと思います。
そんな“救い”のある社会になってほしいと思います。
そんな子供達に未来のある社会をみんなで作っていけたらと願っています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
参考
- 文部科学省「ヤングケアラーに関する実態調査報告書(令和3年)」
- 厚生労働省「ヤングケアラー支援の手引き」
- 国立生育医療研究センター「こどもケアラー支援に関する提言書」
- 埼玉県「ヤングケアラー実態調査報告書」




コメント