こんにちは。
地震や台風、大雨など…日本ではいつどこで災害が起きてもおかしくありません。
ニュースを見て「うちも何か備えなきゃ」と思っても、
なかなか行動に移せない方も多いのではないでしょうか。
特に高齢のご家族と暮らしている場合、災害時の対応は一層むずかしくなります。
避難所までの移動、薬の管理、トイレや食事の準備など、
想定しておくべきことは山ほどありますよね。
そこで今回は、「高齢者とその家族に必要な防災対策」をテーマに、
今すぐできる3つの備えをご紹介します。
特別な道具がなくても始められる、現実的でやさしい対策ばかりです。
「もしもの時」に慌てないために、少しずつ準備を進めていきましょう。
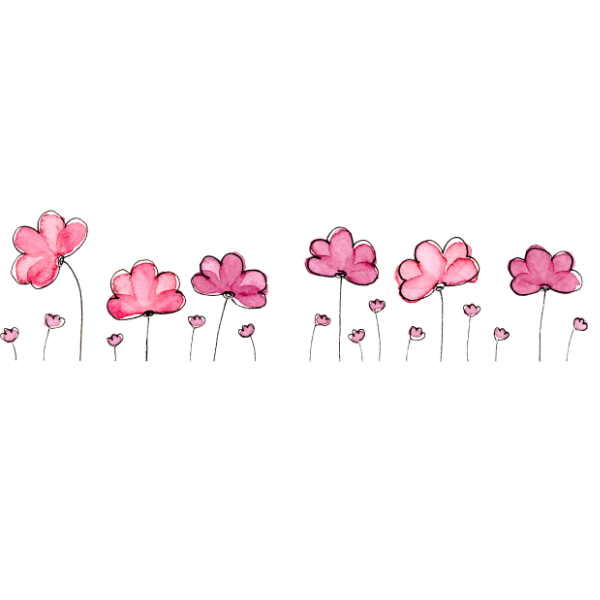
なぜ高齢者ほど防災対策が必要なの?
まず知っておきたいのは、災害時に「高齢者ほど危険にさらされやすい」という現実です。
その理由はいくつかあります。
ひとつは体力や行動力の低下です。
地震や火災などの緊急時は、すぐに身を守る行動が求められますが、反応が遅れたり、
移動が難しかったりすることで、逃げ遅れのリスクが高まります。
また、視力や聴力の低下も危険を増やす要因です。
警報音や避難情報が聞き取りづらかったり、暗闇で足元が見えにくくなったりすることで、
ケガのリスクも高まります。
さらに忘れてはいけないのが、持病や服薬管理の問題。
「いつもの薬がない」「血圧計が使えない」「通院できない」──
そんな状況が続くと、命に関わることもあります。
つまり、高齢者の防災とは「避難」だけでなく、
「災害後の生活をどう支えるか」まで考える必要があるんです。
家族が一緒に住んでいる場合はもちろん、離れて暮らしている場合も、
連絡方法や避難先を決めておくことで安心感がぐっと高まります。
防災対策① 家の中を「安全ゾーン」に整える
まず最初のステップは、避難グッズを買う前に「家の安全性を高めること」です。
地震が起きたとき、家具の転倒やガラスの破損でケガをしてしまうケースはとても多いんです。
特に高齢の方は、とっさに避けることが難しいため、
まずは「家の中でケガをしない仕組み」を作りましょう。
たとえば次のような工夫があります。
・背の高い家具には転倒防止金具をつける
・寝室の近くには重い家具を置かない
・ガラスには飛散防止フィルムを貼る
・懐中電灯をベッドの横に置いておく
ちょっとした工夫ですが、これだけでも災害時のケガを防げる確率はぐんと上がります。
また、寝室を「安全ゾーン」にするのもおすすめ。
夜中に災害が起きると、慌てて転倒してしまうケースが多いからです。
家具を少なくし、足元に何も置かない空間を作っておくと安心です。
「どこから始めたらいいかわからない…」という方は、
まずは家族で一緒に部屋を点検してみましょう。
一緒にやることで、「ここ危ないね」「これは対策できそう」と
話し合えるきっかけにもなります。
[PR]防災対策② 命を守る“持ち出し袋”を家族仕様にする
災害が起きたとき、避難先での生活を支えるのが「持ち出し袋」です。
テレビなどでもよく耳にしますが、実際に中身を準備しているご家庭はまだ少ないのが現状です。
でも、持ち出し袋は“家族の命を守るための第一歩”。
とくに高齢者がいる家庭では、一般的な防災グッズだけでなく、
その方の生活に合わせた中身が必要です。
たとえば、こんなものを入れておくと安心です。
・普段飲んでいる薬(最低3日分)とお薬手帳のコピー
・入れ歯ケースや清潔な歯ブラシ
・眼鏡、補聴器、杖などの予備品
・小さな懐中電灯と乾電池
・水(500mlを数本)と食べやすい非常食(ゼリー飲料、ビスケットなど)
・ウェットティッシュ、簡易トイレ、タオル
・家族やかかりつけ医の連絡先を書いたメモ
特に大切なのは「その人に合わせる」という視点です。
たとえば糖尿病や高血圧などの持病がある場合は、医療機関名や薬の種類をメモしておくと、
避難先での対応がスムーズになります。
また、持ち出し袋は1人1つが理想です。
ただし、高齢の方が重たい荷物を持つのは大変なので、家族で分担するのもおすすめです。
「お薬と連絡帳はお母さん」「水と非常食は息子さん」など、
役割を決めておくと慌てずに動けます。
持ち出し袋は一度作って終わりではなく、定期的に見直すことが大切です。
賞味期限や薬の内容が変わったり、季節によって必要なものが違ったりします。
たとえば夏なら熱中症対策グッズ、冬ならカイロなどを入れ替えましょう。
もし「準備する時間がない…」という方は、まずは100円ショップから始めてみてください。
懐中電灯、タオル、ラップ、ジップ袋など、身近なアイテムでも十分に役立ちます。
完璧じゃなくても、「ある程度でも備える」ことが大事です。
防災は“続けること”がいちばんの安心につながります。

防災対策③ 災害時の「連絡・支援ネットワーク」を作る
3つ目の防災対策は、「人とのつながり」を備えておくことです。
どんなに準備をしていても、災害時は一人では限界があります。
助け合える関係を普段から作っておくことが、命を守る大きなカギになります。
たとえば、こんな人たちとの連絡手段を整理しておくと安心です。
・離れて暮らす家族
・近所の人(できれば数軒)
・介護サービスの担当者(ケアマネジャー、ヘルパーなど)
・かかりつけ病院や薬局
・地域包括支援センター
特に高齢者が一人暮らしの場合は、「見守ってくれる人」を複数確保しておくことが重要です。
「もし地震があったら声をかけ合おうね」と、近所の方と軽く話しておくだけでも
安心感が違います。
また、携帯電話やスマホが使えないときのために、
安否確認のルールを決めておくのもおすすめです。
たとえば、「災害のときは○○公園に集合」
「連絡が取れなければ、親戚の△△さんに電話する」など。
紙に書いて冷蔵庫など目立つ場所に貼っておくと、誰でもすぐ確認できます。
最近では自治体や地域包括支援センターが、
高齢者向けの防災支援マップを作成していることもあります。
どんなサポートが受けられるのか、一度チェックしておくと良いですよ。
また、災害時に介護が必要な方がいる場合は、
「要配慮者避難支援制度」という仕組みも覚えておきましょう。
これは、市区町村が高齢者や障がいのある方など、避難に支援が必要な人を登録・把握し、
いざという時に地域の支援者と連携して避難を助ける制度です。
自治体によって内容は異なりますが、
ケアマネジャーや民生委員を通じて登録できる場合もあります。
登録しておけば、「いざという時に誰が助けに来てくれるのか」が明確になるため、
ご本人もご家族も安心です。
気になる方は、お住まいの市区町村の防災担当窓口に相談してみてください。
災害時の「心の備え」も忘れずに
ここまで物理的な備えについてお話してきましたが、実はもうひとつ大切なのが
「心の備え」です。
災害は、誰にとっても強いストレスをもたらします。
特に高齢者は、環境の変化に弱く、不安や混乱から体調を崩してしまうこともあります。
そんなとき、家族の「声かけ」や「寄り添い」が何よりの支えになります。
「大丈夫だよ」「一緒にいるからね」と、たった一言かけるだけでも安心につながります。
避難所などで落ち着かない時間を過ごすときこそ、会話を増やすことを意識してみてください。
また、介護が必要な方の中には、避難先で普段通りの介護ができないことで
家族が罪悪感を感じるケースもあります。
でも、「できる範囲で十分」です。
無理をして倒れてしまっては、支える人も支えられる人もどちらも苦しくなってしまいます。
そんな時こそ、「助けてもらう勇気」も大切にしてくださいね。
[PR]最後に
ここまで、「高齢者とその家族に必要な災害時の備え」として、
3つの防災対策をご紹介しました。
どれも特別なことではなく、日常生活の延長でできることばかりです。
「週末に家具を見直そうかな」「今度スーパーに行ったら非常食も見てみよう」──
そんな小さな行動の積み重ねが、いざという時に家族を守ります。
防災は、一度やって終わりではありません。
季節や家族の状況によって必要な備えは変わっていくものです。
思い立った時に少しずつアップデートしていきましょう。
“今できること”をひとつずつ積み重ねていけば、きっと安心につながります。
家族みんなで「もしもの時」を想像しながら、
笑顔で乗り越えられる準備をしていけたらいいですね。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み」内閣府
- 「避難体制の整備、避難行動要支援者対策」消防庁
- 「シニア女性の出番です!防災塾」横浜市
- 「災害対策・対応におけるNPOの役割」防災危機管理研究所

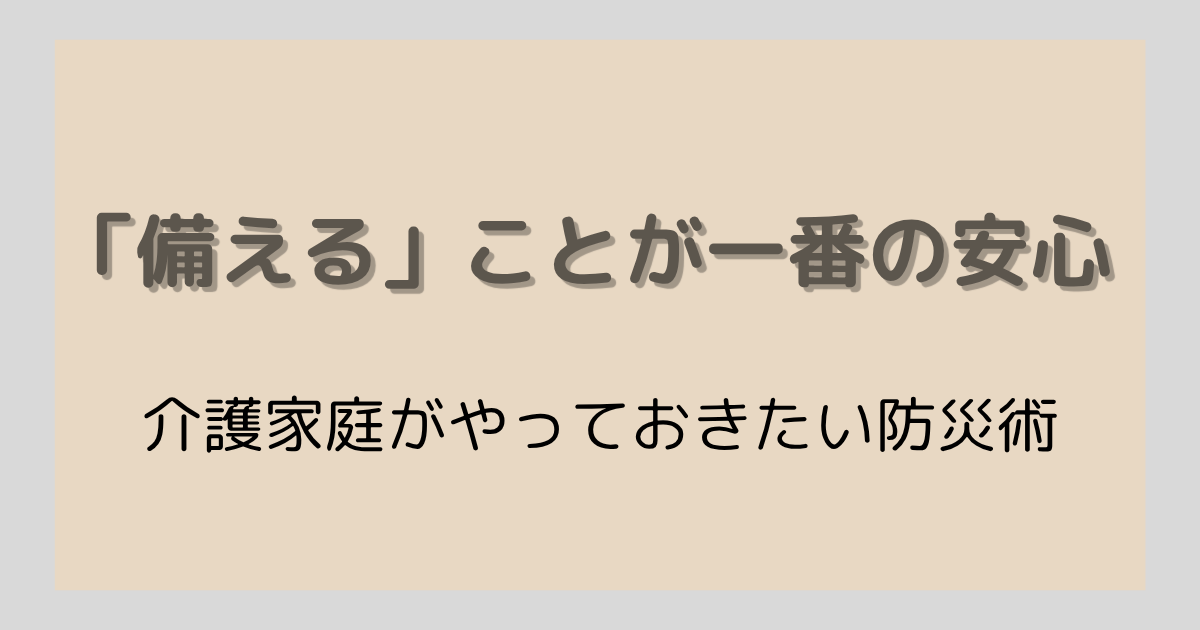
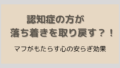
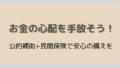

コメント