こんにちは。
「最近、うちの親があまり食べなくなってきて…」「体重がどんどん減ってきて心配」―
高齢の親を介護していると、こんな悩みに直面することがあると思います。
年齢を重ねると、食欲が落ちるのは自然なこと。
ですが、食べる量が減ると、体力や免疫力の低下につながり、
転倒や病気のリスクが高まってしまいます。
「何とかして食べてもらいたい」「でも無理強いはしたくない」―
そんな家族の気持ちに寄り添いながら、やさしく栄養を補う工夫をご紹介していきます。
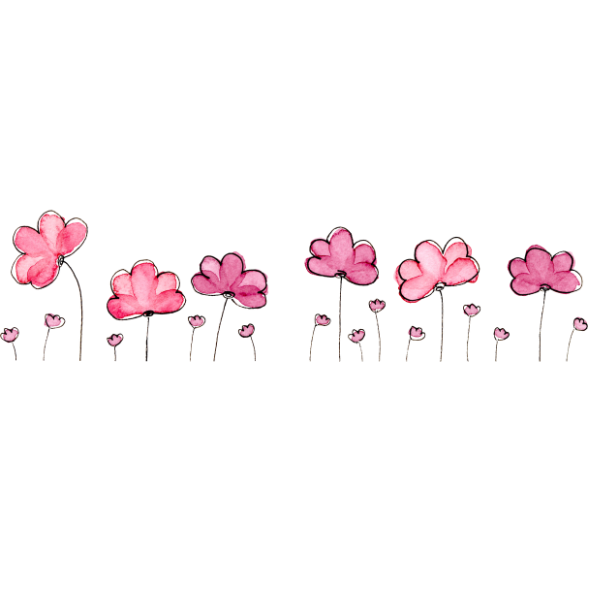
食欲が落ちる理由を理解しよう
まずは、なぜ高齢になると「食が細くなる」のか、その原因を知ることがとても大切です。
原因はひとつではなく、複数の要素が重なっていることがほとんどです。
味覚や嗅覚の変化
加齢とともに味や香りを感じにくくなるため、「おいしい」と感じにくくなります。
その結果、食事への興味が薄れてしまうことがあります。
噛む力・飲み込む力の低下
歯や義歯の不具合、口腔乾燥症、嚥下機能の衰えなどによって、
食事が「しんどいもの」になってしまうことも。
胃腸の機能低下
消化・吸収の機能が弱まり、少し食べただけで
「お腹いっぱい」「胃もたれする」と感じやすくなります。
精神的な要因
独居や配偶者の死、認知症の影響などで、
食事そのものに対する意欲が落ちている場合もあります。
こうした背景を理解すると、「どうして食べてくれないの?」ではなく、
「食べづらい理由があるのかも」と、見え方が変わってきます。
無理に食べさせない。気持ちに寄り添う第一歩
家族としては「もっと食べて」「せめてこれだけでも」とつい言いたくなりますが、
無理やり食べさせることは逆効果になることも。
本人にとって、食事が「苦痛」や「プレッシャー」になってしまうと、
ますます食べたくなくなってしまいます。
まずは「食べたくない理由」や「最近の体調」をやさしく聞き取ってみましょう。
「最近味が分からなくなってきたんだよね」「噛むと疲れるんだよ」など、
思わぬヒントが隠れているかもしれません。
本人の気持ちや体の変化に寄り添いながら、
次のような工夫を少しずつ取り入れていくのがおすすめです。
[PR]栄養を補うための5つの工夫とは?
ここからは、具体的に「食が細くなった親にどんな工夫をすれば栄養を摂れるのか」について、
5つの工夫を紹介していきます。
どれも無理なく取り入れられるものばかりなので、
家庭の状況や本人の好みに合わせて、組み合わせてみてくださいね。
工夫 ①:少量でも高カロリー・高栄養の食材を選ぶ
たくさん食べられないなら、「少量でしっかり栄養が摂れる食材」に切り替えてみましょう。
たとえば…
・卵(タンパク質・ビタミン豊富)
・チーズ(カルシウム・脂質)
・アボカド(良質な脂肪分)
・ヨーグルト(消化が良く、栄養価も高い)
・バナナ(エネルギー補給・食べやすさ◎)
「栄養ドリンクや補助食品」も選択肢のひとつですが、
普段の食事の中で工夫する方が自然に続けやすいです。
工夫 ②:食べる時間やスタイルを変えてみる
「一日3食しっかり食べる」のが当たり前と思われがちですが、
高齢者にとってはそのリズムが合わなくなることもあります。
たとえば…
・朝は食欲が出ない → 朝食をスキップして、10時頃に軽食を
・1回の量が多すぎる → 少量を5〜6回に分けて摂る「分食スタイル」に
・一人だと食べる気がしない → 一緒に食べる機会を作ってみる
「時間」「量」「雰囲気」を変えるだけで、驚くほど食が進むことがあります。
無理に「三食きっちり」にこだわらず、
その人に合った“食べ方の自由”を大切にしてみましょう。
工夫 ③:味つけと見た目を見直す
高齢になると味覚が鈍くなり、「何を食べてもおいしく感じない」と言う人も増えてきます。
そこでポイントになるのが、味つけ・香り・彩りです。
おすすめの工夫:
・だしを効かせる:塩分控えめでも旨味で満足感アップ
・香りを添える:生姜、しそ、ゆず、カレー粉など
・色味をプラス:にんじん、ブロッコリー、パプリカなど鮮やかな食材を使う
視覚・嗅覚・味覚の三方向から「食べたい!」を引き出すのがコツです。
盛り付けを変えるだけでも「あれ?今日はちょっと美味しそうかも」
と反応が変わることがありますよ。
工夫 ④:やわらかく、食べやすい形にする
食が細くなる背景には、「噛みにくい」「飲み込みにくい」といった
口の機能低下も関わっています。
たとえ食欲があっても、うまく噛めない・飲み込めないことで、
食事そのものが苦痛になっている可能性があります。
こんな工夫が役立ちます:
・やわらか食:煮物や蒸し料理、豆腐や卵料理など、口あたりがやさしいもの
・とろみづけ:汁物やおかずにとろみを加えると、飲み込みやすくなる
・一口サイズにカット:食べやすくするだけで、ぐっと負担が減る
「きざみ食=良い」とは限らず、本人の嚥下状態に合った形状を見極めることが大切です。
介護食専用のレトルトや冷凍食品も、最近はとてもおいしくなっています。
上手に取り入れて、本人の「食べやすさ」と「楽しさ」の両立を目指しましょう。
工夫 ⑤:飲み物から栄養をとる
食事として固形物を食べるのが難しい場合は、飲み物から栄養を補うという発想もおすすめです。
具体的には…
・スムージーやシェイク:バナナ+牛乳+きな粉など、カロリーと栄養がしっかり取れる
・具だくさんスープ:ポタージュやシチューなど、飲みやすくて満足感のあるもの
・栄養補助飲料:病院や薬局でも扱っているドリンクタイプの栄養補助食品
飲みやすい温度や好みの味に調整しながら、
「食べるのは無理でも、飲むならOK」という切り口で栄養を摂っていきましょう。
食べることへのハードルを下げる工夫は、
こういった“飲み物の工夫”から始めるのも立派な一歩です。
工夫を「続ける」ために家族が意識したいこと
せっかく工夫をしても、すぐには効果が出ないこともあります。
本人の気分や体調によって、日によって食べられたり食べられなかったり…。
そんなとき、家族が疲れ果ててしまわないようにすることも大切です。
以下のポイントを意識してみてください:
・完食にこだわらない:「食べられた」ことを評価する
・日によって内容をゆるく調整:「今日はゼリーだけでもOK」など柔軟に
・「一緒に食べる時間」を楽しむ:会話や笑顔も食欲アップのスパイス
食事の場を“栄養補給のための作業”ではなく、
“楽しい時間”にすることが、自然と食欲につながることもあります。
[PR]それでも食べない時…「医療」との連携も視野に
どんな工夫をしても、「やっぱり食べない」「どんどんやせてきた」「飲み込みが心配」
というときは、医師や栄養士、訪問看護師に相談することが重要です。
医療の視点が入ることで:
・隠れた疾患(胃腸の病気、口腔の問題など)の早期発見
・嚥下機能の検査や、適切な食事形態の提案
・栄養補助食品や薬の提案(食欲増進剤など)
また、地域包括支援センターでは、管理栄養士による栄養相談を受けられる自治体もあります。
「もう少し様子を見よう」と抱え込まずに、“困ったら相談”を合言葉にしてみてくださいね。
家族の「がんばりすぎ」に気づいて
「食べさせなきゃ」「元気にさせなきゃ」と一生懸命になるあまり、
気づけば家族自身が疲弊してしまっていることもあります。
大切なのは、“がんばりすぎないこと”。
食が細くなるのは、老いの自然な流れである場合もあります。
それを無理に変えようとせず、
「その人のペースに合わせて、できることを少しずつ」と考えることが、
家族にとっても親にとってもやさしい姿勢です。
[PR]最後に
高齢の親の「食べなくなった」という変化に、最初は戸惑ったり、不安になったりしますよね。
でも、大切なのは“どうやって食べさせるか”より、“どう寄り添うか”。
今回ご紹介した5つの工夫は、
すべて「無理なく、やさしく、自然に」取り入れられるものばかりです。
家族のあたたかな気持ちと、ちょっとした工夫が、食卓に小さな変化をもたらします。
そして何より、がんばりすぎずに、自分の心も大切にしながら続けて下さいね。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 厚生労働省「高齢者の食事と栄養管理について」
- 厚生労働省「高齢者の栄養改善に関する調査結果」
- 農林水産省「食事バランスガイド」
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会「食事形態の分類と基準」

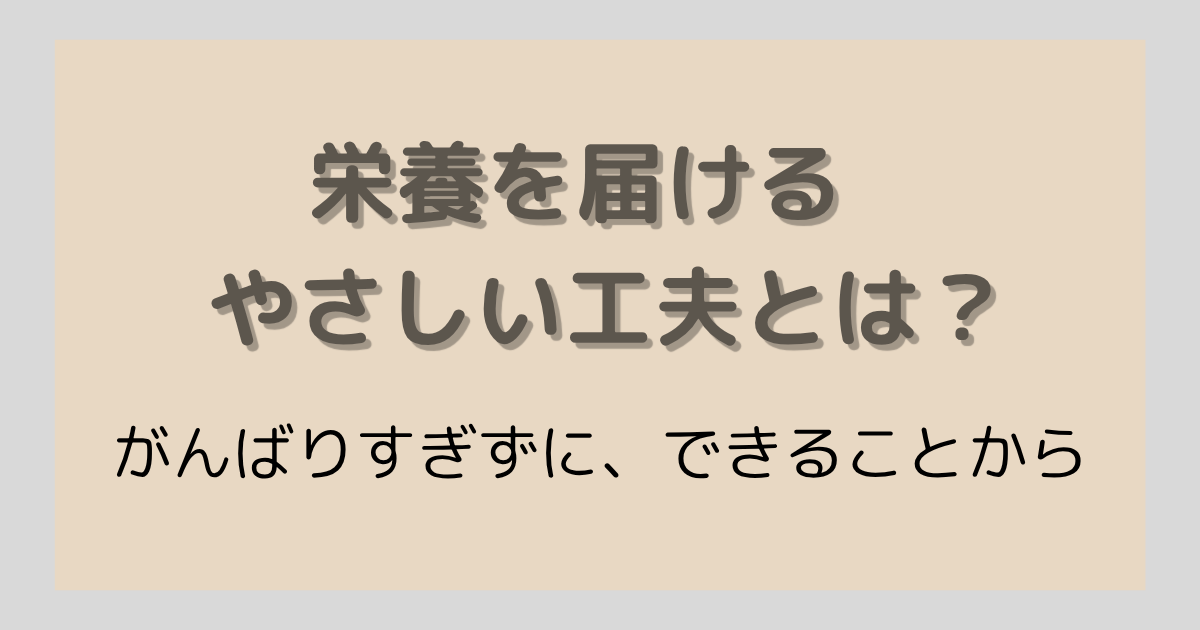
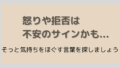
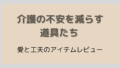

コメント