こんにちは。
「親が認知症になったから、私もきっとそうなるのでは…」と心配になる方は少なくありません。
でも、医学的に見て“認知症=必ず遺伝する”わけではありません。
むしろ多くのケースでは、生活習慣や環境、年齢といった要因が大きく関わっています。
今回は、認知症と遺伝の関係について分かりやすく解説し、
読者の方が安心して未来を考えられるようにお手伝いします。
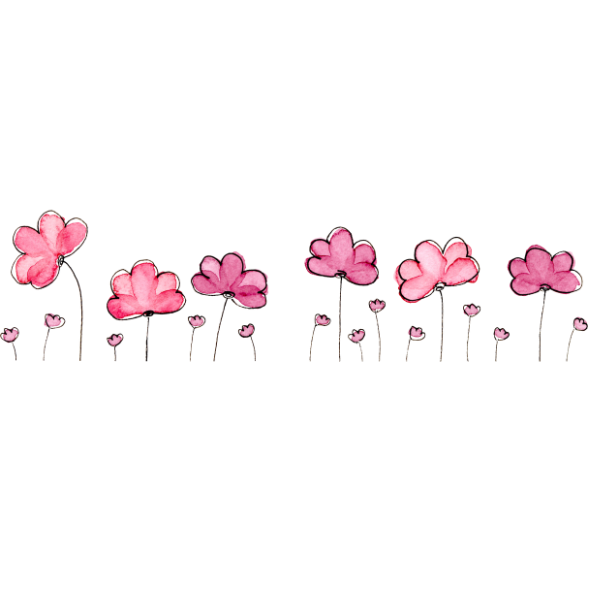
認知症と「遺伝」の関係を整理してみよう
「親が認知症だから自分も必ずなる」とは限りません。
認知症の大部分は、
年齢を重ねることや生活習慣病、血管の状態などによってリスクが高まります。
もちろん遺伝が関係するタイプもありますが、それは全体のごく一部。
むしろ「生活習慣や環境を整えることで防げる部分」がとても大きいのです。
たとえば、親から体質を受け継いで「高血圧になりやすい」「糖尿病になりやすい」という傾向が
ある場合、その体質が血管や脳に影響し、結果的に認知症リスクを高めることはあります。
でも、それは“体質がそのまま認知症に直結する”というより、
“体質+生活習慣の組み合わせ”によるものなのです。
[PR]認知症の主な種類と遺伝との関わり
アルツハイマー型認知症
最も多いタイプです。
ごくまれに「家族性アルツハイマー型」といって、
遺伝子の変化が原因で若い年齢から発症するケースもありますが、全体の1%未満。
ほとんどのアルツハイマー型は、加齢や生活習慣などの影響によって発症します。
つまり「親がそうだったから自分も必ず」という心配は必要ありません。
血管性認知症
脳梗塞や脳出血のあとに起きるタイプです。
これは「遺伝病」というより「生活習慣病の影響」が大きい認知症。
高血圧や糖尿病、喫煙、食生活の偏りが積み重なることで、
脳の血管がダメージを受けて発症します。
親子で似た習慣を持ちやすいので“遺伝する”ように見えるのです。
レビー小体型認知症
幻視や体の動きの変化が特徴的なタイプです。
家族性が報告されることもありますが、全体の中では少数派。
多くは偶発的に起きるもので、必ず遺伝するとはいえません。
前頭側頭型認知症
比較的若い世代でも発症することがあり、家族内で複数人が発症するケースが知られています。
ただし、これも全体で見るとごくわずか。
ほとんどの人にとっては「特別に強い遺伝性」は心配しなくて大丈夫です。
「親が認知症=自分も」という不安の正体
なぜ「遺伝がこわい」と感じるのでしょうか。
多くの場合、その裏には
「将来、子どもや家族に迷惑をかけたくない」という思いがあります。
これはとても自然な気持ちです。
だからこそ、「私もきっとそうなる」と決めつけるより、
「できる準備を今からしておこう」と考えることが、心の安心につながります。
準備といっても大がかりなことではありません。
たとえば「健康診断を受けておこう」「血圧や体重をメモしてみよう」
「生活リズムを少し整えよう」。
小さな積み重ねこそが、未来を変える力になります。
[PR]認知症は遺伝する?生活習慣から考える予防のヒント
気になるのは「じゃあ自分や家族は、何を心がければ予防につながるの?」
ということだと思います。
認知症の研究は日々進んでいますが、今のところ、
「これをすれば絶対に認知症にならない」という方法はありません。
でも、「発症のリスクを下げる」「進行をゆるやかにする」ことができる生活習慣は
たくさん見つかっているんです。
ここからは、今日からでも取り入れられる工夫を一緒に見ていきましょう。
食事でできる予防の工夫
食事は体だけでなく、脳の健康にも直結しています。
最近では「MIND食」と呼ばれる食事スタイルが注目されています。
MIND食は地中海食とDASH食(高血圧予防食)を合わせたもので、
認知症予防のために考えられた食事法です。
ポイントはとてもシンプルです。
・野菜、とくに緑黄色野菜をしっかり食べること。
・魚や鶏肉、大豆製品など良質なたんぱく質をとること。
・オリーブオイルやナッツなど、体に良い脂を適度にとること。
・逆に、赤身の肉や加工食品、バターや揚げ物などの摂りすぎは控えめに。
難しく考えず「彩りのある食卓を心がける」「毎日の味噌汁に野菜をちょっと足す」だけでも
立派な一歩。
おいしく食べながら脳の健康を守れるなら、一石二鳥ですよね。
運動は「無理なく続ける」がカギ
「運動不足は認知症のリスクを上げる」と聞いたことがある方も多いと思います。
でも「運動」と聞くと「ジムに通わなきゃいけないの?」「毎日ジョギングなんて無理!」
と身構えてしまうかもしれません。
実際には、特別な運動じゃなくても大丈夫なんです。
たとえば毎日の買い物を歩いて行く。階段を使う。軽いストレッチをする。
こうした小さな積み重ねが、脳への血流を良くしてくれるんです。
「運動=汗だくになるまで頑張ること」ではなく、
「体を動かすことを生活にちょっと足す」くらいの気持ちで。
無理せず続けられる方が、よほど大きな効果につながります。
質のいい睡眠で脳をリセット
認知症予防において、睡眠の質もとても大切です。
脳は眠っている間に不要な老廃物を掃除するのですが、
睡眠が不足するとその働きが十分に行われません。
「なかなか眠れない」という方は、寝る前のスマホやテレビを控える、
夕方以降のカフェインを避ける、寝室の明かりを落とすなど、環境を整えるだけでも変わります。
また、日中に軽く体を動かすことも夜の眠りを助けてくれます。
人とのつながりが脳を元気にする
認知症の予防で意外と大きなポイントになるのが「社会とのつながり」です。
会話や交流は、脳にとってとても良い刺激になるんですね。
友達とおしゃべりする。地域のサークルに参加する。孫と遊ぶ。
どれも立派な「脳トレ」なんです。
一人で過ごす時間ももちろん大切ですが、
人との関わりがあるだけで心も脳もずっと元気でいられます。
小さな習慣が未来を変える
食事、運動、睡眠、人とのつながり。
こうした日常のちょっとした習慣が、将来の認知症リスクに大きく関わってきます。
「全部やらなきゃ」と気負わなくても大丈夫です。
できそうなことから一つずつ始めてみましょう。
家族との向き合い方
家族の言動が「最近ちょっと変かも」と気になることはありませんか?
認知症かもしれないと感じたとき、本人や家族にどう伝えるかはとても難しいですよね。
「病気なんじゃないの?」と直球で言われると、
本人は傷ついたり否定したりしてしまうこともあります。
そんなときは、「最近ちょっと疲れてるみたいだから、一度お医者さんに見てもらおうか」など、
やわらかい言葉で伝えるのがコツです。
また、受診を「親のため」ではなく「家族みんなの安心のため」と伝えると、
納得してもらいやすくなります。
介護が始まると、どうしても家族が一人で抱え込んでしまう場面が出てきます。
でも、認知症ケアにおいて大事なのは「一人で頑張りすぎないこと」。
認知症は一人で抱え込むものではありません。
家族で話し合い、地域のサービスを活用して、無理のない形で続けることが大切です。
[PR]最後に
認知症は「必ず遺伝するもの」ではありません。
確かに一部のタイプでは遺伝の影響が大きいものもありますが、
大部分は生活習慣や環境の方が深く関係しています。
つまり「自分にできること」はたくさんあるんです。
食事や運動、睡眠、人とのつながり。
そして「もしかして」と感じたときに早めに相談する勇気。
それらが積み重なって、自分や家族の未来を守る力になります。
認知症という言葉に不安を感じる方も多いですが、知ることは恐れることではありません。
正しい知識を持つことが、安心への第一歩。
今日からできる小さな習慣を大切にしながら、家族と一緒に未来を描いて下さいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 「家族性アルツハイマー型認知症とリスク遺伝子の違い」国立長寿医療研究センター
- 「MIND食がアルツハイマー型認知症リスクを50%以上減少させた研究」スマートドック健診クリニック
- 「認知症は遺伝するのか?」テヲトル
- 「認知症の遺伝性・検査とリスク軽減方法」朝日生命





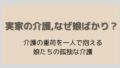
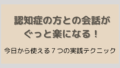

コメント