こんにちは。
今日は「介護される親の本音」に焦点を当てて、普段はなかなか聞けない思いを代弁します。
皆さんが「本当はどう思っているのか」を知ることで、介護の心づもりや接し方が
もっとあたたかくなるよう、優しい言葉でまとめました。
1.「申し訳ない」って気持ち、本当にあるんです
親御さんの多くが感じるのは、子どもに迷惑をかけてるという申し訳なさ。
「こんな年になって迷惑かけちゃって…」と涙をこらえる姿を見ると、
こちらも胸が痛くなります。
でも、子どもがそばにいてくれる安心感も同時に感じているんです。
「あなたがいれば安心」と思っているからこそ、言葉には出さなくても感謝がいっぱい。
そういう気持ちを、受け止めてあげてほしいな、って思います。
2.「たまには放っておいてほしい」も本音
介護される立場になって、最初は素直に甘えられますが、慣れてくるとこんな思いも芽生えます。
「全部やってもらうと、自分で何もできなくなる気がして怖い」
「もうちょっと自分だけの時間がほしい」
ほどよい距離感を保ちながら、子どもには頼りつつ自分の意志も大切にしたい。
そんな複雑な心境を抱えています。

3.「ありがとう」の言葉が何よりのビタミン
きちんと言葉にするのは恥ずかしいかもしれませんが、「ありがとう」は介護される側の
心にストンと届く魔法の言葉。
日常の小さなこと、たとえば「ご飯が美味しかった」「散歩連れてってくれて嬉しい」、
そんな瞬間に「ありがとう」をプラスするだけで、関係がぐっと温かくなるんです。
4.「今日はダメだけど、明日は…」もある
体調や気分は日替わりです。
昨日まで元気だったのに、今日はベッドから出たくない…そんな日もあります。
「今日はちょっとしんどいから、明日お願いね」 「また来週ゆっくり話せる?」
そんな時は無理せず受け流して。予定は白紙にして、一緒に静かな時間を過ごす。
それだけで心が和らぎます。

5.「この先どうなるんだろう」への不安も
将来への漠然とした不安も、実は大きいんです。
- 「介護が重くなったらどうしよう」
- 「自分が動けなくなったら…」
- 「子どもに財産のことで迷惑かけちゃう」
でも、心配を伝えるのは難しい。
「考えすぎかな」とか「あなたに負担になったら悪い」って、どうしても遠慮してしまうんです。
6.「一緒に決めたい」、そんな意思もある
親御さんは子どもに決めてもらいたいと思っているわけではありません。
むしろ自分も関わりたい、と思っているんです。
「今後のこと、自分も一緒に話し合いたい」 「あなたの考えも聞かせてほしいんだ」
だって、同じ家族ですもの。生きてきた人生も、価値観も、思い入れも。
そこを一緒に大切にしていきたいからこそ、「自分の思いも汲んでほしい」と思っているんです。
7.「笑い」を求めている瞬間もある
介護=しんどい、ばかりじゃないんです。
実は、笑いの力ってすごい!
「昔のボケ話、また聞きたいな」 「くだらないギャグでも笑っちゃうよ」
一緒に笑う時間が、親の気持ちを軽くしてくれる魔法なんです。
ユーモアは本当に救いになります。

8.「ありがとう」と「信じてるよ」も魔法
これもまた言葉のビタミンです。
たとえば、介護される立場でも「あなたならできるよ」と背中を押してほしい時があります。
「あなたがやってくれるから安心」「信じてるよ」
その一言が、子どもの胸にもすっと届くんですよね。
お互いの信頼が、介護生活を支えてくれる柱になります。
9.「自分の死」についての希望も
多くの方はあまり言いませんが、自分が最期をどのように迎えたいか、
という最期の願いも持っています。
それは辛くて暗い話に見えるかもしれませんが、親御さんが心穏やかに終えられるように
「事前に話す時間」が安心のためにすごく大事。
10.「あなたが大好き」も、本音中の本音
最後に一番大切なこと。
親御さんは、子どもに介護されるという状況で、愛を改めて実感しています。
「あなたがいてくれて、本当に幸せ」
その気持ちを言葉や行動で表すのは照れくさいかもしれませんが、
心の奥には深い愛情が詰まっています。

11.「自尊心との葛藤」がある
若いころにバリバリ働き、家庭を支え、家族を育ててきた「自分」。
その自分が、今や着替えや排泄すら手伝ってもらうようになっている。
「こんな姿、見せたくない」 「情けないけど、頼るしかない」
これは、親御さんの自尊心との葛藤そのものです。
自立心が強かった人ほど、このギャップに苦しみ、涙をこらえていることもあります。
12.「距離感」の難しさに悩む親心
子どもに甘えたい。
でも、甘えすぎたくない。
自分の老いに向き合う時間、子どもとの関係を壊さないようにする距離の取り方…。
それは、年齢を重ねても親でいたいという想いと、現実とのはざまで揺れ動く気持ちの表れです。
まとめ:親の本音を受け止めるために
- 「ありがとう」「信じてるよ」をしっかり伝えよう
- ほどよい距離感を大切に。頼りやすく、でも自立も尊重する
- 笑いを共有して、心の負担を解す
- 不安や不満を言葉にしにくいと知り、声に出せる環境を作る
- 最期の願いについても、優しく時間をつくって話し合おう
- 自尊心を傷つけない配慮と、静かに見守る優しさを
親御さんの心は意外と繊細で、たくさんの本音が混ざっています。
その声を、できる限り聴いて、対話して、大切に受け止めてほしい。
介護する側とされる側が、お互いに思いやりをもって歩むとき、
その道は優しい光に包まれていきます。
この記事が、読者さんたちの心に寄り添い、心温まる介護のヒントになりますように。
いつも応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
参考・出典
- NGな声…要介護者本人も「申し訳ない」「情けない」と思っている (出典:LIFULL 介護「介護される側の本音」)
- 長年自立してきた高齢者が、介護を受けることで自尊心が揺らぐ (出典:Benesse 介護相談室)
- 認知症の方の「迷惑をかけたくない」という思いが介護拒否に (出典:NHK ハートネット「認知症と自尊心」)
- 介護される人の本音は「感謝」「不安」「情けなさ」が入り混じる (出典:オレンジページ 介護特集)
- 介護拒否の原因は羞恥心。排泄や入浴などプライバシーが関わる (出典:朝日新聞デジタル「介護と羞恥心」)
- 暴言や拒否行動の背景には“親の心の叫び”がある (出典:厚生労働省「認知症施策推進総合戦略」より)
- 本音を引き出すには、週に一度の対話など小さな信頼の積み重ねが大切 (出典:みんなの介護)

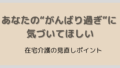

コメント