こんにちは。
「なんとなくおかしいなとは思ってたんです。でも、きっと気のせいだって…」
そう語るA子さんは、母親の認知症に気づくのが遅れたことを、
今でも深く悔やんでいます。
介護が突然始まったわけではなく、じわじわと進んでいた“違和感”。
でも、その小さなサインを、「年のせい」「疲れてるだけ」と自分に言い聞かせていた日々。
1. 小さな変化、それでも見過ごした理由
母は70代半ば。もともとしっかり者で、地域の役員も長く務めた人でした。
数年前までは孫の世話を楽しそうにしていたのに、
いつからか、A子さんが「今週の予定を教えて」と聞いても、
「え?なんだっけ…」と曖昧に笑うようになっていました。
冷蔵庫に同じ調味料が何本もある。
お風呂に入ったかどうか忘れている。
電話で話すたびに、前にもした話を何度も繰り返す。
それでもA子さんは、「うちの母に限って」「たまたま疲れてるんだ」
と心のどこかで否定していました。

2. 忙しさにかまけて、見ないふりをしていた
A子さんは会社員として働きながら、子ども2人を育てるワーキングマザー。
実家は車で30分の距離。週末にしか顔を出せないことも多く、
「実家に帰ると逆に休めない」と感じることもありました。
母の変化に気づきながらも、仕事と育児に追われる毎日。
「大丈夫だよね」「誰かが気づいたら言ってくれるはず」
そんな“誰か任せ”の気持ちも、どこかにあったかもしれません。
でも、その“気づいていたのに動けなかった”ことこそが、
後々大きな後悔として心に残ることになるのです。
3. 兄からの電話で始まった「現実」
ある日、兄からの電話がありました。
「なあ、最近おふくろの様子、おかしくないか?
こないだ銀行で暗証番号を忘れて、職員さんが気づいてくれたらしい」
兄は母と同居していたわけではないけれど、近所に住んでいたため、接する機会は多め。
A子さんはそのとき、初めて胸がザワッとしました。
「あのとき、なんでもっとちゃんと見ておかなかったんだろう」
その日は眠れない夜となりました。

4. 受診のきっかけと「認知症」という診断
兄の電話から数日後、A子さんは母を病院へ連れて行きました。
物忘れ外来という名前に、母は「なんでそんなとこ行かないといけないの」と不満げでしたが、
A子さんは“とにかく受診させなきゃ”という思いでいっぱいでした。
結果は「軽度のアルツハイマー型認知症」。
初期とはいえ、進行を止めることはできない病気です。
医師の説明を聞きながら、A子さんの頭は真っ白になりました。
「あのとき気づいていれば…」
「もう少し早く受診していれば…」
そんな言葉が、心の中をぐるぐると巡りました。
5. 自分を責める日々
「忙しかったから」「母は元気に見えたから」
いくら言い訳をしても、A子さんの胸に残ったのは、深い後悔でした。
母の様子はその後も少しずつ変化していきました。
同じ洋服を何日も着ていたり、料理の味が極端に変わったり。
そんな母に対し、A子さんはつい口調がきつくなってしまうこともありました。
「前はちゃんとしてたのに、なんでこんなこともできないの?」
後から思えば、母にとっても不安な日々だったはず。
でも、A子さんは“母が母でなくなる”ことへの恐怖に、
どう向き合えばいいか分からなかったのです。
6. 兄との温度差、家族のすれ違い
兄とは、母のケアをめぐって何度も話し合いました。
「もっと早く施設を探すべきだ」「いや、まだ家で様子を見たい」――
意見が合わず、つい感情的になることも。
母のことを思っているはずなのに、すれ違ってしまう家族の気持ち。
A子さんは、「みんながバラバラになってしまうんじゃないか」という焦りを感じていました。
そんなとき、ふと母が言ったひと言が、A子さんの心に深く刺さります。
「私、もう迷惑な存在になってるんでしょ?」
A子さんは涙をこらえきれませんでした。
7. 少しずつ向き合い始めた日々
あの日の母のひと言から、A子さんは少しずつ心の持ち方を変えていきました。
「できることだけでいい」「母が笑顔でいられる時間を1分でも増やしたい」
そう思えるようになったのは、後悔の中に“やさしさ”が芽生えたからかもしれません。
デイサービスを利用することになった母は、最初は戸惑っていたものの、
ある日「今日はね、お風呂に入れてもらったの」と嬉しそうに話してくれました。
そんな些細な会話に、A子さんは“まだ一緒に笑える”ことのありがたさを感じました。

8. 過去を責めるのではなく、「今できること」を
認知症は、誰にでも起こり得る病気。
そして、早期発見が大切だと分かっていても、
現実には「気づいても動けない」人がたくさんいます。
A子さんのように、仕事・家事・子育てに追われながら、“ちょっとおかしいかも”と思っても
見て見ぬふりをしてしまうのは、決して珍しくありません。
だからこそA子さんは、「あのとき気づけなかったこと」をずっと責め続けるのではなく、
これからの関わり方で挽回できると信じて、母と向き合い続けているのです。
※この記事は、複数の体験談や調査をもとに構成したフィクションです。
誰にでも起こりうる認知症という病気に対しての気づきになればと願って書きました。
9. この記事を読んでくださったあなたへ
もしあなたのご家族に、「最近ちょっと様子が変かも」と思うような方がいたら、
どうか少しだけ気にかけてあげていて下さい。
気づけなかった過去ではなく、気づいた“今”がとても大切だからです。
そして、どんなに小さな変化でも、誰かに相談してみる勇気を、どうか忘れないでください。
A子さんのような思いをする人が、一人でも少なくなりますように――。
いつも応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
参考
- 厚生労働省「認知症を知り地域をつくるキャンペーン資料」
- 公益社団法人 認知症の人と家族の会「初期の認知症に気づくために」
- 東京都福祉保健局「認知症の初期サインと家族の対応」
- 日本老年精神医学会「認知症の早期診断と受診のすすめ」
- 内閣府「高齢社会白書(認知症と家族の関わり)」
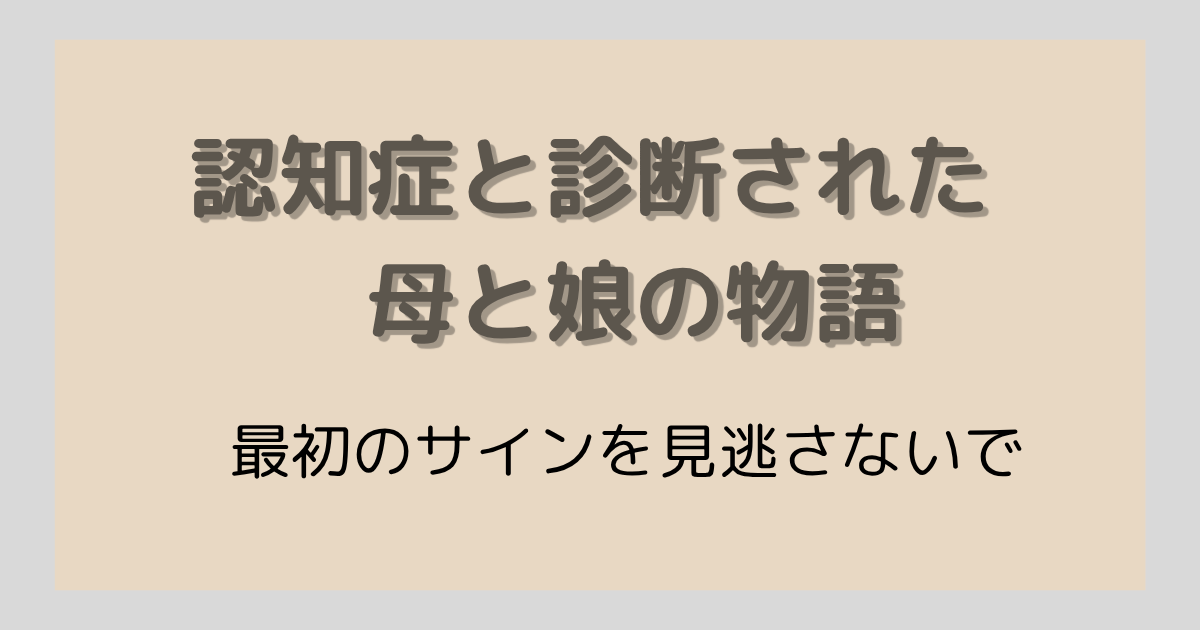
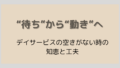
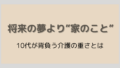

コメント