こんにちは。
「要支援1って軽い介護?」
「要介護ってどこから大変になるの?」
介護保険を初めて使うとき、多くの方がこの“分類”でつまずきます。
ケアマネージャーさんから「要支援認定でした」「今回は要介護2です」と説明されても、
それが具体的にどんなサービスにつながるのか、すぐにはピンとこないことも。
でもこの違いを理解しておくと、利用できるサービスの幅や、
これからの生活設計に大きく役立つんです。
この記事では、要支援と要介護の基本的な違いから、それぞれに用意されているサービス、
家族がどう対応すべきかまで、わかりやすく解説していきます。
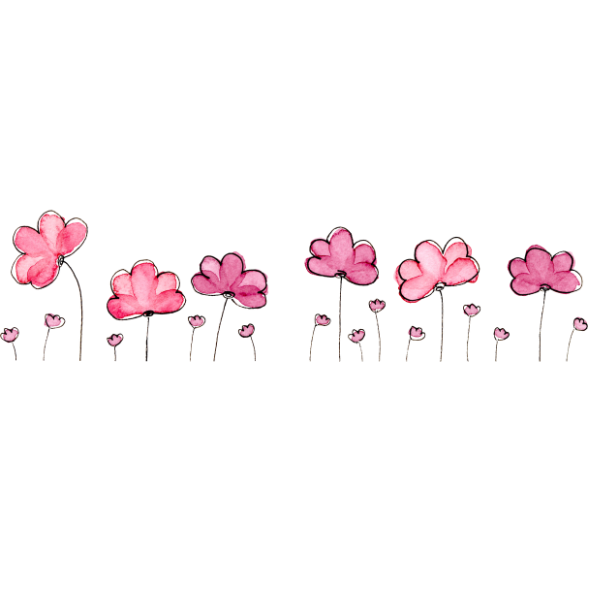
要支援と要介護の違いとは?
まずは、制度的な違いを確認してみましょう。
「要支援」「要介護」は、介護認定の区分として設けられており、
どちらも市町村が行う介護認定(要介護認定)によって決まります。
要支援とは
加齢によって筋力や生活機能が低下し、
家事や買い物などの“日常生活に少し支援が必要”な状態を指します。
要支援1と要支援2の2段階に分かれ、比較的軽度な支援が求められる方が対象です。
要介護とは
認知症や身体の障害などにより、日常生活に介護が必要な状態です。
要介護1から5までの5段階があり、数字が大きいほど介護の必要度が高くなります。
食事や入浴、排せつの介助、移動の支援などが必要になるケースも含まれます。
どこで線引きされるの?
要支援と要介護は、「基本的な生活動作」がどれほど自力でできるかが大きなポイント。
たとえば、歩けるか・トイレに行けるか・服の着脱ができるかなどが判断材料になります。
また、認知症の進行具合や家族のサポート体制なども審査の対象です。
[PR]要支援のサービス内容
要支援1・2と認定された方が受けられるのは、介護予防サービスと呼ばれる支援です。
目的は“現状維持”あるいは“改善”であり、「できることを続ける力を支える」
という視点で提供されます。
主なサービス
以下のようなサービスが、地域包括支援センターを通して提供されます。
・介護予防訪問介護(生活援助中心型):掃除や調理、買い物などの家事支援
・介護予防通所介護(デイサービス):軽い運動やレクリエーションなど
・配食サービス:栄養バランスのとれた食事の宅配
・転倒予防の運動教室:リハビリ的なトレーニング支援
・福祉用具の貸与(軽度用):歩行器や手すりなどの利用
要支援の方に対しては、「○○をしてあげる」ではなく、
「○○ができるよう支える」という姿勢が基本です。
「まだ自分でできる」「もう少し頑張れる」を大切にすることで、
介護状態への進行を防ぐ役割を果たしています。
要介護のサービス内容
一方で、要介護1~5と認定された方には、より手厚い介護保険サービスが提供されます。
身体介助・生活援助・通所・施設入所など、選択肢の幅が広がるのが特徴です。
代表的なサービス
状態やニーズに応じて、以下のようなサービスが利用できます。
・訪問介護(ホームヘルパー):入浴・排せつ・食事などの身体介助
・通所介護(デイサービス):日中のケア、機能訓練、送迎
・訪問入浴・訪問看護:看護師や介護職による在宅支援
・短期入所(ショートステイ):家族の負担軽減や一時的な休養に
・特別養護老人ホーム:要介護3以上の方向けの長期入所施設
・福祉用具の貸与・住宅改修:手すり設置や段差解消などの住環境整備
要介護になると、ケアマネージャーが個別にケアプランを作成し、
本人と家族に最適なサービスが組み合わされます。
介護度が上がるほど支援は多くなり、家族だけでの対応が難しくなるケースも少なくありません。
要支援から要介護になるとどう変わる?
要支援から要介護へと移行するケースは少なくありません。
筋力や認知機能の低下、病気やケガなど、生活機能が急に落ちることで、
支援レベルから介護レベルに切り替わることもあります。
サービス内容の変化
要支援では「自立支援」が基本でしたが、要介護では「生活維持・介助」が主な目的になります。
たとえば、同じ「デイサービス」でも内容は変わります。
要支援では軽い運動や予防プログラムが中心ですが、
要介護では機能訓練・個別介助・入浴支援などが加わります。
生活の見直しが必要に
要介護になると、家の中の動線や通院方法など、
暮らしそのものの見直しが求められる場面も増えてきます。
特に「ひとり暮らし」や「高齢夫婦のみ」の世帯では、
介護サービスの組み合わせによるサポート体制が重要になります。
[PR]どう選ぶ? 家族ができるサポート
介護認定の結果が出たとき、
家族として「どう受け止め、どう支えたらいいのか」は悩みどころですよね。
ここで大切なのは、「どんな支援が“今の状態”にふさわしいか」を一緒に考えることです。
ケアマネージャーとの連携を大切に
認定後は、地域包括支援センター(要支援)
または居宅介護支援事業所(要介護)のケアマネージャーが介入します。
家族の希望もきちんと伝えることで、無理のないケアプランを組んでもらいやすくなります。
本人の気持ちに寄り添って
要支援でも要介護でも、本人が「自分らしく生きる」ことを支える視点が大切です。
「できることは任せる」「困ったら手を貸す」そんな柔軟な距離感が、安心を育みます。
[PR]最後に
要支援と要介護の違いは、“介護の重さ”だけでなく、
サービスの目的と支援の方向性にあります。
| 分類 | 対象者 | 目的 | 主なサービス |
|---|---|---|---|
| 要支援 | 自立はしているが支援が必要な方 | 介護予防・自立支援 | 生活援助・軽度デイサービス・運動教室 |
| 要介護 | 日常生活に介助が必要な方 | 生活支援・介助提供 | 訪問介護・通所介護・ショートステイ・施設入所 |
介護は「制度」を知ることも大切ですが、
“今の暮らしに合っているか”を常に見直していくことが、何より大事です。
あなたとご家族が、どんな段階でも、
“できること”を支える介護を目指して歩んでいけますように。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 厚生労働省「介護保険制度について」
- 厚生労働省「要支援・要介護の認定基準と流れ」
- 東京都福祉保健局「介護サービスの種類と利用方法」
- 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会「要支援・要介護別サービス内容」
- 認知症介護情報ネットワーク「要介護認定の仕組み」
- NHKハートネット「介護保険で受けられるサービスとは」


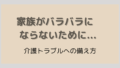
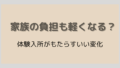

コメント