こんにちは。
在宅介護を続けていく中で、頼りになるのは人の手だけではありません。
ちょっとした道具や介護グッズが、毎日の負担をぐっと軽くしてくれることもあるのです。
今回は「本当に役に立つ!」といわれるアイテムをご紹介します。
すべてが特別なものではなく、身近なものが多いからこそ、
今すぐ取り入れられる工夫もきっと見つかるはずです。
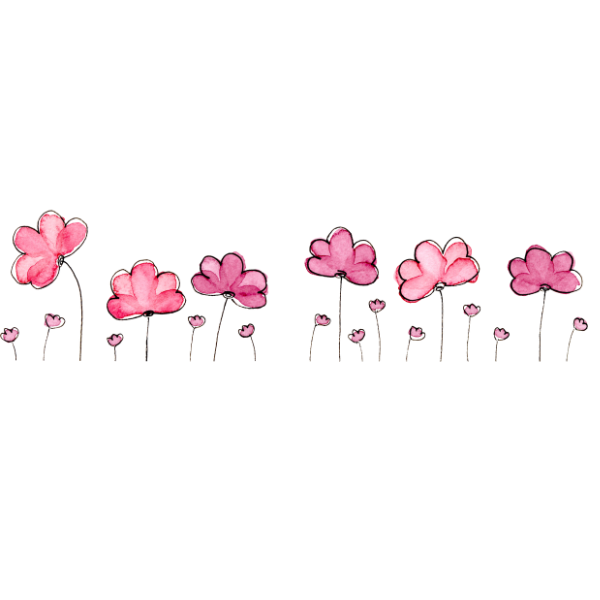
まずは安全第一! 滑り止めマットの効果
「転ばないこと」が、高齢者の介護における最優先事項の一つ。
特に浴室や玄関、ベッドサイドなど、滑りやすい場所は要注意です。
そんなときに役立つのが「滑り止めマット」。
市販のゴム製マットでも、設置するだけで足元の安定感がまったく違います。
特に役立つのは、吸着タイプの滑り止めマット。
ズレにくく、手洗いできるので衛生面でも安心。
介護保険のレンタル対象にはならないけれど、
ホームセンターやネットショップでも手軽に買えるので、試してみる価値は大いにあります。
設置場所の工夫で転倒リスクを減らす
・玄関マットの下に敷く
・ベッドの横に敷く
・トイレの前に小さいサイズを置く
転倒防止だけでなく、足音を軽減したり、冷たい床の感触を和らげる効果もあります。
おむつ交換がラクになる! 使い捨て防水シート
在宅でのおむつ介助では、寝具の汚れ防止が大きな課題です。
そんなときに重宝するのが「使い捨て防水シート」です。
市販の防水シートもありますが、洗濯が大変という声も。
そこで導入したいのが使い捨てタイプのもの。
薄手でもしっかりとした吸水力があり、処理も簡単。
何より、汚れたらそのまま捨てられる安心感があります。
コスパは気になるかもしれませんが、夜間や体調不良時だけ使うといった限定的な使い方でも、
十分に効果を発揮します。
使い方のコツ
・シーツの上に直接敷く
・大きめのサイズを選んでずれを防ぐ
・1枚ずつストックしておいて、すぐ使えるようにする
感染予防や衛生面の観点からも、非常に心強いアイテムです。
コミュニケーションを支える! 卓上ベルや呼び出しボタン
介護をしていると、相手の声が小さくて聞き取れないことや、
別の部屋にいて気づかないこともよくあります。
そんなときに導入したいのが、「呼び出しベル」。
ホテルのフロントに置いてあるようなタイプの卓上ベルや、ワイヤレスの呼び出しボタンです。
「音を鳴らすのが申し訳ない…」とためらう高齢者もいますが、
安心感があることで気持ちも安定します。
むしろ、「呼べる手段がある」ことが、自立の一歩につながることもあります。
呼び出しツールの選び方
・軽く押すだけで反応するものを選ぶ
・音の大きさが調整できるタイプがおすすめ
・設置する場所はベッドサイドやトイレ前
介護される側の「困った」と、介護する側の「気づけなかった」を埋めてくれる、
小さくても頼もしい存在です。
[PR]食事介助をスムーズに! テーブル付き介護用イス
食事の時間がうまくいかない…という声は多く聞かれます。
特に姿勢の保持が難しかったり、体のバランスが不安定な方にとって、
普通の椅子では食べにくいことも。
そこで取り入れたいのがテーブル付きの介護用イスです。
食事用のテーブルが一体になっていることで、姿勢が崩れにくく、食器が安定するメリットも。
また、キャスター付きで移動もしやすく、トイレや入浴の前後など、日常生活の中でも大活躍。
家の中での“もうひとつの安心ポジション”として重宝します。
ポイント
・座面の高さが調整できるタイプが便利
・クッション性があり、長時間座っても疲れにくい
・脱着可能なテーブル付きなら掃除もラク
イスひとつでも、「座って食べる」がスムーズになるだけで、
介護の雰囲気がグンと明るくなりそうです。
水分補給が楽になる! ストロー付きマグや吸い飲み
高齢になると、コップで水を飲むのも難しくなることがあります。
特に寝たままでの水分補給には工夫が必要です。
そんな時便利なのがストロー付きマグや吸い飲みタイプの容器です。
軽く傾けるだけで水分がスムーズに口に届き、
こぼれにくい構造になっているものが多いのが特徴です。
誤嚥を防ぐためにも、一気に流れ込まないタイプや、
吸う力が弱くても飲める工夫がされたものを選びましょう。
選び方のコツ
・飲み口が柔らかく、口当たりのいい素材を選ぶ
・逆流防止弁があると安心
・洗いやすさも大事なポイント
ちょっとした道具の違いで、「飲みたいのに飲めない」というストレスがなくなり、
自分から水分を摂ってくれるようになることもあるようです。
排泄ケアをサポート! ポータブルトイレの進化
自室からトイレが遠い、夜間の移動が不安…。
そんな悩みを抱えるご家庭ではポータブルトイレが大きな助けになります。
最近のものは見た目もインテリアに馴染みやすく、
消臭機能付きや温水洗浄付きなど機能面も充実。
座り心地も配慮されていて、「仕方なく」ではなく「選んで使う」感覚になってきています。
導入に戸惑う方も多いですが、「トイレが近くにある」というだけで心理的な安心感が生まれ、
自立を促す効果もあるのです。
設置のポイント
・できるだけベッドのすぐ横に置く
・転倒しないように周囲を整える
・カバーや目隠しで生活感を和らげる
夜間の移動を減らすことで転倒リスクも下がり、介護する側の安心にもつながります。
[PR]心の距離を縮める! 写真立てと昔のアルバム
介護において「道具=便利グッズ」だけではありません。
心のケアという観点から、とても役立つのが写真やアルバムです。
昔の写真を見ることで自然と会話が生まれ、笑顔も増えてきます。
「このときの旅行、楽しかったね」「おじいちゃんの若い頃かっこいい!」と、
懐かしい記憶を一緒にたどる時間は、介護する人にとっても癒しになります。
認知症の進行を遅らせる効果もあるといわれており、飾るだけでも良い刺激になります。
飾り方・見せ方の工夫
・リビングやベッドサイドに写真立てを置く
・家族でアルバムを見る“おしゃべりタイム”をつくる
・デジタルフォトフレームで写真をスライド表示するのもおすすめ
「道具」というより、「つながりのきっかけ」になる大切な存在です。
離れていても見守れる! 家庭用見守りカメラ
仕事中や買い物中でも、「今、家でどうしてるかな…」と心配になること、ありませんか?
そんな時に安心感をくれるのが家庭用見守りカメラです。
スマホと連動して、リアルタイムで様子が確認できるだけでなく、
動きを感知して通知してくれるタイプもあり、異変にもいち早く気づけます。
声かけ機能があるカメラもあり、「今見てるよ〜」「大丈夫?」といった声かけが、
離れていても気持ちを届けてくれる手段になります。
選ぶポイント
・夜間撮影ができるタイプ
・Wi-Fi接続が安定しているもの
・操作がシンプルで、家族も使いやすいこと
「監視」ではなく、「見守り」として使うことで、お互いの安心感が高まります。
見守る側も、気持ちに余裕が生まれます。
介護アプリで記録と共有を簡単に
日々の介護記録をつけるのは大変。
でも、体調の変化や服薬状況をきちんと記録しておくことはとても大切です。
そんなときに役立つのが介護用のアプリ。
スマホで簡単に記録ができて、複数人での情報共有もスムーズになります。
「今日のお通じはあった?」「昼はちゃんと食べたかな?」など、
細かいこともアプリに書き残すことで、家族間の伝達ミスも減らせます。
こんなアプリが便利!
・服薬記録が通知付きで残せるもの
・複数アカウントで共有可能なアプリ
・グラフやメモで体調の変化が見やすいタイプ
手書きの記録帳もいいけれど、スマホを活用することで手間が減り、
「記録する余裕」が生まれます。
最後に
介護の道のりは長く、時には心が折れそうになることもありますよね。
でも、そんなときに支えてくれるのは、人の優しさと、ほんの少しの便利さだったりします。
高価な福祉用具でなくても、“ちょっとした工夫”や“今の暮らしに合ったアイテム”が、
介護をラクに、そして前向きにしてくれるのです。
今回ご紹介したアイテムが、みなさんの介護生活のヒントや支えになりますように。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- テクノエイド協会「福祉用具情報システム(TAIS)」
- 厚生労働省「介護保険制度における福祉用具貸与の基準」
- 雑誌『日経ヘルスケア』「介護の現場で役立つアイテム最新事情」特集号
- 介護保険最新情報

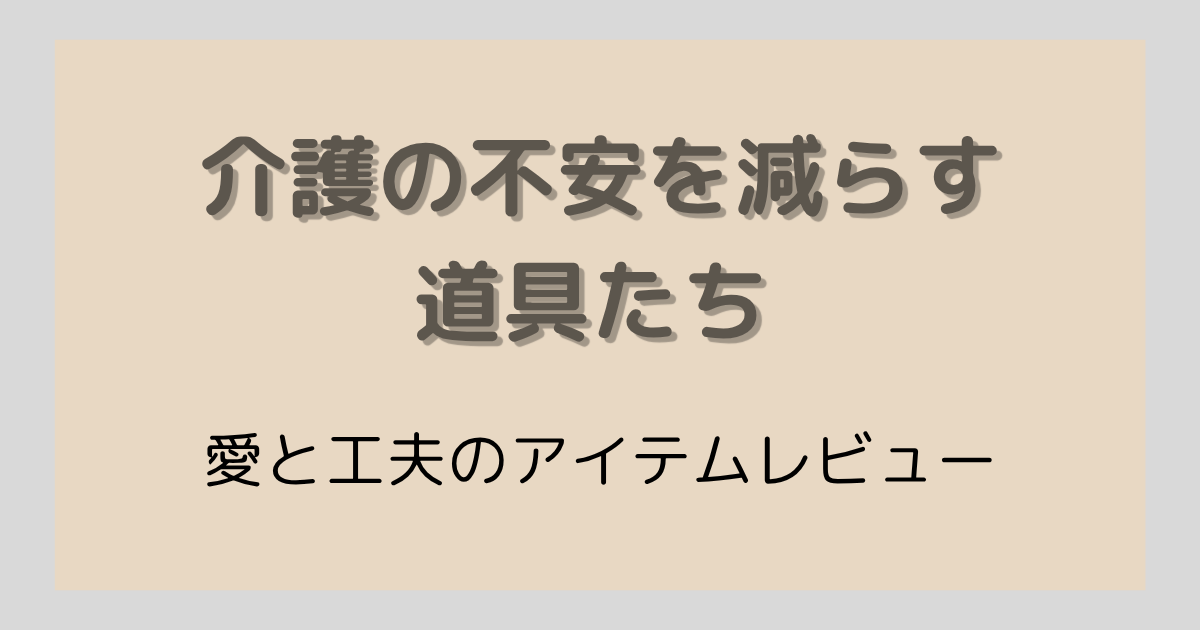
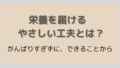
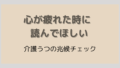

コメント