こんにちは。
「そんなはずない」「物忘れくらい誰にでもあるだろう」――
家族が心配して認知症を疑っても、本人がそれを認めたがらないことは少なくありません。
病気を受け入れないまま時間が経つと、
適切な医療や介護サービスに繋がるタイミングを逃してしまうことも…。
でも、頭ごなしに「病気だから!」と伝えるのは、かえって信頼関係を壊す原因にもなります。
今回は、認知症を受け入れられない本人にどう寄り添い、
どんな言葉で伝えればよいのかを一緒に考えていきます。
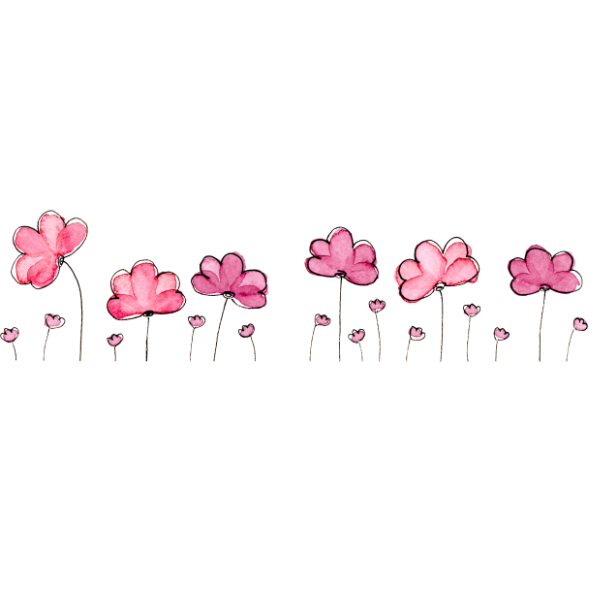
なぜ認めたがらないのか? 本人の心理を理解する
まず大切なのは、「なぜ本人が病気を認めたくないのか?」という気持ちに寄り添うことです。
多くの場合、認知症と聞くと、「もう終わりだ」「自分は人としてダメになった」
と感じてしまう方が少なくありません。
つまり、認知症=人生の終わり、という極端なイメージを抱いてしまい、
「否定することで自分を守っている」のです。
また、自尊心や恐怖心も複雑に絡んでいます。
本人にとっては病気を受け入れることは“自分の人生を否定されるような感覚”でもあるのです。
「説得」ではなく「共感」がスタートライン
ここで大切なことは、無理に認めさせようとしないことです。
家族が「病気だから病院に行こう」と言っても、本人にとっては「病人扱いされた」と感じ、
かえって反発を招くことがあります。
まずは「不安だったよね」「わたしも最初は混乱したよ」といった、
共感の言葉からスタートしてみて下さい。
それだけで本人は、「分かってくれている」と感じて、
少しずつ心を開いてくれる可能性が出てきます。
共感の気持ちを態度でも言葉でも伝えることが大切です。
言い方ひとつで、受け止め方が変わる
病院に連れていくのも一苦労…という声は本当に多いです。
同じ内容でも、言い方によって、本人の反応は大きく変わります。
本人の自尊心を守りながら、「安心のための行動」として提案するのがコツです。
また、普段の会話の中で、病気に関する話題をサラッと織り交ぜることも効果的です。
「最近は早期発見で良くなることもあるみたいだね」と、あくまで情報提供として話すことで、
少しずつ心のハードルを下げていきましょう。
[PR]タイミングと場所を見極める
人目がある場所や、疲れているとき、機嫌の悪いときに話してしまうと、
かえって逆効果になることがあります。
朝よりもゆっくり話せる午後の時間にしてみたり、
本人の好きな場所や落ち着く空間で話すのが効果的です。
タイミングって結構大事なんです。
家族だけで抱え込まず「第三者の力」を借りる
認知症を本人が認めないとき、
家族が一人で抱え込んでしまうと、関係がこじれることもあります。
そんな時に頼れるのが、地域包括支援センター、認知症サポート医、ケアマネジャーなど、
専門の第三者の存在です。
専門職は「病気を説明するプロ」でもあり、中立的な立場だからこそ、
本人が受け入れやすいというメリットもあります。
本人が「病気扱いされた」と感じないように、
ごく自然な流れでの説明を取り入れてもらうことがポイントです。
感情的になったときの対処法
もし本人が怒ったり、拒否的になったりしたときは、無理に押し通さず、
いったん距離を置くことも大切です。
「今は話すタイミングじゃなかったんだな」と受け止めて、
改めて別の日にチャレンジしてみましょう。
説得は、1回で決着がつくものではありません。
焦らず、何度でもやさしく声をかけていくことが信頼の積み重ねになります。
そして、「変わらない親を受け入れる覚悟」も、家族には時に求められます。
本人の「否認」は、その人らしさの一部でもあるのかもしれません。
認めないままでも支援につなげる工夫
たとえ本人が認知症を認めなくても、支援やケアの道は閉ざされていません。
実際に、本人が「病気じゃない」と言い張っていても、
介護保険の申請やサービス導入は可能です。
本人にとって「介護」や「病気」という言葉が強すぎる場合は、
「便利な支援」「安心のためのサービス」という伝え方に変えてみて下さい。
また、ケアマネジャーや相談員に、「本人は病気を認めていない」
という情報を事前に伝えておけば、配慮ある対応をしてくれます。
認めない本人に寄り添い続けるために
説得がうまくいかなくても、「関わり方」ひとつで関係性は変わっていきます。
家族としては、「認めさせること」よりも
「困っている状況に寄り添い続けること」のほうがずっと大切です。
・忘れ物や失敗を責めず、そっとフォローする
・昔話や得意なことを話題にして「自分らしさ」を感じられる時間を作る
・感情が不安定なときは、「そばにいるよ」という姿勢を示す
本人が病気を認めなくても、人と人としての信頼関係は築けます。
そしてその信頼が、いつか本人の心の扉を開くきっかけになるかもしれません。
家族自身の心を守ることも忘れずに
説得がうまくいかない、思うように動いてくれない…そんな日々が続くと、
家族も心が疲れてしまいますよね。
そんなときは、誰かに話したり、相談することがとても大切です。
地域包括支援センターや認知症カフェ、家族会など、同じ立場の人とつながれる場所があります。
また、ケアマネジャーや訪問看護師さんなど、プロの力を遠慮なく借りて下さい。
家族が元気でいてこそ、本人にもやさしく接することができます。
[PR]最後に
認知症を本人が認めない――これは多くの家庭がぶつかる難しい課題です。
大切なのは、本人の気持ちに寄り添いながら、できることを少しずつ重ねていくこと。
無理せず、でもあきらめずに、やさしい関わり方を見つけていけますように。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)
- 東京都健康長寿医療センター研究所「高齢者の心理と行動特性について」
- 独立行政法人 国立長寿医療研究センター「高齢者の記憶と回想法の活用」

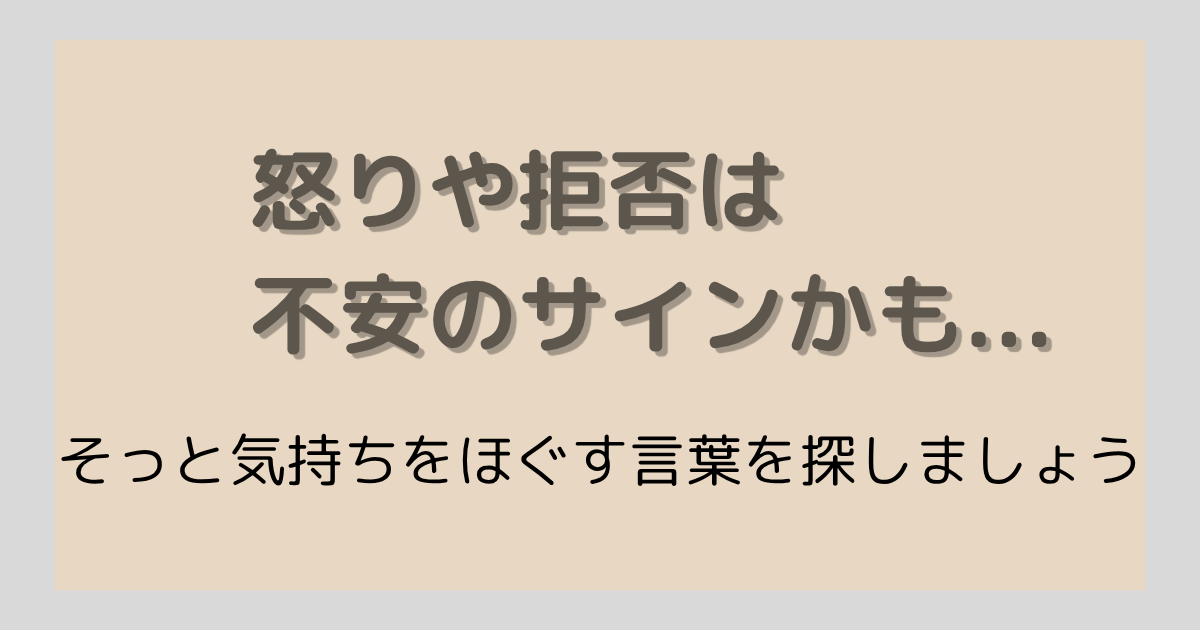
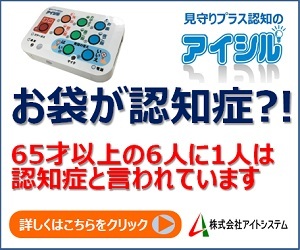
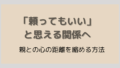
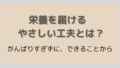

コメント