こんにちは。
「特別養護老人ホームに申し込んだのに、もう半年以上待たされている…」
「母が限界なのに、“順番待ち”と言われて、どうすればいいの?」
そんな声が、日本中であとを絶ちません。
特別養護老人ホーム、通称「特養(とくよう)」は、要介護度が高く、
家庭での介護が難しい高齢者にとって、最後の砦のような存在です。
しかし、この特養に入りたくても入れない「待機老人問題」が深刻化しています。
待ち期間が長期化し、場合によっては数年単位での順番待ちになることも。
今回は、「なぜ特養に入れない人が多いのか」「待機老人とは具体的にどんな状況なのか」
「そしてその背景にある社会的な課題や制度の限界」について、
分かりやすくお伝えしていきます。
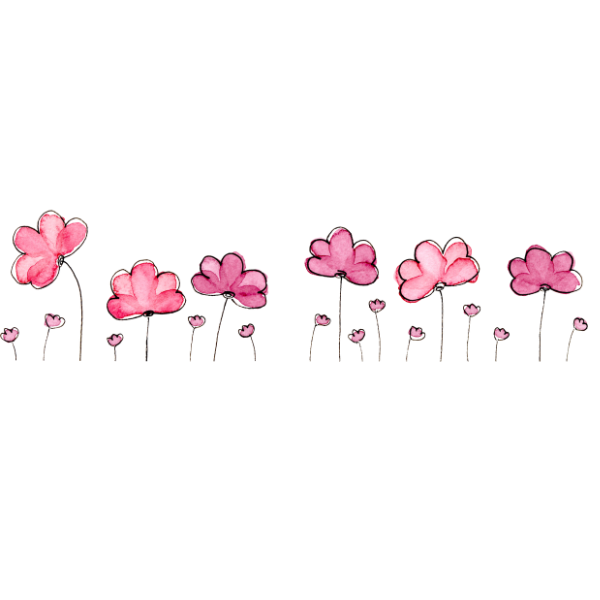
特養ってどんな施設?
まず最初に、特別養護老人ホーム(特養)について簡単に整理しておきましょう。
特養は、公的な介護保険施設の一つで、以下のような特徴があります。
⚫︎ 対象は原則として要介護3以上の高齢者
⚫︎ 入居費用が比較的安価
⚫︎ 終身での利用が可能なケースが多い
いわば「重度の要介護高齢者を、継続的にケアするための施設」として設計されています。
費用面でも他の施設よりリーズナブルなため、
「最終的には特養に入ってもらえれば安心」と考えるご家族も少なくありません。
なぜ入れない?「待機老人」とは
ところが実際には、希望してもすぐに入れるわけではありません。
この「特養に申し込んでも、すぐには入れない状態にある高齢者」が、
いわゆる「待機老人」です。
厚生労働省の統計によれば、全国で約29万人(※2022年時点)が
特養の入居待ちをしているとされています。
地域によっては、申し込み後に「順番は800番目です」と言われることもあり、
「本当にこのまま順番が来るのだろうか?」という不安と焦りがつのります。
優先順位の仕組みと“点数制”の壁
「順番待ち」とは言っても、実は単純な“先着順”ではありません。
多くの自治体では、特養への入居申込者に対して「点数」をつけ、
優先度を評価する仕組みを採用しています。主な評価基準は以下のようなものです。
・介護度(重度ほど点数が高い)
・在宅かどうか(自宅介護中は点数が高い傾向)
・家族の介護負担
・本人の医療的ニーズや緊急性
つまり、「要介護4・独居・老老介護中」といった深刻な状況の人が、
比較的早く入居できる仕組みです。
一方で、たとえ要介護3でも「家族が在宅で介護できている」
「すでに有料老人ホームなどに入居している」といった場合、
点数が伸びず、後回しにされやすくなるのです。
「制度は理解できるけれど、現場の現実はもっと切実なんです」──
これは多くの家族の共通する思いです。
待機中の“中間施設”という選択
特養に入れない間「では、どこで暮らせばいいのか?」という問題がすぐにのしかかってきます。
よくあるのが、以下のような“中間的な居場所”です。
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・ショートステイのロング利用
・自宅+訪問介護でしのぐ
しかし、これらの選択肢は費用負担や介護の継続性の点で課題も多く、
必ずしも安心できる状況とは言えません。
たとえば、ショートステイ(短期入所生活介護)を
「特養の順番が来るまで…」と何カ月も使い続けるケースでは、
そもそも施設側が長期利用を受け入れられないこともあります。
さらに、有料老人ホームなどに一時的に入ったことで、「在宅じゃないから」という理由で
特養の優先順位が下がってしまう──という皮肉な状況も起きているのです。
家族介護者の限界とプレッシャー
「順番を待つ間、なんとか家でみるしかない」
そんな判断をする家族も多いのですが、実際にはかなりの負担がかかっています。
特に老老介護や、遠距離介護、共働き世帯では、在宅での生活維持は困難を極めます。
「もう限界なのに、入所先がない」
「特養しか費用的に無理だけど、順番が来ない」
「どこに相談しても、あきらめずに待つようにと言われるだけ」
こうした声の背景には、介護者の精神的・肉体的な疲弊があります。
一方で、入居できるまでの生活を支える社会資源が乏しく、
在宅介護のプレッシャーだけが重くのしかかっているのが現状です。
地域格差という“見えにくい壁”
実は、特養の待機状況には地域による大きな差があります。
都市部では施設の需要が供給を大きく上回っており、1000人以上が待っている自治体も。
一方で、地方の一部では空きが出ている施設もあるという、二極化の傾向が見られます。
「うちの市では3年以上待ち」「隣の県ならすぐ入れる」──そんな話も現実にあるのです。
しかし、要介護高齢者を遠くの県外施設に入れるとなると、家族の面会が難しくなり、
緊急時の対応にも支障が出るため、現実的な選択肢とは言いがたいのです。
また、介護人材の地域格差や施設職員の不足も受け入れのハードルを上げる要因になっています。
特養側の「受け入れられない事情」
一見、空きベッドがあるように見えるのに、「入居できない」と言われることもあります。
その理由の一つが、介護職員の人手不足です。
たとえば、職員数が足りないために「ベッドは空いていても受け入れられない」という状況が、
実際に多くの施設で起きています。
また、医療的ケアが必要な方や、認知症の行動・心理症状が強い方など、
介護の難易度が高い入居者への対応に限界がある施設も少なくありません。
施設側も日々ぎりぎりの体制で運営しており、
「受け入れたくても受け入れられない」事情があるのです。
制度の狭間で取り残される人たち
「特養に入りたいけど、入れない」
「ほかの施設は高くて無理」
「在宅介護にも限界がある」
このようなジレンマに直面している家族や高齢者は、今、日本全国に数多く存在しています。
介護保険制度の“理想”と、“現場の現実”とのギャップ。
その狭間で、誰にも頼れずに取り残されてしまう──。
それが「待機老人問題」の本質かもしれません。
この問題は、高齢者自身だけでなく、
家族の生活や健康、仕事、人生設計にまで深く関わってきます。
今後どう変わる? 制度と支援のこれから
政府や自治体も、こうした状況を受けて徐々に制度の見直しや整備を進めつつあります。
たとえば──
・地域包括ケアシステムの充実
・特養の増設や小規模施設の開設支援
・介護人材確保のための施策強化
・介護者へのレスパイト(一時的な休息)支援
制度の改善が追いつくまでの間、少しでも現場の声が届きやすくなるよう、
そして“孤立”を生まないような社会的仕組みが求められています。
最後に
「誰にも相談できなかった」
「申し込んだけど、音沙汰がない」
「気がついたら、介護うつになっていた」
そう語る人たちは、決して少数派ではありません。
待機老人問題は、
介護の“終着点”である特養の入口があまりに狭くなっていることに起因します。
そしてそのしわ寄せは、在宅で必死に支える家族や、
制度をよく知らないまま困っている高齢者自身に向かっています。
地域包括支援センターやケアマネジャーに相談すること。
同じ悩みを持つ家族とつながること。
そして、こうした現場の実情や疑問をもっと多くの人に知ってもらうこと。
これらは大切な第一歩だと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
参考
- 厚生労働省「特別養護老人ホームの入所基準と現状」
- 内閣府「高齢社会白書(待機老人の実態と課題)」
- 全国老人福祉施設協議会「特養における入所待機者の実態調査」
- 総務省「地域における高齢者福祉の現状と課題」


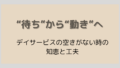
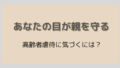

コメント