こんにちは。
「毎日のごはん作り、大変だな…」と感じるとき、市販の介護食が気になる方も多いと思います。
「市販の介護食って実際どうなの?」
「どうやって選べばいい?」
「買うとき、気をつけることってある?」
今日はそんな素朴な疑問に、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
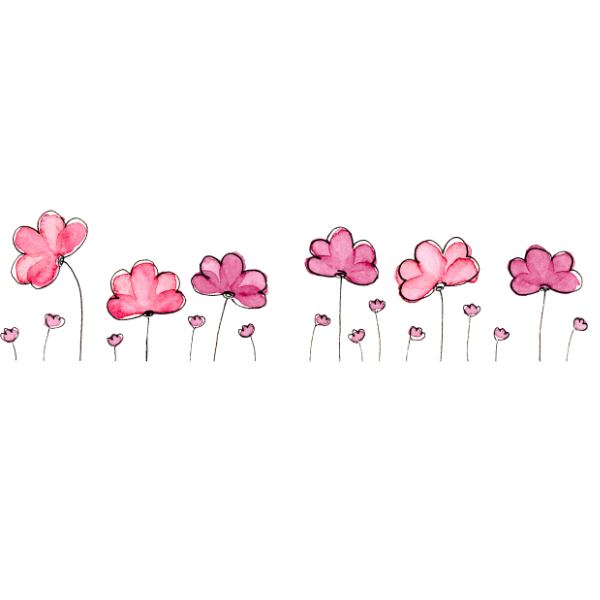
そもそも「市販の介護食」ってなに?
最近は「介護食」と書かれた商品をよく見かけます。
これは、高齢の方や噛む・飲み込む力が弱くなった方向けに、
食べやすさや栄養バランスを考えて作られた食品のこと。
⚫︎おかゆや雑炊など“やわらかいごはん”
⚫︎ペースト状のおかず(魚や肉、野菜など)
⚫︎とろみのついたおかず
⚫︎ゼリー状やムース状のデザートや飲み物
などなど、種類もとても豊富です。
なぜ市販の介護食が人気?
昔は「おうちで手作り」がほとんどだった介護食。
でも、今は市販品を使うご家庭も増えています。
その理由は…
●いつでも手軽に準備できる
忙しい介護の合間に、すぐ使えるのが本当に助かるポイント。
冷蔵や常温、電子レンジOKの商品も多く、保存も簡単です。
●栄養バランスを考えて作られている
高齢者向けに、「タンパク質強化」「エネルギー補給」「塩分控えめ」など、
バラエティも多いです。
医師や管理栄養士が監修している商品もあります。
●食べられるもののバリエーションが広がる
和食、洋食のほか、カレーやシチュー、デザートまで!
好きな味を選びやすく、日々のご飯がもっと楽しみに。
「自分ですべて手作りしなきゃ…」と追い込まれることなく、
うまく市販品を取り入れながら、介護を続けられる方も多いようです。
どんな人が市販の介護食を使っているの?
基本的に、次のような方におすすめです。
⚫︎噛む・飲み込む力が弱くなってきた方
⚫︎誤嚥(ごえん:食べ物が気管に入ること)のリスクがある方
⚫︎食べる量が減ったり、食事のバリエーションがほしい方
⚫︎体調不良、病気、手術後で食事作りが大変なとき
また、在宅介護だけでなく、入院や施設での間食・補助食にも活躍します。
市販の介護食の種類と特徴(区分食)
日本では「ユニバーサルデザインフード(UDF)」という共通マークが使われていて、
「どれくらいかたさ・やわらかさか?」が一目でわかる4段階表示になっています。
・区分1:容易にかめる(柔らかめのご飯やおかず)
・区分2:歯ぐきでつぶせる(さらにやわらかい)
・区分3:舌でつぶせる(ペーストやムース)
・区分4:かまなくてよい(ゼリー状・飲み込みやすい)
パッケージにマークや区分表示があるので、
「今の状態にはどれが合うかな?」と選びやすくなっています。
もちろんこのほかにも「栄養調整食品」や
「高カロリー・高タンパク食品」などのラインナップも増えていますよ。
市販の介護食の選び方ポイント
さて、いざ介護食を探し始めると、
種類が多すぎて「結局どれがいいの?」と迷ってしまうこともありますよね。
そんな時は、次のポイントを意識すると選びやすいですよ。
❶「噛む力・飲み込む力」に合ったものを選ぼう
介護食の最大のカギは、本人の状態に合ったやわらかさ・形状。
パッケージの「ユニバーサルデザインフード(UDF)」区分や
「○○でつぶせる」などをしっかり確認しましょう。
たとえば、「歯ぐきでつぶせる食感?」「舌でつぶせる柔らかさ?」など、
食べる人本人の「今」にぴったりなものをチョイスするのが安心です。
❷ アレルギーや持病に対応した食材
原材料やアレルギー物質表示もチェックしましょう!
アレルゲンフリーや塩分控えめ商品もあるので、
医師・管理栄養士に相談しながら選ぶとさらに安心です。
❸ 栄養バランス
タンパク質、エネルギー、ビタミン・ミネラルの内容も大切。
主食・主菜・副菜を組み合わせたり、間食用ゼリーなどで補ったりして、
栄養が偏らないようにしましょう。
❹ 本人の「食の好み」や彩りも意識
どうしても毎日同じような介護食になりがち…
そんなときは、見た目や味つけ、好きな食材や季節のメニューにも気を配って、
「食べる楽しみ」を大切にできると素敵ですね。
❺ コストパフォーマンス
市販の介護食はメーカーや品目で価格に差が出やすいので、
内容量と栄養価も比べながら、続けやすいものを選びましょう。
[PR]市販の介護食を使うときの注意点
便利で美味しい市販の介護食ですが、使うときに気をつけたいポイントもあります。
❶ 必ず「本人に合った固さ・形状」を選ぶ
その人によって、今日食べやすいもの・明日だと難しいものもあります。
一度買ったら終わりではなく、体調や嚥下(のみこみ)の様子をよく観察して、
必要があれば医師・管理栄養士にも相談しましょう。
❷ 誤嚥(ごえん)や窒息のリスク
ゼリー食やムース食でも、本人のペースでゆっくりと、姿勢も正して食べることが大切。
「食べられるかな?」と不安な時は、飲み込んだ後の様子も観察。
むせたり咳き込んだりした時は、すぐ無理をせず中断しましょう。
❸ 保存・開封後の取り扱いにも気をつけて
市販の介護食は常温保存OKなものや冷凍・冷蔵タイプがありますが、
基本は「冷暗所に」「開封後は早めに使い切る」。
新しい食品でも、賞味期限や異臭・変色などないかは必ずチェックしてください。
❹ アレルギーや食事制限
複数の病気や服薬がある方は特に、
塩分・糖分・タンパク制限など個別の制約に注意しましょう。
細かな疑問は、迷わずかかりつけの先生に聞いてみてください。
❺ 怒ったり落ち込んだりした時の食欲変化
高齢になると、気分や環境、体調で急に食欲が落ちたり「食べない!」と言われがち。
そんなときは量を無理に増やさず様子をみて
「間食」や「好きな味」をうまく活用してみてください。
実体験から学ぶ「うまく使いこなすコツ」
介護食を取り入れているご家族や介護スタッフさんの話でよく聞くのが
「最初は不安もあったけど、少しずつ本⼈に合う商品が見つかってきた」、
「おやつ感覚でゼリーやムースを活用したら、楽しく続けられた」という声。
使いはじめは戸惑いもありますが、いろいろなメーカーを試してみたり、
「今日はおかゆだけ市販品」など部分的にうまく取り入れることで、
ご本人も家族も気持ちにゆとりが生まれることが多いようです。
また、慣れてきたらアレンジするのもおすすめ。
例えば、市販のペースト食にゆでた野菜を加えたり、
レトルトのスープにごはんを混ぜてリゾット風にしたり。
ほんの少しのアレンジが、毎日の食事をより楽しいものにしてくれますよ。
市販介護食のメリット・デメリットを整理
ここまで特徴や選び方、注意点についてお話してきましたが、
最後に市販介護食のメリットとデメリットを整理してみましょう。
メリット
・調理の手間が大幅に減るので、介護する側の負担を軽くできる
・栄養バランスが整っており、医師や栄養士監修の商品も多い
・やわらかさや形状が明確に区分表示されていて選びやすい
・保存が利くものも多く、非常時や急な体調変化時に役立つ
・味やメニューが豊富で、食べる楽しみを広げやすい
デメリット
・毎日使うとコストがかさむ
・手作りに比べると味や香りの自由度が低い場合もある
・添加物や加工食品特有の風味が気になる方もいる
・その人の体調によっては、市販品のままでは合わないことも
大事なのは、「メリットを活かして、デメリットは工夫でカバーする」こと。
例えば、毎食ではなく朝だけ市販品を使う、好きな食材を足して味を変える、
まとめ買いでコストを抑えるなど、
生活スタイルや家族の状況に合わせた使い方をおすすめします。
あえて手作りと組み合わせる理由
「介護食=全部市販品」というイメージを持つ方もいますが、
実際には手作りと市販をうまく組み合わせるスタイルが主流です。
例えば…
・主食(おかゆややわらかご飯)は手作り、主菜(魚や肉のおかず)は市販品
・おやつや間食は市販のゼリーやムース、主食は家で調理
・調子が良い日は手作り、疲れた日は市販に頼る
こうすることで、コストのバランスも取りやすく、本人が「飽きない食事」にもつながります。
そして介護する側も「全部作らなきゃ」というプレッシャーから少し解放されます。
[PR]緊急時・災害時にも役立つ
実は市販の介護食、災害時の非常食としても活躍します。
常温で長期保存できるレトルトや缶詰タイプであれば、
停電や断水の時でも温めずに食べられるものが多いです。
普段からローリングストック(食べた分だけ新しく買い足す方法)で備えておくと安心です。
特に介護が必要な方の非常食は、普通の非常食より形状・やわらかさ・栄養が
あらかじめ調整されていることが大きな強みです。
最後に
市販の介護食は、忙しい日々の中で介護する側とされる側の両方を支えてくれる存在です。
「手作りじゃないと…」と気負う必要はまったくありません。
むしろ「元気でいてもらうための工夫のひとつ」と考えるくらいがちょうど良いと思います。
大切なのは、本人が安全に、そしておいしく食事を楽しめること。
そのための道具として、市販の介護食を遠慮なく活用してください。
「美味しい」「これなら食べられる」と思ってもらえたら、
毎日の食事時間が「大変な作業」から、
「ちょっとホッとできる時間」へと変わるきっかけになって
あなたの介護生活がきっとグッとラクになるはずです。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 厚生労働省「高齢者の食事と栄養管理」
- 農林水産省「高齢者向け食品の活用と選び方」
- 介護ポストセブン「市販の介護食どんな味?見た目は?親に食べて欲しいのはどれ?」
- そふまる「市販の介護食の選び方と活用メリット」
- 本当に美味しいの?レトルトの介護食 キューピー 歯ぐきでつぶせる実食レビュー


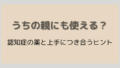


コメント