こんにちは。
介護のことを家族で話し合いたい。
でも、話し合えば話し合うほど、ギスギスしてしまう…。
「自分ばかりが大変な気がする」「本音を言ったら責められそう」
そんな思いから、会議の空気がどんよりしてしまうことはありませんか?
実は、家族会議がうまくいかないのには共通した“つまずきポイント”があります。
まずはその原因を知ることが、改善の第一歩です。
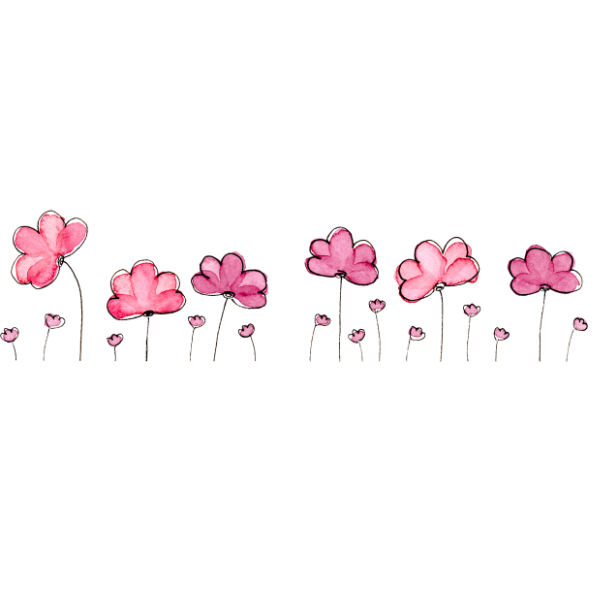
家族会議がうまくいかない…よくある悩みと原因
感情が優先されてしまう
「私はこんなに頑張ってるのに…」
「どうしてもっと早く相談してくれなかったの?」
介護の話題には、これまでの関係性や積み重なった感情がどうしても影響します。
本音で語り合いたいはずが、気づけば過去の不満をぶつけ合う場に変わってしまうことも。
目的が曖昧なまま始めている
「何を決めたいのか」がはっきりしていないと、話し合いは堂々巡りになりがちです。
・今後、介護サービスを使うかどうか
・誰がどれだけ関わるか
・施設入所のタイミングについて
こういった目的を、会議の冒頭で共有しておくことが重要です。
立場や情報の格差がある
すでに介護に関わっている人と、離れて暮らしている人では、状況の把握に差があります。
「親は元気そうに見えるけど?」「そんなに深刻だったの?」
そうしたズレが、話し合いの温度差につながってしまうのです。
失敗しないための事前準備
目的と議題を明確にしておく
「今日はこれを話し合いたい」と、事前に参加者へ伝えておきましょう。
・介護サービスの種類と導入タイミング
・金銭的な分担
・親の意向をどう反映するか
ゴールが見えるだけで、会議の方向性が安定します。
必要な情報を整理しておく
具体的な資料やデータがあると説得力が増し、感情論だけになりません。
・要介護認定の結果や主治医の意見
・施設のパンフレットやサービスの説明資料
・介護保険の限度額や使える制度の一覧…など
参加者の予定と環境を整える
忙しい中での会議にならないよう、日時や場所を調整しましょう。
子どもがいる時間帯、疲れている夜間などは避け、
落ち着いて話せるタイミングを選ぶのがコツです。
親の気持ちを事前に聞いておく
本人抜きで方針を決めようとすると、後で信頼関係にヒビが入ることも。
会議の前に、親自身が「どうしたいと感じているのか」を聞いておくことで、
全体の方向性が見えやすくなります。
[PR]話し合いをスムーズに進めるための工夫
話す順番を決めて、全員の声を聞く
「いつも同じ人ばかりが話して、他の人が口を挟めない」
そんな空気になってしまうと、意見が偏ってしまいます。
発言しやすい雰囲気を作るためにも、
最初に「一人ずつ順番に話そう」と提案しておくのがおすすめです。
誰かが話している間は口を挟まず、まずは“聞くこと”に集中するルールを設けるだけで、
会議の質が大きく変わります。
否定しない・評価しない
話し合いでは、つい「それは甘いよ」「そんなの無理だよ」と言ってしまいがち。
でも、相手の言葉を否定されると、心を閉ざしてしまいます。
まずは「そう思ったんだね」と受け止めた上で、「私はこう思うよ」と、
自分の考えを伝えるようにしましょう。
メモを取りながら進める
話があちこちに飛ぶのを防ぐために、誰かが進行役を兼ねてメモを取りながら進めましょう。
ホワイトボードやノート、スマホのメモアプリなど、
みんなが視覚的に確認できるようにするのがポイントです。
「今、何の話をしているか」「決まったことは何か」が見えると、脱線しにくくなります。
感情的になったら一旦休憩を
家族同士だと、つい感情が爆発してしまうことも。
そんな時は無理に続けず、「一度休憩しようか」「今日はここまでにしよう」と、
冷却期間を挟む勇気も大切です。
休憩を挟むことで、お互いに気持ちを整理しやすくなり、次の話し合いが前向きになります。
[PR]実際の成功例から学ぶ
成功例①:兄妹での役割分担を可視化したケース
三人兄妹での家族会議。
最初は「誰がどれだけ介護するか」で揉めそうになりましたが、
紙に「できること」「できないこと」をそれぞれ書き出したことで、
意外とすんなり役割分担が決まりました。
・Aさん(長女):平日の送迎とデイサービス対応
・Bさん(長男):経済的支援と定期的な電話連絡
・Cさん(次女):緊急時の対応とケアマネとの連携
目に見える形で整理すると、「みんなそれぞれ頑張ってる」と認識しやすくなります。
成功例②:ケアマネジャーの同席で冷静な話し合いに
長年介護を担っていた妹が限界を感じていたものの、
兄は「大げさだ」と取り合ってくれず、話が平行線。
そこで、ケアマネジャーに会議へ同席してもらったところ、第三者の視点で
「今の介護状況の大変さ」や「必要な支援策」を説明してくれました。
話し合える関係をつくるために大切なこと
完璧な答えを求めすぎない
介護の話し合いは、「これが正解!」という明確なゴールがあるわけではありません。
誰か一人が我慢してもダメ。
親の意向だけでも成り立たない。
全員が少しずつ歩み寄って、現時点での“ベスト”を見つけていく。
そんな柔軟な視点が求められます。
小さな「ありがとう」を伝える
「先週の会議、参加してくれてありがとう」
「〇〇の資料、用意してくれて助かった」
そんな一言があるだけで、家族の間にあたたかさが生まれます。
感謝は伝えなければ伝わりません。
だからこそ、意識的に言葉にすることが大切です。
定期的に話す機会をつくる
一度話し合って終わりではなく、「変化があれば、また話そうね」というスタンスが理想的です。
介護は日々変化していきます。
月に1回、半年に1回でもいいので、定期的に振り返る時間を設けることで、
「悩みをためない」仕組みができます。
[PR]最後に
介護の話し合いがうまくいかない背景には、感情・立場・情報のズレがたくさんあります。
でも、そのひとつひとつを丁寧にほどいていくことで、ただの会議ではなく、
「これからの人生を一緒に考える時間」へと変わっていきます。
決して、うまくまとめようとしなくても大丈夫。
感情的になってしまっても、やり直せます。
大切なのは、「話してみよう」「聞いてみよう」と思い続けること。
一人で抱え込まず、つながりながら、少しずつ前に進んで下さいね。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 厚生労働省「家族介護者支援の手引き」
- NHKハートネット「介護と家族関係のすれ違い」
- 一般社団法人日本老年医学会「高齢者とその家族の意思決定支援」
- 公益財団法人さわやか福祉財団「介護における家族のコミュニケーションガイド」

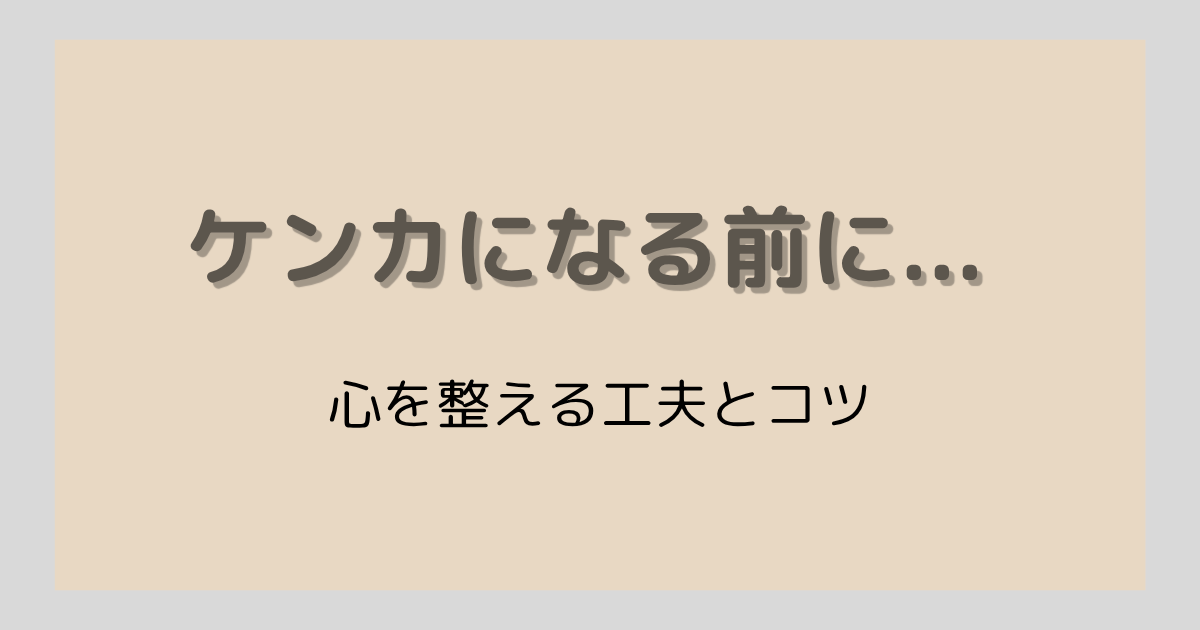

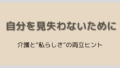


コメント