こんにちは。
「学校と介護、どちらもがんばらなきゃいけないなんて、正直きついよ…」
これは、実際に祖母の介護をしている高校2年生の男の子がぽつりとこぼした言葉です。
私たちがイメージする“介護を担う人”といえば、
30代以上の家族や、現場で働く介護職員かもしれません。
でも、実際には10代の若者、特に中学生や高校生が介護を担っているケースも少なくありません。
こうした子どもたちは「ヤングケアラー」と呼ばれ、社会的な注目が高まりつつあります。
本記事では、学校生活と介護を両立している中高生たちのリアルな実情、感じている葛藤、
そして支援のあり方について、丁寧に掘り下げていきます。
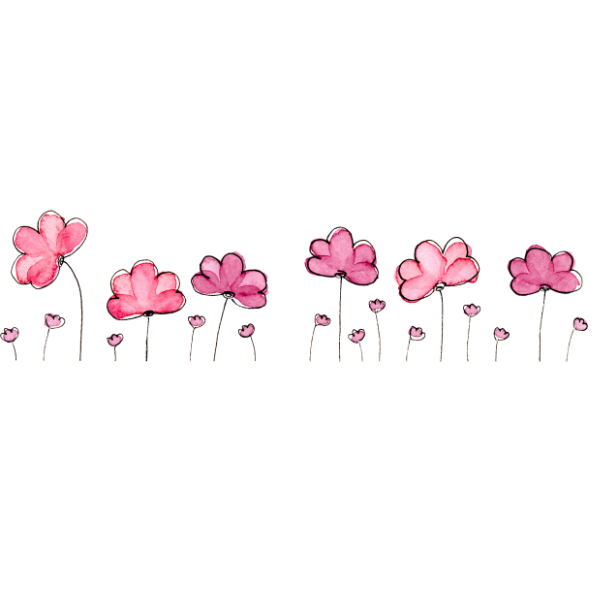
ヤングケアラーとは?
ヤングケアラーとは、家族の介護や世話を日常的に行っている18歳未満の子どもを指す言葉です。
具体的には、以下のようなことを日常的に担っている場合に該当します。
・食事の準備や掃除、洗濯などの家事
・病院への付き添いや薬の管理
・入浴や排せつの介助
・認知症の親や祖父母の見守り
一見「親孝行」「いい子」と評価されがちですが、子どもとしての時間や学びの機会、
遊ぶ権利が奪われてしまう側面もあります。
2020年の厚生労働省の調査では、中学生のおよそ17人に1人、
高校生のおよそ24人に1人がヤングケアラーに該当するとされています。
これは、想像以上に多い数字です。

ある高校生の一日:朝から介護が始まる
たとえば、高校1年生のAくんの一日を見てみましょう。
朝5時半に起きて、祖母に朝ご飯を作り、トイレの介助と着替えを手伝います。
その後、自分の支度を済ませて7時過ぎには家を出て登校。
放課後は部活に出られない日が多く、急いで帰宅して夕飯の準備。
母親はパートで遅くまで働いているため、祖母と二人きりの時間が長く続きます。
「友達がうらやましいって思うときもある。
でも、ばあちゃんが好きだから、がんばれる」とAくんは語ります。
周りの友達に話すこともなく、先生にも「うちは大丈夫です」
とつい笑顔で言ってしまう彼のような子は、少なくないのです。
「普通の学校生活」とは何か
部活に励み、恋をして、放課後に友達とコンビニに寄る…。
そんな「普通の学生生活」を、ヤングケアラーの子どもたちはどこか遠くに感じています。
「文化祭の準備で遅くなって、祖母のおむつ替えが間に合わなかった」
「進路相談の時間に介護の話をするのが恥ずかしい」──。
そんな心の葛藤が、10代の小さな胸に積み重なっていきます。
学校側が状況を把握していないと、本人の学力や生活面での悩みに気づきにくく、
孤立を深める要因にもなりかねません。
進路に悩むヤングケアラーたち
介護を担う中高生にとって、進路選択も一筋縄ではいきません。
「大学に進学したいけど、家を離れられない」
「介護のことを考えると、地元の短大か就職しか選べない」
こんなふうに、将来の夢ややりたいことよりも“家の事情”が優先されてしまうこともあります。
本来であれば、進路選びは「自分の未来」に集中すべき大切な時間。
でも、ヤングケアラーは“家庭の柱”としての責任も感じており、
自分の希望を飲み込んでしまうケースが少なくありません。

心の中にある「誰にも言えない悩み」
中高生という思春期の子どもたちにとって、
「家族の介護をしている」と話すことはとても勇気のいることです。
「かわいそうって思われるのが嫌」
「変な目で見られたくない」
「親のことを悪く言ってるみたいで申し訳ない」
そんな気持ちがあるからこそ、学校では明るくふるまい、
何もなかったかのように日常を過ごしている子も多いのです。
心の奥にしまい込んだまま、誰にも相談できずに抱えるストレス。
そんな日々が長く続けば、やがて心と体のバランスを崩してしまうこともあります。
「家庭内だけ」で完結しがちなケア
日本の家庭では「身内の介護は家族でなんとかするべき」
という考え方がまだまだ根強く残っています。
そのため、ヤングケアラーがいても
「親が頼りすぎてるだけ」「甘やかしている」と受け止められてしまうことも。
制度的にも、子どもが担う介護に対する具体的な支援策はまだ十分とは言えません。
結果として、家庭内で子どもが“介護要員”のような扱いになってしまい、
サポートが届かないまま年単位で続いてしまう現実があります。
周囲の大人ができること
では、私たち大人に何ができるのでしょうか?
一番大切なのは、「気づくこと」と「声をかけること」です。
たとえば…
・朝から疲れている様子の子に「大丈夫?」と声をかける
・家庭の事情を聞いたら否定せず、共感して受け止める
・学校や地域の相談窓口にそっとつないであげる
「あなたが悪いわけじゃないよ」
「助けを求めてもいいんだよ」
そんな言葉をもらえるだけで、心が少し軽くなることもあるのです。
支援は、特別なスキルや制度がなくてもできます。
ほんの小さな気づきと、あたたかいまなざしから始まります。
社会全体でヤングケアラーを支えるために
ヤングケアラーの存在が社会に広く知られるようになったのは、ここ数年のこと。
2021年には厚生労働省が全国調査を行い、支援の必要性がようやく本格的に議論され始めました。
自治体によっては、ヤングケアラー専用の相談窓口や支援制度を設けているところもあります。
学校と福祉が連携して、子どもたちのSOSを見逃さない体制づくりが少しずつ進んでいるのです。
とはいえ、まだ支援の手は十分に届いているとは言えません。
特に中学生や高校生は「子どもだから話せない」「我慢するのが当然」
と思い込んでしまいがちです。
その壁を少しでも取り除くためには、まず大人たちが「ヤングケアラー」という存在を知り、
偏見なく受け止め、声をかけることが大切です。
本人の声を拾い上げる大切さ
「もっと早く誰かに言えてたら、勉強も部活も頑張れたと思う」
「自分のことを気にかけてくれる大人がいるだけで、気持ちが全然違う」
これは、実際に支援につながったヤングケアラーたちの言葉です。
一人で抱え込んでいた苦しさ、日常の中にあった小さなSOS。
それを誰かが拾い上げてくれたことで、ほんの少しずつでも前を向くことができたのです。
彼らは決して「かわいそうな存在」ではありません。
家族のことを思い、懸命に毎日を生きている、強くて優しい子どもたちです。

最後に:やさしい社会の一歩に
この記事を読んでくださったあなたが、もしかしたら学校で、地域で、
そんな子どもたちに出会うことがあるかもしれません。
そのとき、「大丈夫?」と声をかけられる大人であってほしいと思います。
「一緒に考えようか」と言ってあげられる環境が、あたりまえになってほしいと思います。
ヤングケアラーの問題は、誰か一人が頑張っても解決できるものではありません。
でも、誰か一人の気づきが、誰か一人の人生を変えることはあるのです。
学校と介護を両立する中高生たちに、どうかあたたかい視線を。
そして、彼らが「自分らしい未来」を選んでいける社会を、
少しずつでもみんなでつくっていきたいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
参考
- 厚生労働省「ヤングケアラーの実態に関する調査結果」
- 文部科学省「学校におけるヤングケアラー支援に関する通知」
- 東京都福祉保健局「ヤングケアラーを支える地域の取り組み」
- 公益社団法人 子ども情報研究センター「ヤングケアラーの心理的支援」
- NHKスペシャル「見えないケア~10代の介護者たち~」
- 朝日新聞デジタル「ヤングケアラー 特集記事(2023年)」
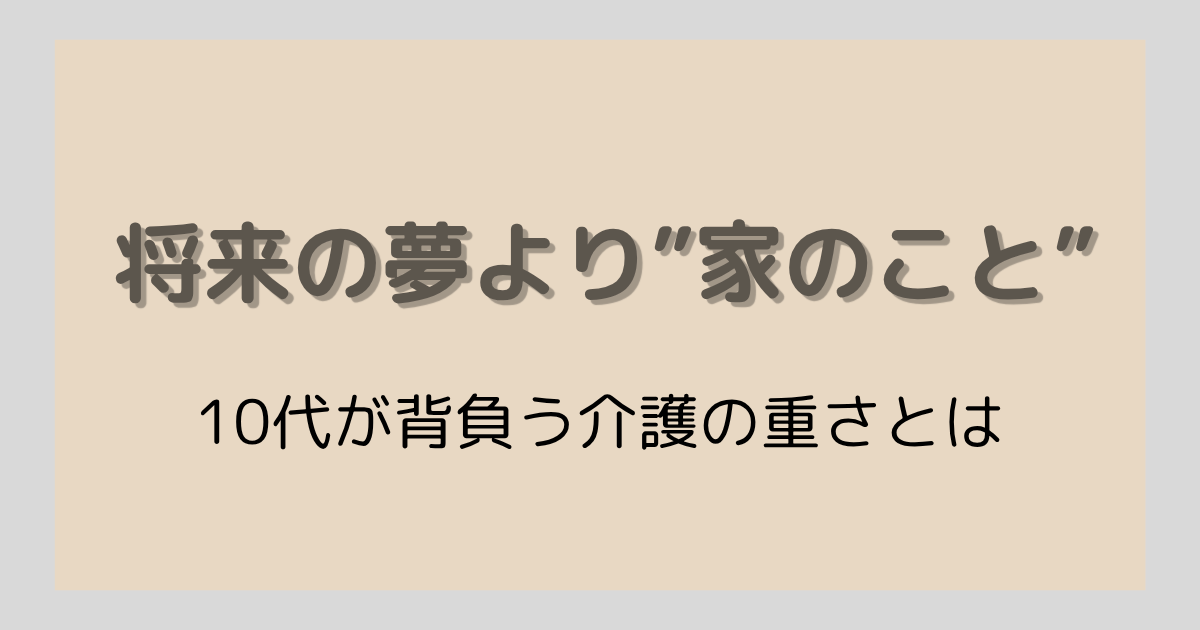
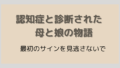


コメント