こんにちは。
在宅介護や家族介護が長く続くと、どうしても生活の中心が「介護」になってしまい、
自分自身のことを後回しにしがちになります。
「趣味なんてやってる場合じゃない」「遊んでる余裕なんてない」
と思っている方も多いかもしれません。
でも実は、“趣味を続けること”は、介護生活を乗り越えるための大切なエネルギー源なんです。
今回は、介護をしながら趣味を楽しむことがどうして心に良い影響を与えるのか、
そしてどんな工夫をすれば無理なく続けられるのかを、やさしい視点でご紹介します。
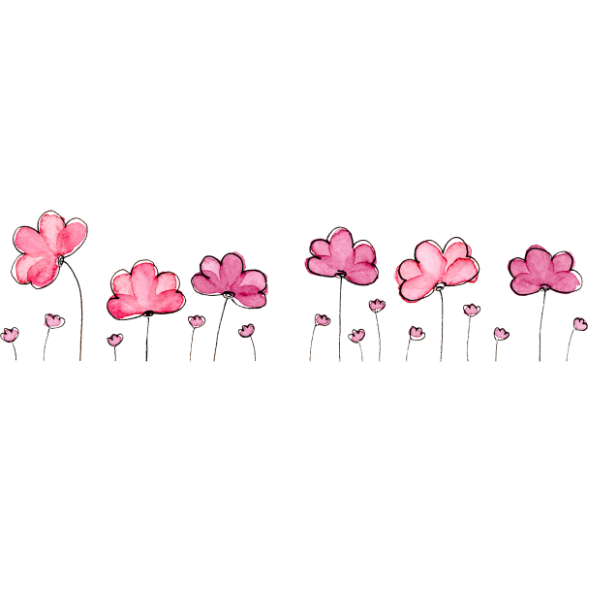
なぜ介護ストレスはたまりやすい?
介護は、身体的にも精神的にも負担の大きい役割です。
たとえ家族のためとはいえ、毎日休みなく続けていれば、ストレスが溜まって当然です。
・自分の時間がなくなる
・相手の感情に振り回される
・社会とのつながりが減る
・常に“責任感”に追われる
こうした環境に長く身を置いていると、「何をしていても気が休まらない」
「自分がどんどんすり減っていく」と感じるようになってしまいます。
趣味にはストレスを和らげる力がある
そんな介護生活の中で、「趣味の時間」が果たす役割はとても大きいのです。
趣味とは、「好きなこと」「夢中になれること」「自分のペースでできること」。
その時間は、介護という緊張感のある毎日から、
ほんの少しだけ“心を解放してくれる特別な時間”になります。
・脳がリフレッシュし、思考が前向きになる
・「自分らしさ」を思い出せる
・自己肯定感が高まる
・「今日もこれができた」と思える達成感
短時間でも、週に1回でもいい。
趣味を通して、自分にごほうびの時間をあげることが、
ストレスを減らし、介護を続ける原動力になります。
「罪悪感」を手放そう!
「趣味を楽しんでるなんて、不謹慎だと思われないかな…」
「自分だけ好きなことをして、申し訳ない気がする…」
そんな罪悪感が、介護中の趣味の時間を遠ざけてしまうこともあります。
でも、あなたが元気で、笑顔で、ストレスを抱えずにいられることは、
介護を受ける相手にとっても嬉しいことなんです。
そして何より、あなたには、自分の人生を楽しむ権利があります。
・「趣味の時間=介護を放棄すること」ではない
・周囲の理解が得られない時は、信頼できる人に気持ちを話してみよう
・「この時間があるから頑張れる」と思えることが、継続の力になる
介護の合間にこそ、心をほぐす時間を作っていいのです。
実際にどんな趣味が続けやすい?
趣味といっても、大掛かりなことをする必要はありません。
介護の合間にできる“ちょっとしたこと”も立派な趣味です。
ここでは、介護中でも取り入れやすい趣味をいくつかご紹介します。
・読書:好きなジャンルの本を1ページ読むだけでも気分転換に。
電子書籍なら場所を選ばず便利です。
・ガーデニング:小さな鉢植えでもOK。土に触れることは癒し効果が高いといわれています。
・手芸・編み物:無心で手を動かすことで、心が落ち着く人も多いです。
・音楽:お気に入りの曲を流す、歌う、楽器を触るなど、気軽に始められます。
・日記やエッセイ:その日の思いや出来事を書くだけで、心の整理になります。
・料理・お菓子作り:「今日は自分のために作る」そんな時間も大切な趣味になります。
[PR]時間がなくても趣味はできる?
「趣味の時間なんて取れないよ…」という声もあると思います。
実際、介護に追われていると、1日のスケジュールに余裕がない方も多いはず。
でも、大切なのは「趣味の時間を確保すること」ではなく、
「趣味的な思考を日常に少しだけ混ぜること」なんです。
「たったこれだけ?」と思うような小さな工夫が、
積もり積もって大きなストレス軽減につながっていくのです。
趣味とは、大きなものでなくていいんです。
誰かに認められる必要もなく、成果を出す必要もありません。
「これをやってる時、少し気持ちがやわらぐ」 そんな小さな「好き」の時間を、
どうか手放さないでください。
介護という大変な毎日の中で、自分を大切にすることは必要なことです。
趣味がある人の介護は、なぜ続けやすい?
介護の長期化が進むなかで、「続けられる介護」を意識することはとても大切です。
その視点で見ると、「趣味を持っている人」は介護の継続力が高いというデータもあります。
なぜなら、ストレスを上手に解消できる“出口”を持っているから。
・気分転換ができる → 感情的になりにくい
・心に余裕が生まれる → 相手にやさしく接しやすくなる
・自分のペースを大切にできる → 燃え尽きにくくなる
これは、介護される側にとっても大きなメリットです。
あなたの穏やかさや笑顔が、そのまま相手の安心感につながるからです。
周囲とのつながりが生まれる
趣味には、“ひとりで楽しむ”だけでなく“誰かとつながる”という面もあります。
例えば、趣味を通じて知り合った人とSNSでやり取りをしたり、地域のサークルに参加したり。
介護で孤立しやすい中、「自分は介護だけの人間じゃない」と感じられる瞬間は、
心をとても軽くしてくれます。
外に出ることが難しいときも、今はオンラインでつながれる時代。
“趣味仲間”との小さな交流が、日常の励みになります。
[PR]最後に
介護のストレスは、決して「我慢」や「根性」で乗り越えられるものではありません。
だからこそ、自分のための時間、自分のための趣味を持つことが、
介護者自身を守る大きな支えになるのです。
あなたが「少し楽になれた」と思える時間は、
きっと介護される方の笑顔にもつながっていきます。
どうか、「好きなこと」をあきらめないでくださいね。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 公益社団法人 認知症の人と家族の会「介護ストレスを和らげるヒント集」
- 厚生労働省「介護者のストレスとメンタルヘルス対策について」
- 国立精神・神経医療研究センター「介護者のうつ傾向と支援の必要性」
- 厚生労働省「家族介護者支援マニュアル」(家族介護者のストレスと支援)
- 厚生労働省「同居の主な介護者の悩みやストレスの状況」(調査結果)

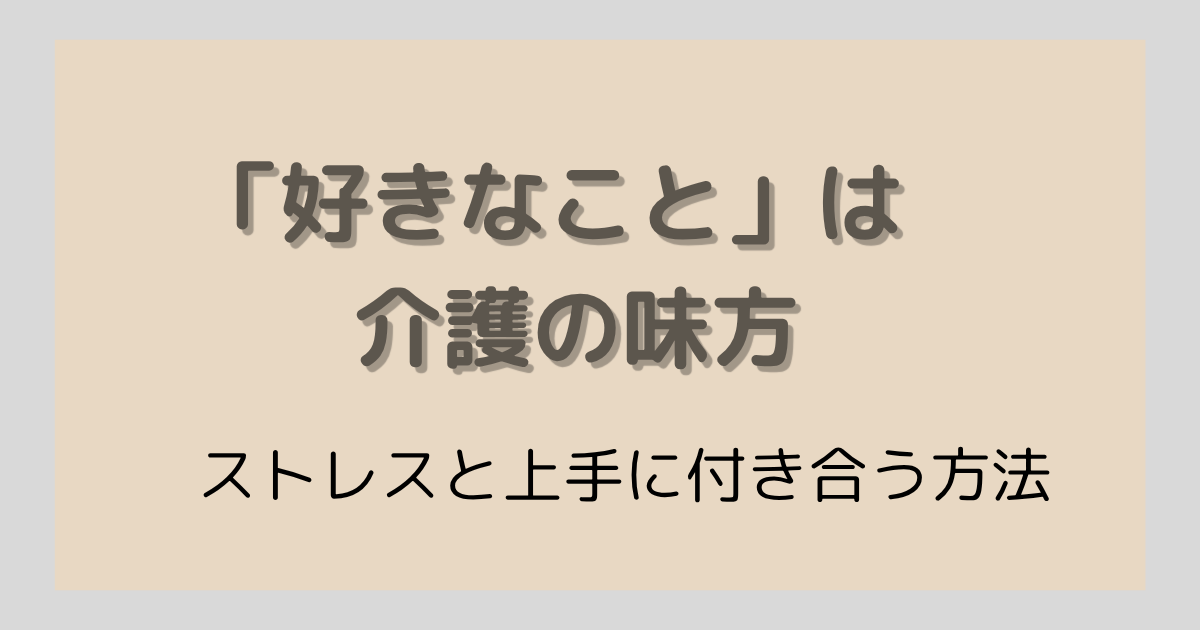

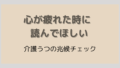


コメント