こんにちは。
在宅で介護をしていると、多くの方がぶつかるのが「夜の見守りどうするか」という問題です。
昼間はデイサービスやヘルパーさんが来てくれることもあって、なんとか一息つける方もいます。
でも夜は…家族だけで向き合うことが多いんですよね。
夜間の見守りは、ただでさえ体力や心が削られる在宅介護の中でも、
とくに大きな負担になりやすい部分。
在宅介護は“24時間体制”になりがちですが、人間の体は休息なしには持ちません。
だからこそ、夜間の安全をどう守りつつ、介護者自身の睡眠を確保するかがとても大切なんです。
この記事では、「夜間の見守りをどうしたらいいのか?」という悩みに寄り添いながら、
介護者の睡眠をしっかり守るためのテクニックをご紹介します。
少しの工夫でその負担をやわらげたり、睡眠時間を確保できることもあるんです。
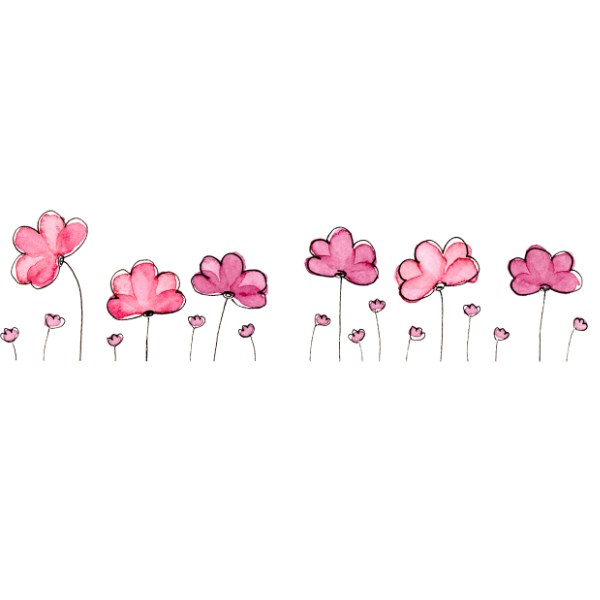
なぜ「夜間の見守り」が大きな課題になるの?
日中は起きている時間帯なので、「何かあってもすぐ気づける」という安心感がありますよね。
ところが夜は、介護している人も眠らなければならない時間。
介護される人が徘徊したり、トイレに立ったり、呼吸が苦しそうにしていたりしても、
気づけないことがあります。
・認知症による夜間の徘徊
・トイレに行くときの転倒リスク
・持病の発作や体調の急変
・夜中に動き出してしまう不安
「何かあったらどうしよう」という不安から、介護者は眠りが浅くなり、
結果的に体力も気力も削られてしまいます。
翌日も介護が待っているのに、寝不足でヘトヘト…という悪循環に陥ってしまうんです。
介護者も眠っていいんです!
「夜ぐっすり寝てしまったら、母に何かあった時に気づけないんじゃないかと思って、
結局ほとんど寝られないんです」
この気持ち、とてもよくわかります。
でも、介護者が長く元気に介護を続けるためには、睡眠は必須。
「自分が眠る=見守りをサボっている」ことにはならないんです。
つまり、大切なのは「安心して眠れる仕組み」をどう作るか、ということなんです。
[PR]まずは“安心”を準備しよう
私たちが夜眠れないのは、実は「もし〇〇が起きたら…」という不安に心がとらわれているから。
だから最初のステップは、「何が不安なのか」をはっきりさせることなんです。
例えば…
・夜中のトイレのとき、転んでしまうのが不安
・徘徊して外に出てしまうのが不安
・寝ている間に呼吸が止まるのが不安
このように、“心配ごとを具体的にする”だけで、対策が選びやすくなります。
「ただなんとなく不安」よりも、「このケースに備えたい」という形に落とし込めると、
安心への第一歩につながります。
夜間見守りの工夫アイデア
それでは、実際にどんな工夫ができるのかを紹介しますね。
今回は、大きく4つの方向で考えてみます。
① 環境を整える(物理的な転倒・徘徊リスクを減らす)
② 見守りを助ける道具を使う(センサー・カメラ・モニターなど)
③ サービスを利用する(夜間訪問介護やレスパイト(ショートステイ))
④ 介護者本人の休息ルールを作る
こうした工夫を少しずつ取り入れることで、
「夜もちゃんと眠っていいんだ」という自信につながります。
[PR]①環境を整える工夫
まず取り組みやすいのが、夜間の環境調整です。
例えば…
・足元に小さな常夜灯を置く(眩しすぎないオレンジ系ライトがおすすめ)
・廊下に手すりをつける(夜中の歩行をサポート)
・トイレまでの動線に段差マットを置く(つまずき防止)
・ベッドガードをつける(転落防止)
こうした小さな工夫が、「夜動いても大丈夫かも」という安心感を与えてくれます。
これだけでも、介護者が眠りやすくなるケースは多いんですよ。
②見守りを助ける道具を使う
近年は、在宅介護を支える便利な見守りグッズがたくさん出ています。
「こんなのまであるの!?」と驚くようなアイテムも。
うまく取り入れることで、
介護者がベッドから飛び起きなくても安心できる仕組みを作ることができます。
代表的な見守りアイテム例
・ベッドセンサー…マットレスの下に入れて、起き上がりや心拍・呼吸の変化を感知
・人感センサーライト…夜中に歩き出すと自動で点灯し、転倒防止に役立つ
・ドア開閉センサー…玄関や部屋のドアに設置し、徘徊で外に出る動きを知らせてくれる
・カメラ・ベビーモニター…寝室を別にしていても、スマホから様子を見られる
特に「ベビーモニター」は、
赤ちゃんの見守り用として市販されているものを介護にも応用できます。
赤外線カメラや音声通話機能がついたものを使えば、夜間の見守りがぐんと楽になりますよ。
機器を導入するときのポイント
・カメラを付ける場合は、ご本人に必ず説明をして納得してもらうこと
・アラーム音が大きすぎると逆に介護者の眠りが浅くなるので、振動やスマホ通知式がおすすめ
・導入費用だけでなく、「毎日安心して過ごせる価値」があるかで考える
「機械に頼るなんてどうなのかな…」と感じる方もいらっしゃいますが、
実際に使い始めると「もっと早く導入すればよかった」という声も多いんです。
介護者が安心して眠れる時間を増やすことは、ご本人にとってもプラスになりますよ。
[PR]③サービスを利用する
もう一つの大事な選択肢が「サービスをうまく使うこと」です。
「家族だけで全部やらなきゃ」と思い込むと、本当に追い詰められてしまいます。
夜間こそ、外部のサービスに助けてもらうことで息抜きができます。
夜間対応の介護サービス例
・夜間訪問介護(排泄介助や体位交換などを自宅で行ってくれる)
・定期巡回・随時対応サービス(必要時に訪問してもらえる仕組み)
・ショートステイ(お泊りサービス)(介護者の休養のために数日預かってもらえる)
・看護師による訪問(医療的な管理が必要な方に対応可能)
夜中に誰かが来てくれたり、気になったら駆けつけてもらえるサービスがあるだけで、
「自分ひとりで背負っているわけじゃない」という安心感が得られます。
結果的に介護者の眠りも深くなるんですよ。
サービスを使うと罪悪感がある?
多くのご家族が「他人に夜までお願いしていいのかな」「自分が頑張らなくちゃ」と迷います。
でも、無理をして介護者が倒れてしまったら、本当の意味で誰も幸せになれません。
サービスを使うことは、“家族みんなの生活を守る手段”なんです。
地域包括支援センターやケアマネジャーさんに相談すると、
「夜だけ利用できるデイサービス」や「短期間のショートステイ」など、
地域ごとの制度を教えてくれるはずです。
[PR]④介護者本人の休息ルールを作る
最後に忘れてはいけないのが「介護者自身が休むルールを作ること」です。
どんなに便利な道具を使っても、どんなに環境を整えても、
介護者が「いつでも自分が起きていなきゃ」と思っていたら眠れませんからね。
休息ルールの例
・夜10時以降は“見守りは機械に任せる”と割り切る
・「自分の睡眠=相手の安心につながる」と意識する
・眠りやすい環境(遮光カーテン、アロマ、リラックス音楽など)を整える
・交代できる家族がいれば“当番制”にしてみる
「よし、今日はここから先は私の休憩時間!」
そう決められることで、ようやく心も体も休める態勢に入れるんです。
睡眠不足を和らげるセルフケア
どんなに工夫をしても、どうしても夜中に起きざるを得ないことはあります。
そんな時に役立つのが「短時間でも回復できるセルフケア」です。
お昼寝を味方にする
「昼寝はだらけてるみたいで罪悪感がある」という方もいますが、実は昼寝は効率的な回復方法。
15〜20分の軽い昼寝は“脳と体のリフレッシュ”にぴったりです。
逆に1時間以上深く眠ってしまうと、かえってだるさを感じてしまうので注意しましょう。
呼吸法で心を落ち着ける
夜中に起こされると、頭が冴えてしまってその後眠れないことがありますよね。
そんな時は、「吸う:吐く=1:2」のリズムで呼吸を整えるとリラックスしやすくなります。
寝付けないまま無理に布団に入っていると余計に焦ってしまうので、
いったん起きて白湯を飲んだりストレッチをするのも効果的です。
「一人で背負わない」が最大のセルフケア
睡眠不足に悩む介護者さんに伝えたいのは、
「介護を自分だけで完璧にしようと思わなくていい」ということ。
少しでも不安を軽くする工夫やサービスを利用すること、それ自体が大切なセルフケアです。
夜間の見守りは、在宅介護をする上で避けて通れないテーマ。
でも「介護者が眠ること=無責任」ではありません。
むしろ介護を長く続けるためには「介護者もぐっすり眠ること」が必要不可欠です。
今回お伝えした工夫はどれも「少しずつ取り入れられることばかり」です。
いきなり全部は難しいかもしれませんが、
「これならできるかも」というものから試してみてください。
夜眠れる時間が少しでも増えると、心も体もぐんと軽くなりますよ。
[PR]最後に
在宅介護の中で、「眠ること」への罪悪感を抱えている人は少なくありません。
でも、介護者が眠れないことは、誰のためにもなりません。
「介護者が眠ることは、介護を投げ出すことではなく、守り続けるための大切な力になる」
この言葉を胸に、今日からできる小さな工夫を始めてもらえたら嬉しいです。
また、在宅介護の夜は、本当に長くて孤独に感じることがあると思います。
でも、同じように工夫を重ねて介護を続けている人がたくさんいます。
どうか自分の眠りも大切にしながら、無理のないペースで介護を続けてください。
安心して夜を過ごすことができる工夫をすることは、あなたがあなたでいるために、
とても大切なケアなんです。
あなたの体も、気持ちも、やさしく守れますように。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 「介護で睡眠不足に!在宅介護でゆっくり眠れない場合の対策を解説」イチロウ
- 「夜間の見守り介護にお悩みなら」訪問看護ヘルパーのクラウドケア
- 「健康づくりのための睡眠ガイド2023」厚生労働省
- 「夜間対応型訪問介護とは?在宅介護用サービスのメリットと注意点」イリーぜ

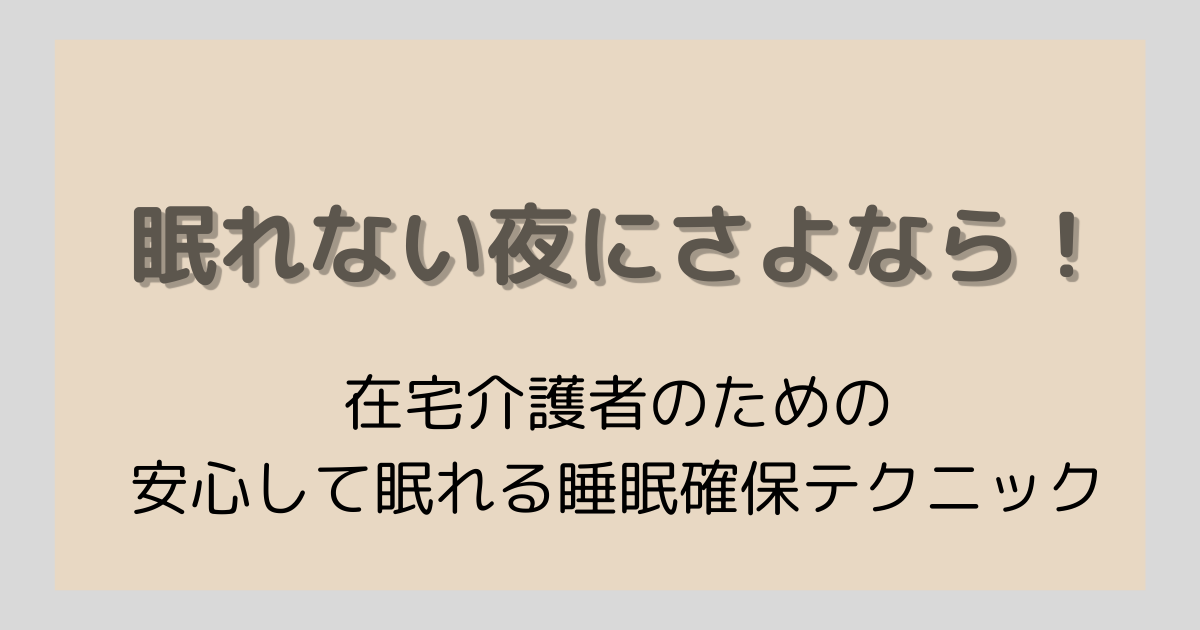



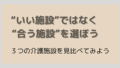

コメント