こんにちは。
「親の介護、家で続けるべきか、それとも施設にお願いした方がいいのか…」
この悩みは、介護に関わる人なら一度はぶつかるもの。
正解がないからこそ、悩みは深くなりますよね。
でも、ひとつ言えるのは「どちらが正しいか」ではなく、
「どちらがその人と家族に合っているか」が大切だということ。
この記事では、在宅介護と施設介護のそれぞれの特徴を整理しながら、
「どうやって判断すればいいか」を分かりやすくご紹介していきます。
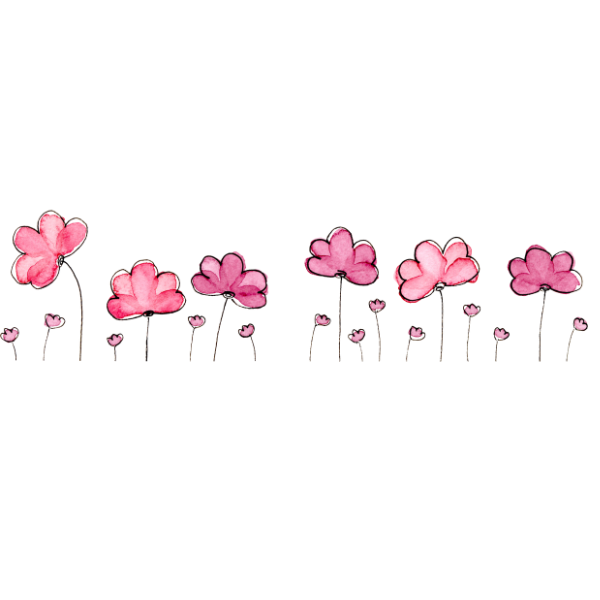
在宅介護が向いているケースとは?
まずは「やっぱり家で…」と考えている方に向けて、
在宅介護が向いているケースを整理してみましょう。
家族のサポート体制が整っている
在宅介護は、家族の負担が大きくなりやすいもの。
でも、周囲に協力してくれる家族がいたり、
近くに住んでいるきょうだいが分担できるような場合は、無理なく続けやすくなります。
また、介護保険のサービスをうまく使えば、
「家でみる=すべてを自分でやる」ではありません。
[PR]本人が「家がいい」と強く希望している
「自分の家じゃないと落ち着かない」という高齢者は多いです。
特に認知症の方にとっては、慣れた環境にいることが安心感につながることも。
本人の気持ちがしっかりしていて、「ここで暮らしたい」という希望があるなら、
それを尊重する形で在宅を選ぶのもひとつです。
症状や介護度が比較的軽い
介護度が要支援〜要介護1〜2あたりの場合、生活全般を一人で送れる場面も多く、
家での介護が現実的なケースが多いです。
とはいえ、要介護度が低くても、夜間の見守りが必要な場合や、
家の中の段差やトイレの場所が使いにくいといった事情があれば、
在宅での対応が難しくなることもあるので、環境面の確認も大事です。
[PR]介護保険サービスをフル活用できる
訪問介護やデイサービス、福祉用具のレンタルなど、在宅を支える制度はたくさんあります。
「プロの手を借りながら、家族も関われる」
そんなバランスが取れるのが理想ですね。
施設介護が向いているケースとは?
「家ではもう無理かもしれない…」と感じたとき、ご自分を責める必要はありません。
施設介護には、在宅では難しいケアを専門的におこなえるというメリットがあります。
介護度が高く、医療的ケアが必要
要介護3以上になってくると、日常生活の多くを支える必要が出てきます。
食事介助や排泄介助、移乗、褥瘡(じょくそう)の予防など…
すべてを家族で対応するのは限界があります。
また、たんの吸引や胃ろうなど、医療的なサポートが必要な場合は、
在宅での継続が非常に困難になるケースも。
家族に介護の負担が集中している
ひとりの家族がすべてを背負っていると、体力的にも精神的にも限界がきます。
「つい怒ってしまう自分がイヤ」
「何もかも投げ出したくなる」
そう感じたときは、施設という選択肢が家族の命綱になります。
「親のためにがんばらなきゃ」も大事。
でも、「自分を大切にする」ことも、同じくらい大切です。
本人が施設の生活に前向き
「みんなと一緒に暮らすのも悪くないかも」
「施設に入って、子どもに迷惑かけたくない」――
そんな言葉をお父さんやお母さんが口にすることはありませんか?
年を重ねる中で、家族に遠慮する気持ちや、
自立を保ちたいという思いが出てくる方も多いんです。
施設では、同年代の仲間と話したり、リハビリを受けたりと、
新しい刺激を得られることも。
そうした環境が元気を引き出すケースもあります。
[PR]家の構造や環境が不便
築年数の古い一軒家や、段差の多い住宅では、
高齢者にとって日常生活が危険と隣り合わせになることも。
玄関までの階段、2階にしかないお風呂やトイレ…。
バリアフリーにリフォームするのが難しい場合、施設のほうが安全に暮らせることがあります。
介護者が働いていて日中の見守りが難しい
共働き家庭や一人親家庭など、介護者が外で働かざるを得ない場合、
在宅での見守りには限界があります。
「ひとりにしている時間が心配」
「仕事中も気が気じゃない」――
そんな不安を抱え続けるよりも、
24時間体制で見守ってくれる施設を選ぶことで、安心できることもあります。
判断のポイント5つ
ここまで、在宅と施設の特徴を見てきました。
では、実際にどうやって「うちはどちらが向いているのか」を判断したらいいのでしょうか?
以下の5つの視点から、一緒に整理してみましょう。
本人の気持ち
まずは何より、「本人がどうしたいと思っているか」を確認しましょう。
介護の主役は、やはりその人自身。
無理に納得させたり、急いで決めたりせず、本人の思いに耳を傾けることが大切です。
介護者の心と体の余裕
在宅介護は、想像以上に体力・精神力を使います。
すでに限界がきているなら、「自分のためにも施設を考える」ことは、決して罪ではありません。
無理を重ねると、共倒れになってしまいます。
家族のライフスタイル
仕事、子育て、通勤時間、家の場所…。
それぞれの家庭に、それぞれの生活があります。
在宅介護を続けるには、家族全体の時間の使い方にも大きく関わってきます。
無理のない暮らしの中に介護を組み込めるかどうか。
冷静に見つめてみましょう。
経済的な面
在宅・施設、どちらにも費用はかかります。
施設の場合は入所費用や月額利用料が必要ですが、
在宅でも介護サービスの利用料や住宅の改修費がかかることもあります。
一時的な負担だけでなく、「何年続くか分からない」という視点で、
長期的に見た経済設計が必要です。
地域のサービスや施設の状況
住んでいる地域によっては、介護サービスの充実度に差があります。
「デイサービスの送迎が来ない地域」
「施設の空きがまったくない」といった事情があることも。
自治体の介護保険課や、地域包括支援センターに相談して、
使える支援を確認しておくことが大切です。
[PR]家族で話し合うときのコツ
在宅か施設か―
これは、ひとりで決めるには大きすぎるテーマです。
だからこそ、家族でしっかり話し合うことが大切です。
感情ではなく事実で話す
感情や気持ちをぶつける形ではなく、
「週に3回の入浴介助が限界に近づいてる」
「このままだと仕事との両立が難しい」
といったように、現実に起きている事実をもとに冷静に伝えることが、
話し合いを建設的にしてくれます。
“誰かが悪者”にならないようにする
お互いがお互いを責め合う空気になると、話し合いは破綻してしまいます。
大切なのは、全員が「どうすればみんなが納得できるか」を考えること。
誰かが我慢することでバランスが取れている状態は、長く続きません。
専門家の第三者を交えてもOK
地域包括支援センターの職員さんや、ケアマネジャーさんに同席してもらって話すと、
家族の誰かが偏った意見に引っ張られることも少なくなります。
冷静な視点で整理してくれる第三者の存在は、意外と大きな助けになるものです。
[PR]最後に
在宅介護と施設介護。
どちらにもメリットとデメリットがあります。
だからこそ、「迷う」のは当然のことです。
そして、「立ち止まって考える時間」を持つことは、
むしろとても大事なプロセスです。
大切なのは、あなたの家族にとって、今、そしてこれからをどう生きたいかを考えることです。
「こうしなきゃいけない」に縛られすぎず、
「どうしたらみんなが幸せでいられるか」に目を向けていけたら
その選択は、きっと正しい道になると思いますよ。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 全国老人福祉施設協議会「特別養護老人ホームの現状と課題」
- 日本在宅医療学会「在宅医療の実態調査報告書」
- 東京都福祉保健局「高齢者施設の種類と特徴」
- 独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)「施設介護の役割と選び方」
- 公益社団法人 認知症の人と家族の会「施設選びと本人の気持ち」




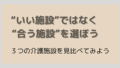


コメント