こんにちは。
在宅介護って、家族のぬくもりを感じられる一方で「ヒヤッ」とする瞬間も多いですよね。
気を付けているつもりでも、ちょっとしたすき間から事故が起きてしまうことがあります。
実際、在宅介護で多い事故は大きく分けて「転倒」「入浴」「窒息」の3つ。
どれも日常の中で起きやすく、ちょっとした工夫や対策でリスクを減らせるものなんです。
この記事では、介護をしているご家族が「なるほど、これなら今日からできそう」
と思えるような視点で、それぞれの事故の原因と対策をご紹介していきます。
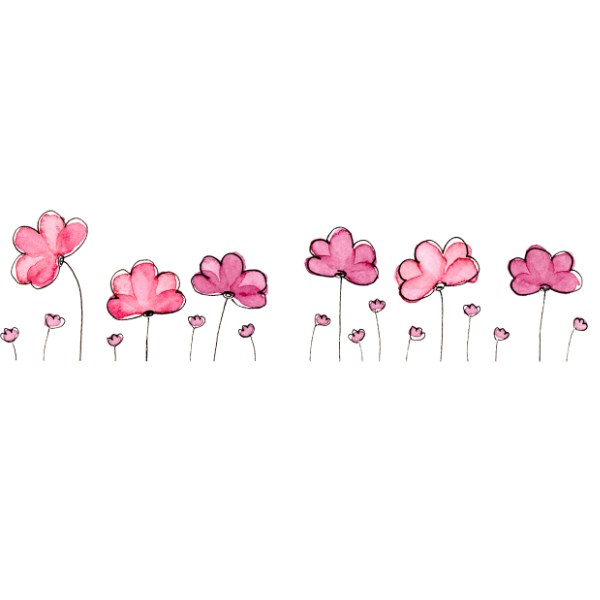
転倒事故:家の中が意外と危険スポットだらけ!
まず一番多いのが「転倒」。
実は、病院や施設よりも自宅での転倒事故の方が多いとも言われています。
特に高齢になると筋力やバランス感覚が落ちて、
ほんの小さな段差やカーペットのめくれが命取りになることも…。
骨折をしてしまうと、そのまま寝たきりにつながることもあるので、
できるだけ防ぎたい事故の一つです。
転倒の原因は?
転倒の原因は「身体的な要因」と「環境的な要因」があります。
身体的な要因としては、筋力低下や視力の衰え、認知症による判断力の低下など。
ちょっと立ち上がるときや、夜中にトイレに行こうとする時に、ふらつきやすくなります。
環境的な要因は、家の中に潜む“つまずきポイント”。
玄関の段差、滑りやすいフローリング、コードが床に伸びている、家具の配置が狭い…などなど、
私たちが普段は気にならないことが、介護を受ける方にとっては
大きなハードルになってしまうんです。
[PR]転倒を防ぐための工夫
「全部完璧に!」と思うと大変ですが、できるところから始めれば十分。
たとえばこんな工夫があります。
まず、床に物を置かないこと。
新聞やスリッパ、延長コードなどは意外とつまずきやすいんです。
コードは壁際にまとめるか、コードカバーを使うと安心です。
段差には手すりを設置するのがおすすめ。
玄関やトイレ、廊下など「よく通る場所」にあると安心感が違います。
手すりをつけるのが難しい場合は、突っ張り式の簡易手すりでも十分役立ちますよ。
夜のトイレ移動には足元を照らすライトを活用。
暗い中で歩くのはとても危険なので、
人感センサー付きのライトを置くだけでも事故のリスクが減ります。
それから、靴下やスリッパにも注意。
滑り止め付きのものを選ぶだけでも、転倒の可能性はグッと下がります。
おしゃれよりも安全第一!ですね。
入浴中に起きやすい事故の種類
よくあるのは、浴室での転倒。
床が濡れていて滑りやすく、立ち上がる時にバランスを崩すことが多いです。
それから、長湯での意識消失や心臓への負担による事故も見逃せません。
実際に、入浴中の急変が原因で救急搬送されるケースは少なくないんです。
そして「ヒートショック」。
急な温度差によって血圧が上下し、失神や心筋梗塞、脳梗塞を引き起こすリスクがあります。
特に冬の寒い脱衣所や浴室は危険度が高いポイントです。
事故を防ぐための環境づくり
まずは「温度差を減らす」ことが大切。
入浴前に浴室を暖房器具やシャワーで温めておくだけでも違います。
脱衣所に小型の暖房機を置くのも効果的ですよ。
床には滑り止めマットを敷きましょう。
ホームセンターなどで安価に手に入るので手軽に始められます。
また、浴槽の出入りには「浴槽手すり」や「バスボード」がとても便利。
自力での出入りがスムーズになり、転倒リスクがぐっと下がります。
さらに、入浴時間は長くならないように注意。
お湯の温度も高すぎると血圧の変動を招きやすいので、40度前後のぬるめがおすすめです。
「熱いお風呂が好き」という方も多いですが、体への負担を考えると少し控えめが安心です。
[PR]介助するときのポイント
家族が入浴を手伝う場合は、見守りがとても大切です。
完全に付き添うのが難しいときでも、声をかけながら様子を確認するだけでも安心感が増します。
「のぼせてない?」「足元気を付けてね」と、やさしい声掛けを習慣にするといいですね。
どうしても心配なときは、デイサービスでの入浴や訪問入浴サービスを利用するのも一つの方法。
プロの介護スタッフが安全にサポートしてくれるので、ご家族の負担も減ります。
お風呂は心と体を整える大切な時間。
ちょっとした工夫で「気持ちいい」と「安全」を両立できるので、
ぜひ無理のない範囲から取り入れてみてください。
窒息事故:食事中の「むせ」が命に関わることも
「ごほっ、ごほっ」と食事中にむせるのは、高齢の方にはよくあること。
でも、この“よくあること”が油断ならないんです。
むせただけで済めばいいのですが、食べ物や飲み物が気管に詰まってしまうと窒息につながり、
命の危険すらあります。
[PR]窒息が起きやすい原因
高齢になると、飲み込む力(嚥下機能)が弱くなります。
喉の筋肉が衰えることで、うまく飲み込めずに気管へ入ってしまうんですね。
さらに、認知症によって「よく噛まずに飲み込んでしまう」ことや、
早食いの習慣がリスクを高めます。
食材の形状にも注意が必要です。
例えばお餅やパン、こんにゃくゼリー、肉の塊などは特に窒息しやすい食品。
誤嚥性肺炎の引き金にもなるため、食事内容には気を配りたいところです。
窒息を防ぐ工夫
まず大切なのは「食べやすい形にする」こと。
肉や野菜は小さく刻む、柔らかく煮る、またはミキサーを使ってペースト状にするのも有効です。
最近では介護食やソフト食がスーパーやドラッグストア、ネットでも手に入るので、
無理なく取り入れられます。
とろみをつけるのも効果的。
お茶やスープなどの液体はそのまま飲むと気管に入りやすいので、
専用のとろみ剤を使うと飲み込みやすくなります。
食事の姿勢も重要です。
背もたれにしっかり座り、顎を少し引いて飲み込むことで誤嚥しにくくなります。
寝転んだまま食べるのは絶対に避けましょう。
また、急がずゆっくり食べる習慣をつけることも大切です。
ご家族が一緒に食べながら「ゆっくりでいいよ」と声をかけると安心して食べられますよ。
[PR]もし窒息してしまったら
万が一食べ物が詰まってしまったら、すぐに対応する必要があります。
基本は背部叩打法(背中を強く叩く方法)や腹部突き上げ法(ハイムリック法)ですが、
これは慣れていないと難しいもの。
自治体や地域包括支援センターで行われる救急法の講習に参加しておくと安心です。
いざというときに落ち着いて行動できるように、
家族みんなで知識を共有しておくと心強いですね。
最後に
在宅介護で起きやすい3つの事故、転倒・入浴・窒息についてご紹介しました。
どれも「ちょっとした日常の中」に潜んでいるリスクでありながら、
命に関わることもある大きな事故です。
大切なのは「事故をゼロにする!」と肩肘を張るよりも、
小さな工夫を重ねて安心できる暮らしをつくることです。
転倒には手すりや照明、入浴には温度差対策や滑り止め、窒息には食事形態の工夫やとろみ。
それだけで事故のリスクはぐっと減ります。
どれも日常生活の中で起こりやすいからこそ、事前の工夫で大きな安心につながります。
介護はどうしても「大変」「しんどい」と感じる場面が多いですし、
「守らなきゃ」「事故を防がなきゃ」と力が入りがち。
でも、完璧を目指すと疲れてしまいますよね。
大切なのは「できることから、できる範囲で」。
小さな工夫を積み重ねるだけで、ご本人も家族も安心できる暮らしに近づいていきます。
この記事が、みなさんの介護生活にちょっとでも役立つヒントになれば嬉しいです。
今日からできる工夫を一つでも取り入れて、安心で笑顔の多い毎日を過ごして下さいね。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 「転倒予防の取り組み」厚生労働省
- 「高齢者の入浴事故(ヒートショック)対策」健康長寿ネット
- 「嚥下・誤嚥対策の指針」日本摂食嚥下リハビリテーション学会




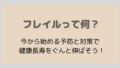

コメント