こんにちは。
「できることなら、家で介護をしてあげたい」
そんな思いから、在宅介護を選ぶご家族はとても多いです。
でも、実際に始めてみると「こんなに大変だとは思わなかった」「どこまで頑張ればいいの?」
と、壁にぶつかることも少なくありません。
この記事では、在宅介護でできること・できないことの「現実」と、
在宅介護の限界ラインや判断ポイントをわかりやすく解説していきます。
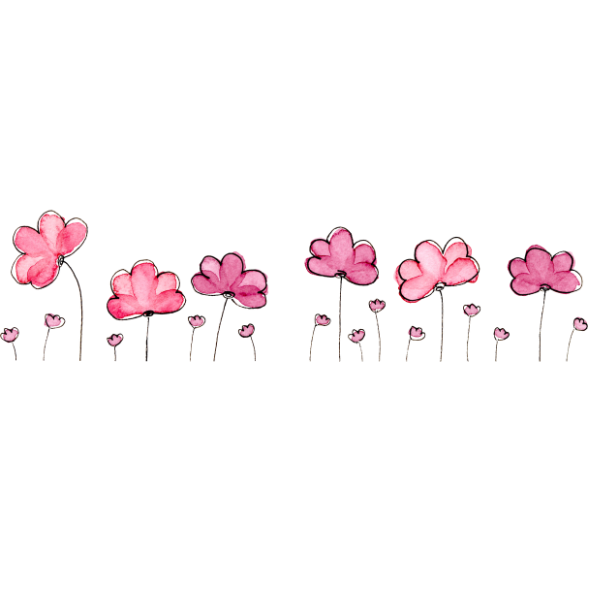
在宅介護って、そもそもどこまでできるの?
在宅介護には「限界がある」と言われますが、実際のところ、どこまでできるのでしょうか。
実は、要介護5のような重度の方でも、家族や訪問サービスを上手に使えば、
在宅介護を継続することは可能です。
とはいえ、実際には「介護する人の体力・気力・経済力」「介護される人の状態や性格」
「家の構造」など、さまざまな要素が関係してきます。
つまり、「できるかどうか」よりも「続けられるかどうか」が大切な視点になるのです。
在宅介護は、“続けられる仕組み”があるかどうかがカギです。
在宅介護の限界ラインとは?
在宅介護の限界は、「本人の状態」だけでなく、「家族側の限界」が重なることで訪れます。
家族の体力・時間が尽きるとき
- 夜中のトイレ介助で睡眠が取れない
- 仕事を辞めなければならなくなった
- 自分の病気・体調不良が悪化してきた
これらは、在宅介護の限界を知らせる“サイン”のひとつです。
介護内容が専門的になってきたとき
- 点滴や吸引などの医療的ケアが必要になった
- 誤嚥・転倒リスクが高くなった
- 認知症の進行で24時間の見守りが必要に
このような状態になると、専門のスタッフが常駐する施設でのケアが望ましいケースもあります。
精神的な限界が見えてきたとき
- 気がつけばため息ばかり…
- ちょっとしたことで怒ってしまう
- 「早く終わってほしい」と思う自分に罪悪感がある
介護うつや燃え尽き症候群のサインかもしれません。
自分を責めず、「限界だ」と認めることも、家族として大切な判断です。
在宅介護には、ゴール設定がとても大切。
「無理をしない」「助けを求める」「施設も選択肢にする」ことは、立派な介護の姿です。
判断ポイント① 家族が“笑顔”でいられるか?
在宅介護は、本人のためだけでなく、家族の人生とのバランスが大切です。
「仕事を辞めたけど、イライラばかり」「寝不足で笑顔が出ない」——
そんなときは、もう頑張りすぎている証拠。
たとえば、こんなチェックをしてみてください:
- 1日3回以上「つらい」「疲れた」と口にしている
- 趣味や友人との時間がなくなった
- 以前の自分らしさが感じられない
ひとつでも当てはまったら、見直しのタイミングかもしれません。
判断ポイント② 安全が守れているか?
在宅介護で一番大切なことのひとつは、「本人が安全に暮らせているかどうか」です。
たとえば、こんな状況が続いていませんか?
- 夜間の徘徊があり、家族が寝られない
- トイレや入浴中に転倒しそうになったことがある
- 火の不始末や飲み込み事故が起こりかけた
これらは、一歩間違えば命に関わるリスクがあります。
在宅での安全確保が難しいときは、施設での見守りを選択することも必要です。
「大丈夫」だと思っていても、小さなヒヤリが増えてきたときこそ、見直しのサインです。
[PR]判断ポイント③ 専門サービスで補えるか?
「もう限界かも…」と思っていても、地域の支援サービスを上手に使えば、
在宅介護を続けられる場合もあります。
在宅介護を支える主なサービス
- 訪問介護(ホームヘルパー)
- 訪問看護・訪問入浴
- 通所介護(デイサービス)
- ショートステイ(一時的な宿泊)
- 小規模多機能型居宅介護
介護保険のケアマネジャーに相談すれば、状況に合ったプランを組んでもらえます。
ただし、こんな場合は限界かも
- 週7日のサポートを入れても足りない
- 日中・夜間ともに介護が必要で、家族の負担が軽減されない
- 本人がサービス利用を拒否し、家族だけが抱え込んでいる
“サービスで補えるか”が、在宅継続か施設移行かの分かれ道になります。
[PR]判断ポイント④ 将来の見通しが立つか?
在宅介護をする上で、「これから先どうなるのか」も大切な判断材料です。
たとえば:
- 今は歩けるけど、いずれ寝たきりになるかも?
- 認知症が進行してきたら、どう対応する?
- 介護者(家族)が高齢化したときは?
中長期の見通しを立てることで、早めに準備・相談ができます。
また、無理にギリギリまで頑張って限界を超えてしまうと、事故や共倒れのリスクが高まります。
「いま何ができて、どこまでなら続けられるか」
そして「いずれはどうなるか」も見据えておくことが、安心につながります。
在宅介護でできること・できないことリスト
在宅介護でできること
- 日常の介助(食事・トイレ・着替えなど)
- 簡単な見守り
- デイサービスやヘルパーとの併用
- 家族の愛情ある関わり
在宅介護では難しいこと
- 医療的な処置(点滴・吸引・胃ろうなど)
- 24時間対応の見守り
- 暴言・暴力など認知症による問題行動の対応
- 重度の寝たきりや褥瘡(じょくそう)管理
「頑張ればできるかも」と思っても、それを何ヶ月、何年と続けられるかが重要です。
限界を迎える前にできること
限界を迎えてから施設を探すと、「空きがない」「費用が合わない」「急すぎて準備できない」
というトラブルになりがちです。
今からできる備え
- 施設の種類を調べておく
- 近隣の施設を見学・資料請求しておく
- ケアマネジャーと定期的に相談する
- 家族会議をして、今後の方向性を共有する
「いつかのために、情報だけでも持っておく」ことが、大きな安心になります。
[PR]最後に
在宅介護には、あたたかさと、やさしさがたくさん詰まっています。
でも、同時に限界もあるという現実からは、目をそらさないで下さい。
一人で抱え込まずに、相談したり、頼ったり、休んだりすることも、
介護の大切な一部だと思います。
どうか限界を迎える前に気づいて下さい。
そして、自分の笑顔も大切にして下さい。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 厚生労働省「令和4年版 高齢社会白書」より抜粋
- 東京都福祉保健局「在宅介護の限界を迎える前にできること」
- 全国在宅医療推進協議会「在宅ケアにおける限界と判断基準」
- 日本介護福祉士会「介護者のストレスとサポート体制」
- NHK福祉ネットワーク「介護者の“がんばり過ぎ”に気づくサイン」
- 朝日新聞「在宅介護の限界と施設入所のタイミング」特集記事

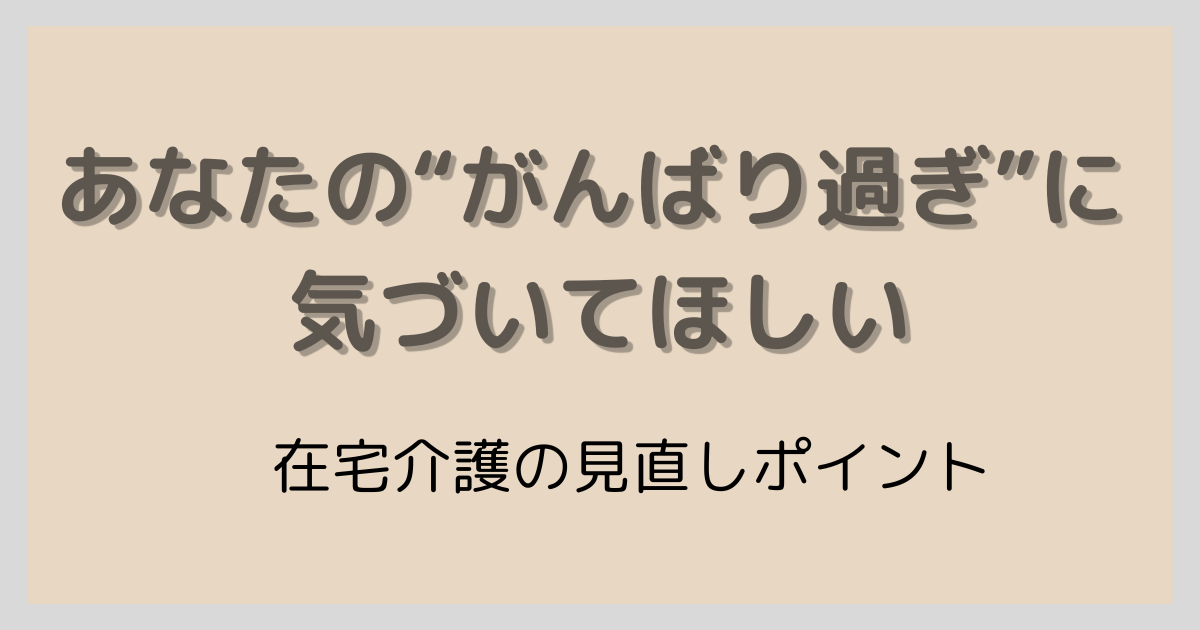


コメント