こんにちは。
「同じ日本なのに、どうしてこんなに違うんだろう?」
介護に関わる中で、こんな疑問を感じたことはありませんか。
特に多いのが、「都会と地方では、受けられる介護サービスに差がある気がする」という声です。
実際に調べてみると、その“気がする”は、あながち間違いではありませんでした。
今回は、都会と地方で介護サービスにどんな違いがあるのか、
そして、その背景にどんな事情があるのかを分かりやすくお伝えします。
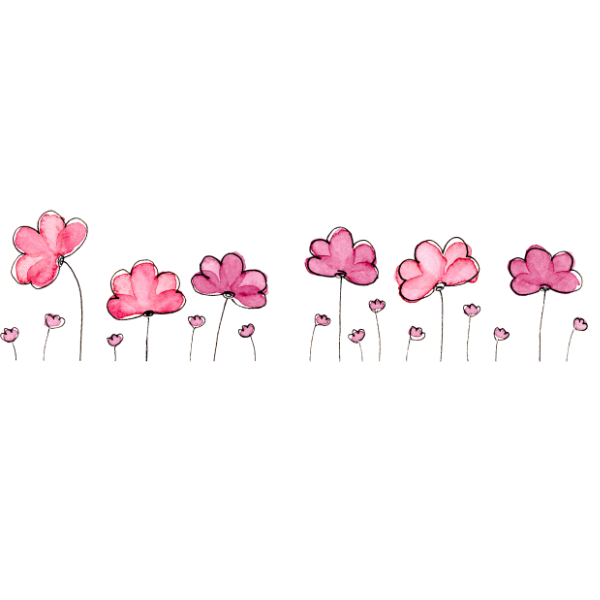
都会と地方でどう違う? 介護サービスの基本事情
事業所の数が圧倒的に違う
まず大きな違いとして挙げられるのが、介護サービスを提供する事業所の数です。
都市部では、デイサービスや訪問介護、訪問看護、ショートステイなど、
選択肢が比較的豊富にそろっています。
「合わなかったら別のところを探す」ということもしやすい環境です。
一方で地方では、「そもそも選べるほど施設がない」
「一番近い事業所でも車で30分以上かかる」といったケースも珍しくありません。
これは人口密度の違いだけでなく、人手の確保や経営面など、
事業者側の事情も大きく影響しています。
サービス開始までのスピード
都市部では事業所が多いため、
条件が合えば比較的スムーズにサービスを始められることが多いです。
一方、地方では「空きがない」「人手不足で受け入れができない」といった理由から、
希望してもすぐにつながらないケースがよくあります。
「デイサービスを使いたいけれど、今は3か月待ち」
こんな状況は、地方では決して珍しい話ではありません。
サービスの質・専門性
都市部では、医療ニーズの高い方に対応した医療対応型デイサービスや、
リハビリに特化した施設、認知症専門のユニットなど、
より専門性の高いサービスが増えてきています。
その一方で地方では、多くのニーズに対応する「多機能型」や「一般向け」のサービスが
中心になりやすく、専門的な支援が必要な場合、選択肢が限られてしまうことがあります。
ケアマネジャーの数と質
ケアマネジャーは、介護を進めるうえでの“道しるべ”のような存在です。
都市部では、経験豊富なケアマネジャーが複数在籍している事業所も多く、
相性を見ながら担当を選べることもあります。
しかし地方では、慢性的な人材不足が続いており、
一人のケアマネが多くの利用者を抱えているケースも少なくありません。
地域によっては、経験の浅いケアマネが現場を支えざるを得ない状況もあります。
「介護が必要」=「すぐ使える」とは限らない現実
実際に使おうとすると「思っていたのと違う」と感じる人が多いのも事実です。
制度は同じでも、受け取れるサービスやスムーズさには、
どうしても地域ごとの差が生まれてしまいます。
その理由を、もう少し詳しく見ていきますね。
地域密着型サービスの限界
介護保険には「地域密着型サービス」と呼ばれる仕組みがあります。
これは、住んでいる市区町村の中でのみ利用できるサービスで、
小規模多機能型居宅介護や認知症対応型グループホームなどが含まれます。
「住み慣れた地域で暮らし続ける」ための制度ではありますが、
地方では、そもそも該当する施設がなかったり、数が極端に少ないこともあります。
人口構成の違い
都会では、比較的若い世代も多く、介護を支える側の人材が一定数確保されています。
一方、地方では高齢化率が高く、支える人の数が圧倒的に足りていません。
「やりたくても人が集まらない」
そんな理由で、新しい事業が始められない地域もあります。
行政の支援体制や予算の違い
実際の運用や支援体制は自治体ごとに差があります。
都市部では情報提供が充実していたり、相談窓口が複数用意されていることもあります。
一方で地方では、「相談できる場所が限られている」
「制度自体があまり知られていない」といった課題も見られます。
地域性による「暗黙の空気」
都会では「介護はサービスを上手に使うもの」という考え方が比較的浸透しています。
反対に地方では、「家族が見るのが当たり前」
「人に頼るのは申し訳ない」という空気が残っていることもあります。
こうした価値観の違いも、サービス利用のしやすさに影響しています。
地域に合った介護のスタイルを探そう
どの地域にも、その土地なりの強みがあります。
完璧な環境でなくても、情報と工夫で補えることはたくさんあります。
地域包括支援センターを積極的に活用する
どの地域にも必ず設置されているのが、地域包括支援センターです。
「この地域ではどんなサービスが使えるの?」
「今、空きのある施設はある?」
そんな素朴な疑問でも、気軽に相談できます。
まずは1本電話をかけるだけで、今いる地域の“現実”が見えてくるかもしれません。
少しだけ視野を広げてみる
住んでいる市区町村に希望のサービスがない場合、
周辺地域まで視野を広げることで選択肢が増えることもあります。
「隣の町なら空きがある」「車で30分なら通えそう」
そんなケースも意外とあります。
オンラインやテレケアの導入
最近では、オンライン診療やリモートリハビリ、オンライン相談など、
距離を補う仕組みも増えてきました。
「難しそう」と感じたら、ケアマネや包括支援センターに聞いてみるのがおすすめです。
介護者同士の横のつながりを持つ
同じ地域で介護をしている人の声は、とても参考になります。
ちょっとした情報交換や、気持ちを吐き出せる場所があるだけで、
心の負担が軽くなることもあります。
ーもしもの時のために準備しておくと安心ですー
[PR]最後に
全国一律の制度であっても、介護サービスの“使いやすさ”や“選択肢の多さ”は、
地域によって驚くほど違います。
大切なのは、自分が住んでいる地域の特徴を知ることと、
その中で「今できる最善」を見つけていくことです。
介護は、情報とつながりで選択肢が広がります。
「うちは田舎だから仕方ない」とあきらめず、
「じゃあ、何ができるかな?」と考えることが、地域差を乗り越える第一歩です。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
ー日用品や重い荷物も玄関先まで届けてくれますよー
参考
- 総務省|過疎地域における高齢者福祉の実態調査
- 国立社会保障・人口問題研究所「地方の介護人材確保に関する課題」
- 日本経済新聞|地域差広がる介護の現場、担い手不足の実態
- 厚生労働省「介護保険制度の地域差とサービス提供体制について」
- 公益財団法人介護労働安定センター「都道府県別の介護人材状況」
- 全国老人福祉施設協議会「施設不足と待機者問題」



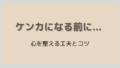


コメント