こんにちは。
「なぜ私ばかりが…」
親の介護に関わるきょうだい間で、そんな不満やモヤモヤを抱えていませんか?
介護は家族みんなで協力して…という理想はあっても、
現実には誰か一人に負担が集中してしまうことが多いものです。
特に長男だから、実家に近いから、専業主婦だから…といった理由で、
「なんとなく」介護を引き受けてしまい、
気づけば何年も一人で頑張り続けているという方も少なくありません。
今回は、きょうだい間で介護の負担が偏ってしまう理由や背景を整理したうえで、
「じゃあ、どうしたらいいの?」という対処法や、負担を感じたときの伝え方、
そして関係性を壊さずに協力体制を築いていくためのヒントをお届けします。
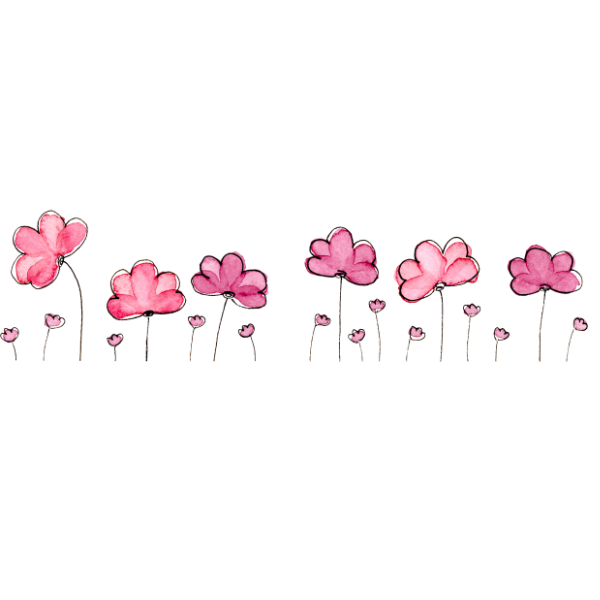
なぜ、介護の負担が偏るのか?
まずは原因を冷静に見てみましょう。
介護の負担が偏ってしまう背景には、以下のような要因があることが多いです。
距離的・物理的な理由
実家の近くに住んでいるきょうだいは、どうしても「何かあったらお願いね」と頼られがちです。
特に親が急に体調を崩したときや、通院の付き添い、ちょっとした買い物など、
細かなサポートは近くの人に集中しやすくなります。
性格や家族内の「役割」
昔から「しっかり者」「優しい」「頼りにされる」といった立ち位置だった人が、
自然と介護を背負ってしまうことも。
逆に、「あの子は昔から自由人だから」「仕事が忙しいから仕方ないよね」と、
他のきょうだいが免責されてしまうケースも見られます。
親の希望
親自身が「○○(長女・長男)に頼みたい」と口にしてしまうことも負担の偏りにつながります。
「あんたには何でも話せるから」と言われると、つい断れない気持ちにもなってしまいますよね。
経済的な格差
収入差やライフスタイルの違いから、「時間のある人がやって」「お金のある人が負担して」と
暗黙の了解ができてしまうこともあります。
[PR]心の中のモヤモヤを無視しないで
介護に関わっていると、「みんな頑張ってるんだから」「私がやるしかない」と、
自分の気持ちを後回しにしてしまいがちです。
でも、それは決して長続きしません。
・なぜ私ばかりがやっているのか?
・どうしてあのきょうだいは何も言わないのか?
・親に文句を言うわけにもいかないし…
そんな想いが積み重なっていくと、やがて爆発してしまったり、
きょうだい間の関係がギクシャクしてしまうことも。
「もう限界…」となる前に、自分の感情に気づき、整理し、
少しずつでも発信していくことが大切です。
「不満」を「提案」に変える伝え方
介護の負担が偏っていると感じたとき、つい感情的に「なんで私ばっかり!」
と言いたくなってしまいますよね。
でも、その言い方では相手も心を閉ざしてしまい、話が前に進まないことも。
まず大切なのは、「不満」を「お願い」や「提案」に変えて伝えることです。
NGな言い方
・「どうして何もしてくれないの?」
・「いつも私だけじゃん!」
・「自分の親なのに他人事なの?」
OKな言い方
・「最近ちょっと疲れてきちゃって…できれば○○を手伝ってもらえないかな?」
・「一緒に話し合う時間があると嬉しいな」
・「お金のことやサービスのこと、どう思う?」
相手を責めずに、自分の「今の気持ち」や「具体的な希望」を伝えるだけでも、
関係性はずいぶん違ってきます。
[PR]話し合いの場を作るコツ
家族会議を開こうとしても、なかなか日程が合わなかったり、
「話し合いなんて大げさだよ」と避けられてしまうこともあります。
形式にこだわらなくてOK
「家族会議」と銘打たずに、ちょっとした電話やLINE、ビデオ通話でもOK。
「この前のお母さんの病院、どうだった?」「ちょっと相談したいことがあるんだけど…」
といった軽い入り口から話題を広げていきましょう。
資料や状況を共有する
「今、週にこれだけ通院があって、これくらいの時間がかかってる」
「サービス利用料はこのくらい」など、
なるべく具体的な数字やスケジュールを共有すると、
相手も現実味を持って受け止めやすくなります。
第三者を交えるのも手
どうしても感情がぶつかってしまう場合は、
ケアマネジャーさんや地域包括支援センターの職員など、
専門職の方に間に入ってもらうと冷静に話し合いができることもあります。
[PR]分担のパターンは一つじゃない
「介護を平等に分け合う」と言っても、何をどのように分担するかは家庭によってさまざま。
いろんな形の協力があります。
時間を分ける
週末だけ手伝いに来てもらう、病院の付き添いを交代制にするなど、
役割を時間で分けるパターン。
仕事や育児との両立が難しい人にも向いています。
役割を分ける
・Aさん:日常の見守りや買い物
・Bさん:金銭管理と施設探し
・Cさん:定期的な面会と親の話し相手
それぞれの得意分野や事情に合わせてできることを分担するだけでも、
偏りはかなり改善されます。
費用負担で協力する
「介護はできないけど、その分、経済的には支えるよ」というスタンスも十分な協力の形です。
誰が何をどのくらい負担しているのかを見える化しておくと、不公平感も少なくなります。
[PR]家族関係を壊さないために
介護の話し合いは時に、
きょうだい間の価値観や過去のわだかまりを浮き彫りにすることもあります。
でも、親の介護がきっかけで家族関係が壊れてしまっては本末転倒。
・意見が違うのは当然
・完璧はない
・「無理しない」「責めない」「求めすぎない」
この3つを心がけるだけでも、ぐっと関係性はラクになります。
どうしても分かり合えないときは
話し合っても協力が得られない…という現実に直面することもあります。
そんなときは、「理解されること」をゴールにしすぎず、
「自分が潰れないための工夫」を優先しましょう。
公的サービスを最大限に活用する
介護保険サービスを利用して、できる限り自分の負担を軽減する。
訪問介護、デイサービス、ショートステイなど、
プロの力を借りることは決して「甘え」ではありません。
愚痴を吐ける場所を持つ
信頼できる友人、カウンセラー、介護者の会など、「共感してもらえる場所」があるだけで、
気持ちの整理がグッとしやすくなります。
最後に
きょうだいで介護の負担が偏るのは、ある意味「自然なこと」でもあります。
人生のタイミング、価値観、距離、事情…それぞれ違う中で「公平」を求めるのは、
とても難しいものです。
でも、「みんなで一緒に支える方法はないか?」と模索することで、
少しずつでも歩み寄れることもあります。
もし今、「なんで私ばっかり…」と思っているなら、その気持ちにフタをせず、
少しだけ立ち止まってみてください。
そして、できることから一つずつ。
話してみること、頼ってみること、自分の時間を取り戻すこと。
それが、介護と家族との距離感を健やかに保つための大切な一歩です。
あなたの介護が、少しでも軽く、あたたかいものになりますように。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 東京都福祉保健局「家族間の介護負担とその調整に関する手引き」
- 公益社団法人 認知症の人と家族の会「介護負担の不公平に悩む声」
- 内閣府「高齢社会白書(家族内の役割と意識調査)」
- 介護労働安定センター「兄弟姉妹間の介護協力に関する調査結果」
- All About介護「親の介護を一人で抱え込まないために」
- NHKハートネット「きょうだいで向き合う介護問題」


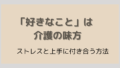
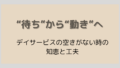

コメント