こんにちは。
介護をしていると、同じ話を何度も聞くことってありますよね。
「昔の話ばっかり、何回聞いたか分からないよ〜」なんて、
つい心の中でため息をつきたくなることも…。
なぜ高齢になると「昔の話」を繰り返すのでしょうか?
今回は、「昔ばなし」がもつ意味や背景、そして相手の心をほんのりとほどく会話術について、
やさしくご紹介していきます。
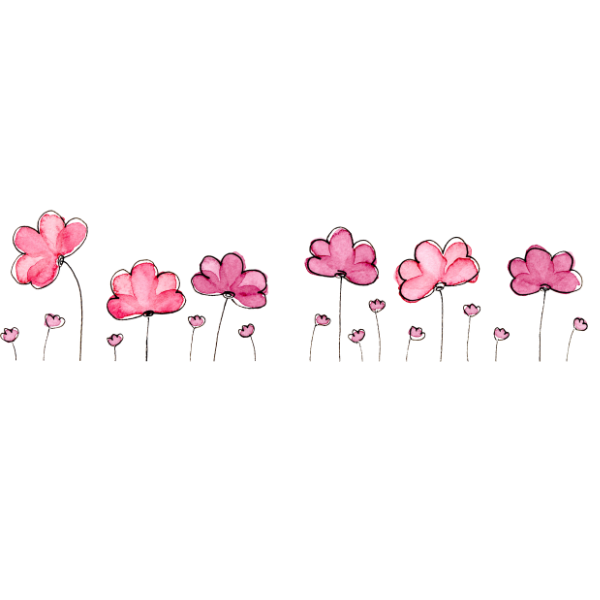
なぜ「昔の話」ばかりになるの?
高齢者が過去の話を繰り返す理由には、いくつかの心理的・生理的背景があります。
短期記憶より長期記憶が残りやすくなる
加齢によって、最近の出来事を記憶する「短期記憶」は少しずつ弱くなっていきます。
一方で、子ども時代や若いころの記憶は「長期記憶」として脳に深く刻まれているため、
思い出しやすくなるんです。
たとえば、「朝ごはんは何食べた?」と聞かれても思い出せないのに、
「子どもの頃のお正月はね…」という話はスラスラ出てくる。
そんな現象に心当たりがある方も多いのではないでしょうか。
自分の存在を再確認したい気持ち
人は誰でも、「私はここにいていい存在なんだ」と感じられることで安心します。
「昔の話」は、人生の中で自分が輝いていた時代や、
意味のある出来事を思い出すきっかけになります。
それを誰かに話すことで、
「ああ、自分は確かに生きてきたんだ」と確かめているのかもしれません。
相手との距離を縮めたい
「昔ね、こんなことがあってね…」
そんな語り口は、どこか懐かしく、あたたかい空気を生み出します。
過去の話をすることで、相手と心を通わせようとしているのです。
つまり、「昔話=ただの繰り返し」ではなく、
「心を開いてくれているサイン」かもしれないのです。
不安や孤独を和らげたい
加齢や病気、生活環境の変化などで、心が不安定になることもあります。
そんなとき、過去の「安心できた記憶」に戻ることで、
今の不安をそっとやわらげているのかもしれません。
昔話は、本人にとって“心の避難所”になっていることも多いんです。
安心を引き出す「聴き方」のコツ
「またその話…」と内心つぶやきたくなる気持ち、よくわかります。
でも、その会話の中には、本人が誰かに聞いてほしい「大切な記憶」が込められていることも。
ちょっとした「聴き方」の工夫で、相手の安心感はぐんと増していきます。
驚いたふりでもOK!リアクションで共感を
話の内容が分かっていても、初めて聞くように
「へぇ〜!」「それはすごいね!」とリアクションしてみましょう。
ほんの少し大げさでも大丈夫。
リアクションは「あなたの話をちゃんと聴いてるよ」という安心のサインになります。
話のキーワードを拾って、質問してみる
たとえば、「昔は毎朝5時から畑に行ってたんだ」という話なら、
「5時ってすごく早いね!そのあと朝ごはんはどうしてたの?」など、
自然な質問を添えると、会話がふくらみます。
相手は「ちゃんと聞いてくれてるんだな」と感じて、さらに心がほどけていきます。
「聞き役」になりきらなくていい
介護をしていると、つい「全部を聞いてあげなきゃ」と思いがち。
でも、ときどきは自分のことを話しても大丈夫です。
「うちの祖母もそんな話してたなぁ」
「それ聞くと、小学校の遠足思い出すよ」
そんな風に、自分の思い出もそっと挟むことで、「対話」になります。
共通の思い出があれば、それを一緒に味わおう
親や祖父母と、共通の昔の話があるならチャンスです。
「お祭りで焼きそば食べたね」「あの時、雨に降られたっけ」など、
記憶を一緒にたどることで、心の距離はぐっと近づきます。
ときには「話の終わり方」も意識してみて
終わりが見えない話が続くと、こちらも疲れてしまいますよね…。
そんな時は、「じゃあその話、また続きを聞かせてね」と
優しく切り上げるのもひとつの方法です。
無理しないことは、お互いの心を守るためにも大切なんです。
[PR]認知症と「昔話」を混同しないために
「同じ話ばかりする=認知症」ではありませんが、
最近のことをまったく覚えていない、会話のつじつまが合わないなど、
他のサインとあわせて気になることがあれば、一度専門機関に相談してみるのも大切です。
とはいえ、たとえ認知症であっても、「昔の記憶」は比較的よく残っていることが多く、
その話題が本人にとっての安心材料になることは変わりません。
「認知症だから昔話ばかり」ととらえるよりも、今できる会話の形を大切にする視点があると、
介護の負担感も少し和らぎます。
「会話のストレス」を減らす工夫
介護者として、毎日聞き役に徹するのは正直しんどいですよね…。
そんなときは、こんな工夫を試してみるのもおすすめです。
「話し相手」を増やす
家族以外との交流の場を持つことで、話し相手が広がり、昔話の“聞き役”が分散されます。
地域のサロンやデイサービスの活用も一つの手です。
昔の写真やアルバムを活用する
言葉で思い出せないことも、写真を見ることで記憶が鮮やかに戻ることがあります。
一緒に写真を見ながら会話をすることで、楽しく思い出を共有できる時間になります。
「話す」から「書く」へのシフト
「昔のことをノートに書いてもらう」「自分史をつくる」など、
話を記録する方向に向けるのも◎。
本人にとってもやりがいになりますし、読み返すことで会話のきっかけにもなります。
[PR]最後に
話の内容よりも、「誰かが聴いてくれている」「ちゃんと受け止めてもらえている」
——そんな実感が、高齢者にとっての一番の安心になります。
高齢者が昔の話を繰り返すとき、そこには安心したい、つながりたい、
自分を肯定したいという深い気持ちが込められています。
もちろん、毎回完璧に向き合うのは難しくても、
ときどきでもいい、少しの余裕があるときに、優しいリアクションを返してみてください。
言葉の力って、大きいんです。
介護のなかで繰り返される会話には、退屈なようでいて、かけがえのない思いが詰まっています。
今日も、あなたの優しさが、誰かの心に届いていますように。
応援しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
[PR]参考
- 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)
- 東京都健康長寿医療センター研究所「高齢者の心理と行動特性について」
- 独立行政法人 国立長寿医療研究センター「高齢者の記憶と回想法の活用」


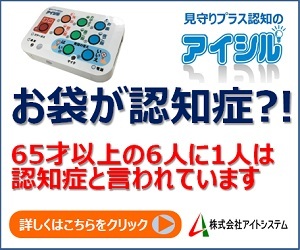
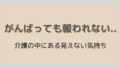
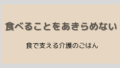

コメント